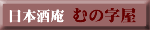
いま「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成18年8月の日々一献
★居酒屋は呑み手の学校である★18/8/30のお酒
いまは日本にも映画学校というのがあるが、まだそういうものがなかったころ、俳優であり監督でもある伊丹十三のお父さんだった伊丹万作監督が残した文章の中に、映画館こそ映画の学校だと書いてあった。
映画は教室で先生から教わるものではなく、映画館で生の映画(しゃしん)を見て感じ取るものだというのである。
能楽の野村万作だったかが弟子についてこういっていた。
分かる者はなにも言わなくてもわかる。わからない者は言っても分からない。
映画も、分かる人なら生の映画を見れば理解するところが多いが、分からない人はいくら言っても理解できないということなのだろう。
物事を理解するセンスは、いちいち先生が手取り足取り教えるものではないということである。
松竹蒲田撮影所の所長だった城戸四郎が「撮影所には小津安二郎は二人いらない」といったという。見識である。
小津安二郎(おず・やすじろう)は、後に巨匠と呼ばれるようになる監督である。そのときすでに自分のスタイルをもっていた監督である。
映画は先生が教えたとおりの映画を撮ってもしょうがないということである。また他人と同じものを撮ってもしようがないということである。新しい視点がほしい。それは学校で教えることができるものではないということである。
自分でテーマを見つけるものである。
お酒も学校で習うものではない。
ではどこで習うのか。
居酒屋で、である。
居酒屋の仕事は呑み手を教育することである。
うまいお酒という現物を実際に呑ませてあげて呑み手を育てるのである。
そういうお酒を呑めば、わかる人は分かるのである。分からない人はいくらうまいお酒を呑んでもわからないということである。
それでは不安だという人もいるだろう。
酒飲みには学年はないから、自分がどのくらいの酒飲みなのかわからないからである。
おれは少しはお酒を知っているということが自慢の人は自分が今どの程度の呑み手なのかということを確かめることができないので酒を知っているという優越感を満たすことができないからである。
そこできき酒師という資格が登場したのである。
その資格なるものを嗤う人は、学校でお酒がわかるものかという。
お酒は知識ではなくて、体験だからである。頭で理解するものではなくて、体で理解するものだからである。
そしてなぜ学校でお酒を教えないかというと、子供にお酒を呑ませるわけにはいかないこともあるが、それよりもなによりもお酒のことを知っていてもなにも役に立たないからなのである。
語りすぎるとかえって疎(うとん)んじられるのである。
そしてまた、いいお酒はどうしても本数が少ないから最高峰をだれもが味わえるものではないからである。
モナリザを見ないで絵画を語れないように、最高峰のお酒を知らないでお酒を語ることはできない。
それができないから、お酒の知識を教えることは可能であるが、お酒を教えることは不可能なのである。
酒の味わいや香水の匂いを文字で読んでその味わいを理解できるわけがない。
お酒は教えられないというわけである。
しかし、お酒は文化として連綿として呑みつづけられている。
酔っぱらうという快感と同時にお酒の心を理会しようとする情熱からである。
では呑み手はどこでお酒を知るのか。
居酒屋で、である。
現在のうまいお酒を知るのは居酒屋でなのである。
すなわち居酒屋は酒飲みの学校なのである。
だから、居酒屋はそのときどきの日本酒をしっかり見極めてほしいのである。自分で判断してうまいお酒を呑み手に提供してほしいのである。
商品には造り手の精神が反映されているから、安い酒にはそれなりの思想を、逆にすぐれたお酒には造り手の思いと技を感じることができる。
安いお酒を売るのは立ち呑み屋にでもまかせておいて、居酒屋の看板を出すのなら売るのが惜しくなるようなうまいお酒を揃えてほしいのである。
居酒屋がきちんと呑み手を教育すれば、それはやがてそのお店に行けばうまいお酒が呑めるという信用となってお店の利益となって返ってくるのである。
呑み手にとってもまた実際にそのお酒を呑んで体で覚える以外にお酒を理解することはできないということである。
呑んだことがないお酒を語ってもしょうがないからである。
さあ、能書きを読んでいてもしようがない。今夜も居酒屋に行ってお酒を学んで来よう。
書を捨てよ、居酒屋に行こう、である。

★夏は日本酒★18/8/23のお酒
タイトルは「夏は日本酒」とあるが、夏はなんてったって生ビールである。
連日の猛暑で毎日毎日いっぱいの汗をかくから、まずは生ビールで喉をうるおさないことには力が出てこない。
はらがへっては戦 (いくさ)ができないというが、まずは生ビールを飲まないと次のお酒を呑む気力もわいてこないというものである。
しかしである。連日水代わりの生ビールばかり飲んでいると、確実に疲れがたまってくるのである。
体が芯から疲れてくるのがわかる。
夏バテというが、水物を取りすぎるという食生活を何日も続けていると体力が確実に減退してくるのである。
そうなったときに呑む酒が日本酒である。
これは効く。一口呑んだだけで体に元気がみなぎるのがわかる。
夏、汗をかいて喉が渇いているときに冷たい水を飲むと、その水が喉元から全身にしみていくのがわかる。
夏のお酒もそれと同じ感覚なのである。
喉元から全身にしみわたるお酒が、体の末端から元気を回復させてくれるのがわかる。
そのときに思わず出てくる言葉が「うまい」なのである。
うまいということは身心の回復剤なのである。
だから、夏に呑むお酒は本当にうまいお酒に限る。
中途半端なお酒ではその効果が薄いからである。そういう酒ではかえって疲れてしまう。どっと気疲れしてしまうからである。
夏に呑むうまいお酒とは、例えば「天明」の純米大吟醸である。
これがうまい。
酸味と甘味と渋味のバランスがいいお酒だった。
夏場の疲れたときには良質な香りを控えめに使うことも疲れをいやす一法である。
香水の香りは三つの変化で人の気持ちをなごませてくれる。
最初にぱあーっと広がる華やかな香りがトップノート(上立ち香)である。
そしてその香りが落ち着いたところがミドルノートである。
そのときの香りが香水の本来の香りである。
やがて時間の経過とともにミドルノートもうすれていくとラストノートとよばれる地味な香りに変わっていく。
地味ではあるが、その香りはながくいつまでも残る香りである。後立ち香ということになるが、むしろそれは香りの余韻と訳したほうがいいかもれしない。
ラストノートの香りがきれいだとその人とその香水の相性がいいということになる。
トップノートやミドルノートがプンプンしている女の人には近寄りがたいが、心ひかれるのはラストノートの爽やかな人である。
だれでもいい香りと感じるトップノートやミドルノートの時の匂いはその香水が個性を発揮しているときだから、その人の香りというよりも、その香水の香りなのである。
服でいうならば、人が服に着られている状態である。
ラストノートになったときにその人の匂いとなるのである。
人が服を着こなした状態になる。
そして、香水の香りというのも、余韻の美しさなのである。
いい香水というのはその三つの香りの変化を楽しめる香りの贅沢である。
「天明」の純米大吟醸は酸味がまずうまいと感じさせるのである。
庵主は酒のうまさは酸味のうまさだと思っている。それは日本酒に限らずである。
「天明」はトップノートがいい。
そして、ミドルノートは、甘味との絡みである。
日本酒のうまさは麹が醸しだす甘味にあると思う。砂糖のような明確な甘さではなくてにじみでてくる甘さのことである。
その甘さがないと日本酒はおもしろくない。いわゆる辛口のお酒というのはその甘さがないつまらないお酒なのである。
大きな声ではいえないが、いわゆる辛口の酒なら誰でも造れるのではないかと思っている。甘味との絶妙な絡みを出す必要がないのなら醗酵をいきつくところまで進めればいいのだから。どこで搾るのかという判断が必要ないお酒なのではないかと思っているからである。杜氏いらずのお酒なのではないかという見方を庵主はしているのである。
アルコールのうまさを味わいたいのなら焼酎を呑んだほうがいいのではないかと庵主が思うのはそういう理由による。
いわゆる辛口のお酒というのは甘くない砂糖を口にするようなものなのである。
それなら人工甘味料を使った方がいいのではないかということである。
「天明」は酸味とその甘味がきれいにからんでいてうまかった。味わいにめりはりがあるということである。
香水のラストノートにあたるのは渋味である。
にがい酒とか渋い酒というのは欠点とされるが、しかし適切なそれはお酒の余韻となるのである。
ほのかに舌に残る渋味は、そのお酒を呑んだという記憶として残るのである。
「天明」の純米大吟醸にはそれがあった。
純米大吟醸だからうまいというのではない。そのバランスが絶妙にいいからうまかったのである。
「天明」はほんとうにうまくなった。
こういうお酒を真夏に呑むことができる東京の酒事情はホント幸せなのである。
タイトルを「夏は日本酒」としたが、本当は「東京のお酒」というのが最初に付けた題名だった。
東京には日本中のうまいお酒が集まってくるからである。
地方に住んでいるとこういうお酒とめぐあえる機会がないことだろう。今は、勝ち組負け組という言葉があって格差があるのが当たり前の社会になりつつあるという人もいるが、ことお酒に関しては昔からその格差は歴然としていたのである。
東京のお酒は明らかにうまいということなのである。
東京の地酒は、庵主は「喜正」意外にうまいと思うお酒を呑んだことがないが、東京にあるお酒は本当にうまいお酒が綺羅星の如く輝いているのである。
酒呑みが東京を離れられない理由である。まずいお酒だけは呑みたくないからである。

★おいしいお酒という名の幸せ★18/8/9のお酒
どんな世界でもそうだが、興味のないものはそのよさや違いがわからないものである。
なんでも知っているということは立派なことのように思えるが、そんなことはない。知らなくてもいいことをいくら知っていてもなんの役にも立たないからである。
そういう知識は時間つぶしの娯楽なのである。
かえって知らない方がいいことも少なくない。その方が幸せでいられるということである。
お酒を呑まない人や呑めない人にとっては日本酒の知識なんかなくても全然かまわないのである。知っていても役に立つことがないからである。
でも、酒呑みにとっては知っていることが即幸せにつながるから知っといることに越したことはない。知らないとうまいお酒ともめぐり会えないからである。
うまいお酒を呑む一番てっとり早い方法は、ちゃんとしたお酒を揃えている居酒屋で呑むということである。
そこでならなにも知らなくてもうまいお酒が出てくるからである。
自分で探すとなると金も暇もかかることはいうまでもない。
せっかくお酒を呑むのなら庵主はうまいお酒を呑みたい。
酔えればなんでもいいという人は酒に好き嫌いがないということで一見大人に思えるが、しかしそこが食い物と酒の違いである。
食い物の好き嫌いをいう人は子供っぽく見えるだけだが、酒はべつに呑まなくてもすむものだから、そういうものは逆に好き嫌いをハッキリ言った方が主張があっていいのである。主張がないとさびしいのである、その人間が。
アルコールだったら何でもいいということになると、かえって酒に汚いと思われてしまうから不思議である。何でもいいということは一貫性がないということで人間が小さく見えるのである。
庵主はうまいお酒しか呑まない。正しくはうまいお酒でないと呑めないのである。まずい酒はどうにも体が受け付けないからである。
庵主はお酒を楽しく呑めることをおいしいお酒と呼んでいる。いいお酒をおいしく呑めると気持ちがいいからである。
ほんのり感じられる酔いごこちはなんとなく幸せになった気分にしてくれる。
幸せな気分とは満足感のことである。生きていることの快感のことである。
うまいお酒は幸せ気分を味わえるからいいのである。安上がりな幸せであるが、お酒造りをしている人は実は幸せを醸しているということなのである。

★清酒は大丈夫か★18/8/2のお酒
又聞きであるが、2006年7月26日の「日本経済新聞」の記事によると、老舗の和洋菓子店が苦渋の値上げを余儀なくされているという。
甘い物を作っているお店が苦渋を飲まされているというのである。
なぜかというと、原油高がその原因なのだという。
原油高→代替原料にサトウキビ→砂糖高騰、という流れからなのだという。そのために十数年ぶりに羊羹・飴・饅頭などが5〜10%の値上げを余儀なくされているというわけである。
記事によると、原油価格の上昇でガソリン価格も値上がりしたため自動車燃料をサトウキビから作るエタノールに切り替える動きが世界的に広がっているためだという。
そのため、砂糖の供給が減るのではないかとの思惑から国際価格が高騰してるという。割安な代替甘味料を使うメーカーもあるが、品質重視の高級和菓子では、そうもいかないために砂糖の値上げを仕方なく受け入れているとのこと。
実際、日本橋の榮太郎は秋に全商品を2割ほど、とらやも4月から羊羹などを4%程度値上げしたという。
又聞き元は、メルマガ「あんこ便り その52」である。
それと清酒にどんな関係があるのかというかもしれないが、多くの清酒の主成分は、すなわち普通酒の主成分はサトウキビの廃糖蜜から作った醸造アルコールなのである。それがガソリン替わりに使われるようになると砂糖のように供給が減ってくるのではないかということである。
それが理由で清酒が値上がりしたら噴飯物である。日本人はガソリン相当品をあたかも酒だといって飲まされていたということであり、そんなものをお酒だと認めてきた酒造技術者の見識が物笑いのタネになるからである。
もっともそういうアルコールでも実用上は全然問題ないので、あくまでもそれを日本酒だといいはる見識を嗤うのであって、その酒自体を馬鹿にするものではないことはいうまでもない。

★「弥久」(びきゅう)がうまい★18/8/1のお酒
7月の晦日になにげなくはいったお店で呑んだお酒。
「弥久」の特別純米無濾過生原酒である。
庵主が今年呑んだお酒でピカ一である。
香りはなんとなく古臭いお酒を感じさせる。もっともそれは麹のにおいだったのだが、紹興酒のようなにおいにも似ている。老ね香といわれるにおいにも似ている。
しかし、呑んでみたらびっくりした。
においはどろくさいのに呑んでみたら意外とうまいかったというお酒はよくあることである。
当今のお酒は香りのいいお酒が多いから、においが汚れているお酒に出会うとちょっと引いてしまうが、お酒は呑んでみないと分からない。
よく、物事は下駄を履くまで分からないというが、お酒の場合は呑んでみるまでわからないということである。
庵主が「弥久」に驚いたのはその酸味のうまさである。その酸味の美しさは絶品である。
酸味と甘味がきれいに絡んだときのお酒の味わいはそれ自体が一つの美である。美術品が目で見る美だとしたら、その味は舌で見る美である。
目で見る美が自分の肉体の外部にある美だとしたら、お酒が醸しだす美は肉体の内で感じる美である。
どっちがすぐれているかと聞かれたら庵主は二者択一はしない。そんなコンピュータみたいな、西洋人か共産主義者みたいな発想はしないからである。
目で美術品を味わいながら同時にうまいお酒を呑みたいと答えるのである。
お酒はうまい酒とまずい酒が別々にあるわけではない。安い酒と高い酒という区別はうまいまずいとは別の区別であるから混同してはいけない。
酒の味わいはアルコールによって裏打ちされた連続している一つの味わいなのである。最初からうまいとまずいが別れているわけではなくてある時点からうまいと感じるようになるものだからである。
造りがうまくいかなかった純米酒に割り切ってアル添をしたら呑めるようになったということはよく聞くことである。酒の味わいは、まずいはずの酒でもそれなりにうまい酒に変えることができるということである。両者は別の物ではないということである。
お酒自体は、庵主はアルコールがあんまり呑めない体質であることから、まずいものだと思っている。しかしそのまずさを比較的にあまり感じさせない味わいのお酒があって、その場合にこのお酒はうまいと感嘆するのである。そういうお酒なら庵主にも呑めるからである。いうなれば贔屓の引き倒しをしているのである。庵主にとってかわいいお酒だけがうまいのである。
庵主に、この酒はうまいと感じさせる魔法の一振りが酸味のうまさである。うまさというよりも美しさといったほうがいい。
酸味がしっかりしていればなんでもうまいかというとそうはいかない。美しい酸味のときに限る。美しいと感じるうまい酸味を醸しだしたお酒が現にあるということである。
「悦凱陣」(よろこびがいじん) の酸味、そして「村祐」(むらゆう)
の酸味のうまさに心引かれる庵主であるが、この「弥久」もその嗜好にぴったりのお酒だった。
「悦凱陣」の酸味が一徹な酸味で、「村祐」の酸味がてらいのない酸味だとしたら、この「弥久」の酸味はというと色っぽいのである。庵主の舌はそのくすぐったさにとろけてしまった。
7月の最後の夜に呑んだ一杯である。野球で言えば、最終回に出た逆転サヨナラ満塁ホームランに快哉を叫びたくなるような気分のお酒だった。
そのお店の大将とは街中で顔見知りのため、ありがたくも定量よりもおまけをしてくれたのである。
うれしかったものの困っちゃった。そんなに呑めないからである。
しかし、酸味のうまさがあるお酒はもう十分だと思っていても呑めるのである。
それが普通酒なら、もう呑めないと思ったときにはそれ以上呑むのは苦痛でしかないが、酸味がしっかりしているお酒はそれでも呑むことができるということである。
アルコール度数が19〜20度の酒だった。どうりでうまいと感じたものである。しかし、呑んでいるときにはそんな高い度数であるとは感じさせないうまさが口の中にひろがっていたのである。
庵主にとって、日本酒のうまさは17度から始まる。従来の標準とされていた15度前後のお酒では呑んでいてなんとなく頼りなく感じるのである。心配しながら呑む酒がうまいわけがない。
ビールが5度前後、それに5度たしてワインが12度、それに5度くわえて日本酒が17度、さらに25度なら焼酎に切り換えた方がうまいと感じる。
酒には、それが一番うまいと感じるアルコール度数があるということである。
この夜のお酒はうまかった。うまいお酒が向こうから飛び込んでくるのだからありがたいことである。
お店は、曙橋の《ぼうのぼうの》である。お酒の目利きの大将がいるお店である。



|