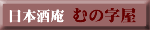
いま「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成19年7月前半の日々一献
★期待と落胆★19/7/18のお酒
北海道旭山動物園のラベルが貼ってある「男山」のカップ酒には特別純米酒が入っている。
いまや知らない人でも知っているあの旭山動物園を看板にしている北海道のお酒だから、中のお酒がいいかげんなものであるわけがないと思うのである。そうでないと看板の名折れになるからである。
しかも、180MLで300円とあるから、概算すると一升で3000円のお酒なのである。一升で3000円の酒となると錚々たるお酒を買うことができる値段帯である。味に不足はないだろうと思うのである。
で、冗談で買ってみたのである。
冗談という意味は、いわゆるカップ酒というのはその容器の密閉度がよくないのか、味が落ちるというのが庵主の実感だからである。
味わって呑む酒ではないという先入観があるから、それを呑むのはあくまでも好奇心からである。だから、庵主にとってカップ酒を呑むことは冗談の域を出ないということである。
「ワンカップ大関」の大吟醸酒を、素面で呑もうという人がいるだろうか。庵主はそれを素面で呑んだことがあるのである。
カップ酒はなぜかうまく感じないというのは、あの少し厚めのガラス容器に直接口を付けて呑む時のお酒の感触がせっかくの味わいを損なっているのかもしれない。
お酒はそれを呑む酒器が変わると味わいまで違って感じるものだからである。
多分、一番まずいお酒の呑み方は、紙コップで呑むことだろう。その次はペラペラのプラスチックカップで呑むそれに違いない。
前者は紙のニオイを感じるのと、手にしたときにいかにも使い捨てといった感じの貧相感よるものであり、後者は手に持ったときのたよりない軽さとカップの柔らかさの不安定感による。
それに次ぐのがカップ酒の分厚いガラスカップで呑むそれだろう。
ビール瓶に直接口をつけてビールを飲むような品のなさを感じるからなのだろうか。
即席ラーメンでいえば、器に移さずに鍋から直接それを口にしているようなものである。それはそれなりにうまい食い方なのだが、カップ酒でそれをやると、お酒がかわいそうな気がするのである。
カップ酒のの中に入っている酒は大したものではないから、それでいいのだという考え方もあるだろうが、1合で300円のカップ酒となると、ちょっと期待をしてしまうのである。
で、本当に買ってきて呑んでみる。
木綿屋男山本家の「男山」である。北海道旭川市のお酒である。
特別純米の「特別」は精米歩合を指しているのだろう。精米歩合は60%とある。
米は何を使っているのかわからない。
あとからよく見たら、アルコール分は15度とあるから、庵主にはちょっとものたりないと感じる度数である。
庵主の好みからいうと、アルコール度数が15度というのはちょっと低すぎるのである。水っぽく感じるからである。
逆に、度数が17度を越えると、その度数だけでうまいと感じることがある。アルコール度数が高いお酒がうまいと感じるのは、量を呑まないので、最初からインパクトのある酒でないと呑んだ気がしないせいかもしれない。
もっとも17度あればお酒はうまいかというとそうはいかない。最初、その度数でうまいと感じても、やっぱりうまくないお酒はそれなりの味わいでしかないことがすぐにわかるからである。
カップ酒の「男山」特別純米酒であるが、やっぱり庵主には水っぽく感じるお酒だった。
はっきりいって呑むまでもないお酒だった。
悪い酒ではない。そのかわりうまくもなんともない酒だった。
よく言えば、癖のないすっきりした出来映え(味わい、ではない)の酒である。
庵主にとってはインパクトがないお酒だった。いらない主張のない、しっかりした造りのお酒がいいのだ、という人にはぴったりのお酒だろう。
なんといっても、悪くはないのだから。
しかし、庵主がこういうお酒を呑んだときに感じることは、呑んだ甲斐のないお酒だった、という思いである。
呑む前の期待が大きかっただけに、落胆も大きかったというわけである。
庵主の経験則はここでも実証されたのである。
お酒の多くはうまくもなんともない酒である、ということである。
しかし、そういうお酒に価値がないのかというと、そういうことはない。そのようなお酒があるからこそ、本当にうまいお酒の有り難みとうまいお酒に出会えた喜びが心の底からわいてくるのである。

★シードルの誘惑★19/7/11のお酒
英語のciderをサイダーと読むと三ツ矢サイダーのような甘い炭酸飲料を思い浮かべるが、それをシードルと読むとリンゴ酒のことでこちらはアルコール飲料となる。
元の単語は同じなのに、その日本語読みが違うと意味するところが異なる言葉でおもしろのいはカードとカルテである。
カルテも元の単語はカードcardなのだというが、カルテからはなかなかcardが思い浮かばない。
伊丹十三が書いた本の中に、日本語のプレハブの元の英単語をやっとたどりついたという話がある。
伊丹十三は最後は映画監督として亡くなったが、もとは俳優で、英語も話せたからアメリカ映画にも出演しているはずである(←面倒くさいので調べていない)。
英語に堪能な伊丹十三にも、「プレハブ」という読み方からは元の英語が想像もつかなかったのだという。
外来語を日本語で使うときには日本人の感覚に合わせた発音になるということである。
何年か前に、韓国人牧師だったか神父が、日本国内で自分の名前を日本語読みされるのは気に食わないので、ちゃんと韓国語で読んでほしいと訴えたことがあった。
韓国人、裴勇俊を日本語読みでハイ・ユウシュンと読んでいたら、それをペ・ヨンジュンと読んでほしいというわけである。
漢字名前の外国人はそれを日本語の読み方で読むのは当たり前のことなのだが、それが気に食わないというのである。
ここは日本だという感覚がない僧職者だったようである。
アメリカに行って、日本のことをジャパンというな、ちゃんとニホンといってほしいと要求しても相手にしてくれる人はいないだろう。
韓国人が嫌われるのはそういう主張を平気で外国人に突きつけるからである。
名前の読み方が違うと自分の心が痛むとまでいわれたら、日本人としては気を使ってわざわざ読みにくい名前を使うという心遣いをしなければならなくなるのである。 庵主などは、はっきりそういう相手を「馬鹿か」と思ってしまうが、それでもつい日本人なので相手の気持ちに合わせてしまうのである。
当人は日本人は自分の気持ちを受け入れてくれたと思っているかもしれないが、日本人としては迷惑な隣人だと心の中では思っているから、できればお近づきになりたくないという気持ちになってくるのはいたしかたがない。
中国人は、他国の総理大臣に靖国神社に参拝するなと余計なお世話を言ってくるが、その名前をマオ・ツートン(毛沢東)とかフー・チンタオ(胡錦涛)と読まないと中国人民は心が痛むとは言ってこないのは少しは大人だからなのだろう。
日本はそういう隣人と隣り合わせているから、本当は関わり合いにならないほうが幸せなのであるが、そうはいかないのがご近所つきあいということなのである。
サイダーは英語であるが、シードル(cidre)というのはフランス語である。いずれもリンゴ酒という意味である。
では英語でいわゆるサイダーのことはなんというのかというと、ソーダ (soda) というのだと、ウィキペディアに書いてあった。
お菓子にシュークリームというのがある。
シューは靴でそのクリームだから、靴磨きのクリームかというとお菓子なのである。では英語で靴磨き用のクリームはなんというのか、というクイズがあった。
そう聞かれるとすぐにはわからないものである。
シューポリッシュだという。
そのシードルだが、庵主がそれをなんとなくうまそうに感じるのはリンゴから造った酒だということ、サイダーという甘美な味わいを思い浮かべること、そしてそれを国内で商品化しているのがニッカウヰイスキーだということ、といったおいしそうな想像力をそそられるからである。
そのニッカのシードルが今販売しているのが、「季節限定」で「リンゴ100%のスパークリングワイン」の「シードル・サマースパークリング」である。
「糖分・香料・着色料を一切加えない、リンゴ100%の夏限定シードルです。」と小さな文字で書かれている売り文句がなんとも魅力的なのである。
本物だ、という安心からからつい飲んでみたくなるのである。
本物だからきっとおいしいにちがいないと勝手に想像してしまうからである。
そう思い込んだら、すでに自己暗示にかかっているようなものだから、うまいのである。
酒を飲むときは自己暗示で飲むとうまく感じるのなら、そういう自己暗示を掛けて呑めばどんな酒もうまくなるというわれである。
これは貧乏人には有益な術であるが、しかし、庵主に関しては、お酒についてはその暗示は効かない。体がうまいお酒を知ってしまったものだから、頭の中でうまいと信じて呑んでも、からだがウンと言わないからである。
知っていることが必ずしも幸せとはかぎらないということである。
どんな人でも、自分が死ぬ日を知っていたら、毎日安心して生きていけないように、余計なことは知らない方がいいこともあるということである。
ニッカの今度の季節限定シードルはそのパッケージが美しい。
気持ちいいぐらいに美しい。さわやかな色遣いなのである。
アルミのキャップと200ML入り瓶の上半分に巻かれているラベル部分は同じ黄緑色で、その色感がアルミも紙も同じなのである。インクの調子が同じなので、キャップとラベルが一体となっているように感じる。
ラベルの部分には真っ赤なリンゴが描かれているから、緑の中に赤ということで補色関係にあるので、リンゴが最初に目に飛び込んでくるのである。
瓶の下半分は透明ガラスで中のシードルの色が見えるから、それがいかにもうまそうな色で庵主の気持ちを誘惑するのである。
つい手にしたくなるパッケージなのである。
パッケージデザインぱかりを褒めているのは、中身が大したことがないからなのかと邪推されては困る。
中身もうまいのである。
というより容量がたった200MLである。うまいのか、そうでないのか、わからないうちになくなってしまったのである。

★サントリーのビールがうまい★19/7/4のお酒
サントリーが造る酒というのは、料理屋でいえば創作料理みたいなもので、まともな味を知っている人は相手にしない、おっと、避けて通ると言いなおしておくが、そういうウィットに富んだものが多いので、下手物好きの庵主は実はひそかなファンなのだが、しかし、結局はまともに造った酒のほうがうまいので一度飲んだらそれきりになってしまうものが多いというのがこれまでであったが、ここにきてサントリーの実力を感じさせるビールが続いて発売されたことから庵主はついそのうまさを書いておきたくなったのである。
まずは、限定醸造と名付けられているが、いまのところ市場在庫が十分にあるように思えるモルトセレクションシリーズの最新作「英国産ロースト麦芽使用」である。
この限定醸造は、期間限定ではなくて、販路限定という意味なのかもしれないが。
ローストモルトを使っているのだから、いわゆる黒ビールの範疇にはいるビールであるが、色はそれほど黒くなくて、ふつうのビールの色を少し濃いめにした感じの色合いのビールである。女の子でいうならば地肌の白を感じさせる褐色の肌といったところである。
そのへんはサントリーの広告文案がうまい。このうまいは上手という意味である。
「英国産麦芽のきめ細かい口当たりに、英国産ロースト麦芽の香ばしさが加わった上品な味わいのアンバー(琥珀色)タイプビールです。大切な時間にゆったりどうぞ。」とある。
そうそう、このビールの色はコハク色というのだったということを今思い出した。
このピールがうまいのである。このうまいはもちろん味わいがいいというほめ言葉である、ねんのため。
なにがいいのかといって、ビールの味がするのがいい。
ビールを飲んでいるのにビールの味がすると感心しているのもなんであるが、今日のビールというのは、正しくはビール類と呼ばれる一群を指していることから、そこには本物ビールから代用ビールまで含まれているために、はなしがややこしくなっているのである。
だからビール類のなかでこの本物のビールは砂漠に湧き出る泉のような状態になってしまっているから、庵主はそのうまさの泉に頭から飛び込んでしまったのである。
最近のビール類の市場は、第3のビールに加えて、第4のビールなどとからかわれているビールみたいな感じがするリキュールまでが登場して、それはそれで飲めないことはないのだが、ビール本来のうまさからだんだん遠のいている不思議な味覚の世界が広がってきたために、ピールの味がするまともなビールが飲みたいと思っていたときにサントリーのビール部門が真っ当なビールを造ってくれたのである。
いまどきのビール類を女性にたとえていえば、本来の美しさである女性の美を追求するのではなく、ニューハーフみたいな人工のイメージを追いかけているようなもので、庵主はやっぱり本物の女性の美しさの方が好きだから、奇妙に美しい代用ビールの味わいには一瞬心を引かれるものの、それは本物の女性の美しさにはかなわないということを思い知らされることになるだけなのである。
酒のうまさは理屈ではない。体がうまいと納得するとまた飲みたくなるのである。
「英国産ロースト麦芽使用」にはそのうまさがある。まだ飲んだことがない人はぜひそれを飲んでみてほしい。セブンイレプンで売っているからすぐ手にはいることだろう。
サントリーらしいところは、「英国産ロースト麦芽使用」と大きく書かれた下にちいさな文字で(全麦芽の10%以上)という庵主にはよくわからない表示がちゃんと書かれているところである。
飲み手を素直に酔わせてくれないところが、サントリーらしいニクイところである。
英国産ローストモルトと謳っていながら、小さい文字でそれは1割ぐらいしか使っていないというのである。
日本酒で、「米だけで造ったお酒」とあって、その下に小さな文字で「国産米10%以上使用」とあったら、まず感じることはそのお酒のうさんくささであろう。
この酒は大丈夫なのか。残りの90%の米は実は屑米を使っているのではないかと邪推したくなること必定である。
そういういかがわしい表示をいささかのはじらいもなく書き記すところがサントリーのおもしろいところなのである。
原料がなんであろうと、飲んだときにうまければそれでいいと庵主は思っているからそれは話のネタにはするが全然気にしてはいないのであるが。
このビールは間違いなくうまいのである。
原料を見ると「麦芽・ホップ」だけの本物のビールである。
本物だからうまいと限らないのが酒の世界であるが、これは飲めるビールである。
ちなみに庵主が苦手な味のビールはキリンの「淡麗」。これは飲めない。まずいとはいわない。ただ、庵主のからだはそれをうまいと認識しないということである。
酒造りは、従来の造り方をきちんと踏襲しても、味わいが古い感じになったりすることがあるから伝統的な製法が必ずしもうまいものになることを保証するものではないののである。
その味わいの中に当世風の味わいがなければ古くさい味だと感じてしまうのは、人間の見掛けの文化が時代とともに洗練されていくように、味覚もまた同じように洗練されているからなのだろう。
嗜好が時代とともに変化しているといったほうがいいのか。
今度のモルトセレクション「英国産ロースト麦芽使用」は庵主おすすめのビールである。ようするにうまいからである。
それがまっとうなビール造りに由来するものだから、まっとうな酒を庵主は支持するのである。
サントリーのプレミアムモルツが3年連続でモンドセレクションの金賞を受賞したということでサントリーは大々的にそれを前面に打ち出して広告を展開しているが、庵主にはそのモンドセレクションの価値がわからないので、ぜんぜん有り難みを感じないものの、その勢いをかって造られたのだろうか、プレミアムモルツの黒ビールが出たのである。それがまたうまいのである。
こちらの方は完全な黒ビールである。
庵主の味覚は、かつて、庵主の回りにいる大方の人がうまいとはいわなかったサントリーの普通のビールの生ビールに共感を覚えていたから、潜在意識の中ではサントリービールの味わいと波長が合っているものか。
一時、サントリーがライセンス製造していた「バドワイザー」の生ビールも庵主は口に合ったから、庵主のビールの好みは国産大手5社の中ではサントリーが一番近いのかもしれない。
こんどの黒ビールは最初の一口が甘いのである。その甘さが庵主の心をつかむ。
麦芽由来の甘さである。お酒も米由来の甘さが感じられないものはうまいと感じないが、ビールもただのアルコールになってしまってはおもしろくもなんともないのである。
ベタ塗りの白粉(おしろい)で作られた女性の顔を見ても、きれいだとは思うが好もしいとは感じないのと同じである。すぐあきるということである。
やはり地の美しさが感じられないと、お酒を呑んでいてもつまらないのである。
サントリーのプレミアムモルツの黒ビールには地の美しさを感じさせる味わいがある。
そして、甘いとはいってももちろん砂糖やいまどき多くの甘味飲料で多用されている果糖ブドウ糖液糖みたいなただ甘いだけの表情がない甘さではなく、絶妙な味わいを楽しませてくれる甘さなのである。その甘さを感じるのも束の間、きれいな味わいのビールのボディがそれを泡沫(うたかか)の夢のようにかき消してくれる。
そして、甘い夢の記憶だけが残るのである。
だから、また甘い夢にひたりたくなって、グラスに口を寄せることになるのである。
ロマンあふれるビールなのである。
ちなみに缶に書かれている広告文案は「ほのかな甘みと豊かな味わい、心地よい上品な香りをお楽しみください。」である。
こういうビールを飲むと、さらにうまいビールを飲みたくなる。もちろんこの場合は口直しにではなく、こんどは別のスタイルのビールのうまさを求めてである。
サントリーのビールは、今、うまいのである。
「日刊ゲンダイ」が、実力はあるのにすぐ故障したりしてなかなかファンの期待に応える活躍をしない清原の低迷をなじって「もうやめろ清原」と見出しを打ったその日の試合で巨人を勝利に導く大活躍をした途端、それまでの清原バッシング見出しが一転したという。
「やればできるじゃないか、清原」。それでこそ男、清原だというわけである。
人工美の極致みたいな「ジョッキ生」とか、缶のデザインの青の色遣いだけは庵主も気に入っているのだが発泡酒にスピリッツを混ぜたリキュール「金麦」(きんむぎ)とかのビールみたいな不思議なアルコール飲料を横目に睨みながら、庵主はふと日刊ゲンダイの見出しを思い出したのである。
「やればできるじゃないか、サントリー」。
「英国産ロースト麦芽使用」と「ザ・プレミアム モルツ〈黒〉ビール」のうまさにすっかり酔ってしまったのである。



|