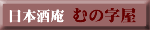
いま「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成19年4月前半の日々一献
★サントリーが凄い会社であることの補足★19/4/11のお酒
「むの字屋」には週1回は更新することをモットーとしているホームページとは別に毎日更新しているブログがある。
本日のプログは「サントリーは凄い」である。
庵主はこれまでサントリーの酒をことごとく馬鹿にしてきた。ただし「響」の17年だけは例外でそれだけは飲めるが。
それらの酒はどれも庵主の常識をはみ出していて冗談の域を越えていると思われたからである。
水で割らなければ飲めないウイスキーやブランデーとか、麦芽の使用量を故意に減りして造ったビールだとか、子供が呑むようなカクテルみたいな飲料とか、よくそんな紛い物の酒を臆面もなく売っていられるものだという不信感がぬぐえなかったからである。
この会社はやっていることが信用できないという庵主の心象からである。
サントリーが三流メーカーなら笑って見ていられることであるが、しかし、サントリーは日本を代表する大会社なのである。
イメージは一流なのである。
そういう会社がなぜ三流の発想による酒を造って売っているのか、日本の恥ではないかという不愉快な気持ちがつきまとっていたからである。
酒造りの考え方が狂っているのである。
それが庵主の不愉快の原因だった。
サントリーは、洋酒の壽屋が古い社名である。
壽屋のスタートは「赤玉ポートワイン」という甘ったらいワイン風アルコール飲料だったという。
甘ったらいというは悪口ではない。当時の日本人の口にはそうでないと合わなかったらからである。
ポートワインという呼称は後年、商標権の侵害だということでスイートワインとかに名前を変えることになったはずである。
シャンパンでもないのに、ナントカシャンパンと名付けて売っていたわけである。
当初はその程度の知識で酒を売っていた会社だった。
ようするに下手物の酒だったのである。
その発想が一流のイメージを広告力で造り上げた今日でもその社風を引きずっているというわけである。
サントリー文化人という言葉がある。
往時その宣伝部にいた才人、開高健、山口瞳、柳原良平といったイメージの人たちのことである。
サントリーはその人当たりのいい文化的なイメージで酒を売っていたのである。
とはいえ、飲み手もサントリーの酒が飲めることが楽しかったということは間違いない。
中身ではなくそのイメージを売っていたからである。
しかし、その商品である酒の品質は社風をしっかり守っている酒だったからたまらない。
名前はウイスキーではあるが中身はとんでもなアルコール飲料を飲まされていたのである。
正統派の飲み手はその非をあげつらうことになるのである。
そのウイスキーの実態を知った飲み手の怒りは、往年何冊か刊行されたサントリーの酒造りを批判した本にいっぱい書かれている。
庵主がそれらの本に影響されたことはいうまでもない。
庵主はそのころはウイスキーなど飲んでいなかったので、それらの本の著者の怒りの感情に火をつけた当時のサントリーのウイスキーの味わいがどんなものであったかわからないが、その中身はよほどひどい酒だったのだろうと思われる。
酒なんか、とりわけ蒸留酒などは上手に模造すればうまいかまずいかはそんなに気にならないものである。
庵主は芋焼酎に関しては、どの銘柄を呑んでもみんな同じように感じるから醸造酒と違って蒸留酒は模造しやすい酒なのではないか。
醸造アルコールに芋焼酎のフレーバー(食品用香料)を加えたものを呑んでも、庵主は多分気がつかないだろうと思う。
フレーバーに強い西酒造(「富乃宝山」の蔵元)が試しにそれを造ったら、下手な本物の芋焼酎よりもうまいかもしれない。
それとは反対に、醸造酒である日本酒はそうはいかない。今でも売られている合成清酒は飲めたものではないし、飲めないということではなく、味わいがつまらなすぎるという意味であるが、合成清酒でない本物の日本酒でも下手な造りの日本酒もやっぱりうまくないのである。
その味わいの違いが、理屈以前に、庵主の体が好き嫌いを露にするからである。だめなものは庵主には呑めないのである。
その点、蒸留酒というのは高いアルコール分からして異常な飲物なのである。その香りの好みが呑めるかどうかを左右するものだから、万人向けの香りを付けておけば酒の善し悪し以前になんとかなるものなので、サントリーがそれをジャパニーズウイスキーだといって売りまくったことはそれなりに飲めるものだったら問題はなかったのである。
じっさいにそれを飲んだら満足感を得られたようだから問題はなかったのである。それがサントリーでなかったのなら。
批判書の著者も、サントリーのウイスキの香りが自分の好みに合わないのなら自分好みの舶来ウイスキーを探して飲めばよかったのである。
度数の高い蒸留酒は、飲めばすぐ酔っぱらってしまう代物だから味のよしあしで呑んでいるのは最初の1〜2杯ぐらいなので(おっとこれは庵主の場合)、能書きをいってまで飲む酒じゃないので、批判書の著者は、サントリーのウイスキーを飲んでも酔えなかったものか、アルコール耐性が強すぎて、いくら飲んでもうまく感じないのでこれはおかしいと気付いたものか。
本当のところは、そのジャパニーズウィスキーの中身がとんでもない代物だとあとから知ったことで怒りに火がついたということなのだろう。
本当の両親だと信じて疑わなかった子供が、実は貰い子だったと知らされたときのショックがそれまで騙し続けてきた両親に対する反感に変わってしまったのである。
つまりサントリーの広告に騙されていたという不愉快な気持ちから発した怒りだから語気が険しいのである。
それが模造酒だとわかっていて飲んでいる分にはそれがひどい酒であっても全然気にならないが、しかし、いい酒だと思わされて飲んでいた酒がとんでもない酒だったとあとから知ったらそのショックは小さくないということである。
サントリーはそれをやってしまったのである。
だから飲み手の顰蹙をかってしまったのである。
庵主は、サントリーは真っ当な酒が造れない会社だと思っていた。模造酒を大量生産してそれを宣伝力で売りまくっているメーカーだと思っていたが、実はそうではないのではないかと思うようになったということなのである。
まともな日本酒と三増酒を比べてもしょうがないということに気付いてから、それらの酒は上下関係ではなく、横並びの世界の違う酒なのだから、それぞれの味わいは別の楽しみなのではないかという発想の転換を行なったからである。
だめな酒をいくら貶してもうまくはならない。
それをどうやってうまく呑むかを考えた方が楽しいということなのである。
貶して得られるものはないが、新しい呑み方を考えることは面白いからである。
サントリーはうまい酒を造るメーカーではなく、面白い酒を創るメーカーなのである。
新しい酒を考え出す柔軟な発想ができる酒メーカーなのである。
それをイメージ豊かな宣伝力で売りまくる馬力のある会社だということである。
サントリーは酒の概念を変えるメーカーである。
酒は人類の長いつきあいである。
アルコールは毒ではあるが、人間はそれを長きわたってうまく呑みこなしてきた。
それが文化だった。
酒は人間の基本食品になっているのである。自由に使える蓄積された知識を文化という。酒は文化なのである。
食品の定義はなにか。体にやさしいものである。
アルコールという毒にやさしさを求めるというのも矛盾しているのではあるが、いい日本酒はホントに体にやさしいのである。体がうっとりするのである。
そうでない日本酒は呑むとガッカリして急に酔いがまわってくることはよく知られていることである。
それには本物という前提が呑み手の心に安心感を与えてくれるからである。
それが紛い物だということになったら、人間の気持ちは揺れるのである。その気持ちの違いが本物と紛い物の違いである。
紛い物だって、それは紛い物としてはまぎれもなく本物の紛い物なのである。
サントリーは伝統的な酒の定義にこだわらない大胆な発想をする革新的酒メーカーだということである。
モルトウイスキーをそんなに使わなくてもウイスキーを造れるという発想は、後年、麦芽の量を減らしてもビールみたいな酒は造れるという発想に至るのである。
そのうち、醸造アルコールにウイスキーフレーバーをつけた新しい概念のウイスキーなどを飲ませてくれるのではないか。
そういうのが出たら庵主は真っ先に買ってしまうのである。
下手物も好きだからである。
そういう酒造りをサントリー文化と呼ぶのだそうだ。真っ当とは対極的なところにある新しい文化なのである。
もっともそんなことまでして日本人にアルコールを飲ませなければならないのかという問題には目をつぶっての話ではあるが。
他人の着ている物と買った物を貶さないということとその天職を貶さないというのは庵主のモットーだからである。
サントリーの酒創りの面白さを見間違ってはいけないというのが本日のブログの本意である。
サントリーの意表をついた酒創りついてはまた具体的にその面白さを紹介したいと思う。

★日本酒の多様性★19/4/4のお酒
日本酒と呼ばれる酒には多種多様な造り方をしたものがある。
主原料である米の違い、精米歩合の違い、酵母の違い、醸造設計の違いなどいくつもの要素が絡み合って、それこそめくるめくような数多くのお酒が造られている。
その前に、日本酒という呼び方は日本で造られている日本固有の酒の総称なのだという。つまり醸造酒である清酒と蒸留酒である焼酎、泡盛、黒糖焼酎などを含めた言い方だというわけである。
だから、いわゆるお酒のことは清酒と呼ぶのが正しいということになる。
この「むの字屋」では、お酒とか日本酒という場合は日本語の常識に従ってその清酒のことをいう。焼酎は含まない。
なぜなら、庵主には焼酎のうまさがわからないから語りようがないからである。
ところで、日本酒を日本で造られている日本固有の酒の総称というと、では海外で造られているそれは日本酒ではないということになってしまうから、ここでは、いちおう日本伝統の酒造法で造られている酒としておこう。
最初の定義だと、日本国内にある日本酒メーカーでありながら、見た目は日本酒みたいなのに日本酒とは呼べない酒を造っていることになるところがいくつも出てくるため、そういう酒が日本酒ではないことになってしまうのでは紛らわしいからである。
この書き方も紛らわしいから、わかりやすく書き直しておこう。
清酒の醸造に使われている醸造アルコールの原料が海外からの輸入品であることが多く、それらは日本に固有の原料ではないということである。
醸造アルコールを使った清酒なるものは、舶来の醸造アルコールを混ぜたカクテルだということである。日本固有の酒とは呼べない代物なのである。
水っぽい酒(清酒)という言い方がある。それならまだお酒と呼んでも問題がないが、アルコールっぽい酒(清酒)というのはどちらかというと、清酒というよりは焼酎に近いのではないか。
それは連続式蒸留焼酎(少し前までは甲類焼酎と呼ばれていた)と清酒の混和酒である。
普通酒の中には前者の方が後者の量よりずっと多いというものがあるが、そういうカクテルは考えようによっては日本酒風焼酎と呼んでも間違いではないのである。
そこまでアルコールのうまさにこだわるなら、最初からうまい焼酎を飲んだ方がいいのではないかというのは、庵主のイヤミである。
醸造アルコールを混ぜて造る清酒もまた日本の伝統的酒造法になってしまったから庵主はそれがうまければべつに差し支えないので気にはしていないが、一方ではこのゆたかな時代に今でも合成清酒というのが造られているのだから、それは酒の善し悪しというよりも、多様性なのだと捉えたほうがいいみたいである。
たしかに、品質がいいものも嬉しいが、そうでない実用的な商品もまた需要があるということである。
庵主はそのうちのごく一部、うまいお酒だけを好んでいるというわけである。お酒の好みが偏っているということである。
酒を呑む場ではなく、ただそのお酒のうまさだけを語っているのである。
へんなお酒の呑み方をしているということなのである。
お酒の酔いを楽しんでいるのではなく、お酒造りに込められた造り手の、すなわち日本人の酒造りの美しさを感じることが好きなのである。
それは日本刀を鑑賞するのに似ている。
刀が好きな人は、なにもそれで人を殺そうという気持ちは持っていないはずである。ただ、その刀剣の美しさ、すなわち、刀鍛冶の気合の美しさに惚れ惚れしているのである。うっとりしているのである。
うっとりするという点ではうまいお酒もまた同様である。
酒の多様性もまた日本人の酒造りに対する意欲の現れなのだが、しかし、本物と偽物とにわけるなら、本物のお酒の方がやっぱりうまいという感想に落ち着くということである。
うまいお酒だけでさえ、個人では呑みきれないほどの種類があるのに、庵主にはとてもじゃないがそうでないお酒まで呑んでいる余裕がないのである。
なかにはカップ酒にはまってそれを追いかけている人がいるが、それもまたお酒の楽しみなのである。
いろいろなお酒の楽しみがあるということである。

★花見の酒★19/4/1のお酒
今年は4月1日が日曜日で、東京では桜の花がそれに合わせたかのように満開になった。
庵主の花見はいつもながら千鳥ヶ淵の桜並木の縁道である。
「桜の花のトンネルみたいだね」と親に連れられてきた女の子がいっていた堀沿いの道を数多くの人たちと一緒に花を見て遊歩する。
見事な桜のトンネルが続くその縁道にはいるまでがすごい人出なのである。
地下鉄の九段下駅2番出口から出てそこから縁道の入口の方に列をなして向かうというのが順路である。
市ヶ谷から行く場合は、通行規制が行なわれているため、いったん縁道の入り口を通り過ぎて、九段下駅の出口まで行ってから戻ってその列の最後尾に付かないと縁道にははいれないようになっている。
歩道は縁道に向かう大勢の人でうまっていて通れないから、市ヶ谷の方から来た人は靖国通りの車道を通って列の後ろに加わらなければならない。
車道の一車線を開放して歩道とされた所を歩いていると、なんとなくデモ行進で車道の端を歩いているような気分になる。
もちろん交通警官が誘導してくれるので車道を歩いても安全は確保されている。
九段下駅の出口からは次から次に花見の客が押し出されて来る。
その出口を出た途端、もうそこは満開の桜である。
ひらひらと舞い落ちてくる桜の花びらが日常とは異なる別世界に誘う。
桜の花に狂って集まってきた人たちの群である。
庵主は桜に狂えるようになるまでに数十年を要した。
それまでは花見を馬鹿にしていたのである。そんなものを見て何がおもしろいのだろうかと。桜の木の下で酒を呑んでどこか楽しいのかと。
日本の映画で、余命短い人のセリフに「来年の桜は見ることができるのだろうか」というのがあるが、そういう歳とか境遇にならないと桜の美しさがわからないのではないかとも思う。
もっとも若い人でも花見が好きだという人がいるから、そうでもないのだろうが、庵主はここへきてやっと桜の花を見ることが面白くなってきたのである。
もっとも今でも分からないのは、紅葉を見るということである。これは理解できない。あんなもの見てどこがおもしろいのか。
桜は人の気持ちを狂わすが、紅葉を見ると生きていることの虚しさを、すなわち、朽ちていくことの儚(はかな)さを感じるからどうにもつまらないというところなのかもしれない。
九段下の出口を出た人は、江戸城内に向かう群と庵主のように千鳥ヶ淵縁道に向かう群に分かれる。
江戸城の入口である田安門への道もまた桜と人でいっぱいである。
縁道に向かう行列の最後尾について並ぶことややしばらくしてやっと縁道の入り口まで進んだ。
あとはただ桜の花びらが舞い落ちてくる桜のトンネルの中を人の流れに合わせて進むだけである。
入り口までの歩道に並んでいたときは列が進まないことにイライラしていたのに、桜の花でおおわれた縁道にはいると心が落ち着くのは日本人の伝統的心情のせいなのか。
もっとも外国人もその中に混じって喜々としていたから、そうでもないようである。
千鳥ヶ淵縁道は、見上げると上は桜、堀の方を見ると目の前も桜、そして堀の向かい側も桜、さらに堀には桜の花びらが浮かび、ボートがそれをかき分けているのが見える。
舞い落ちてきた桜の花びらを頭に載せて歩いている人もいる。
隣の女の子は、掌いっぱいに桜の花びらを握りしめて、息を吹き掛けて舞い上がらせている。
一陣の風が吹くと、桜の花びらが吹雪のように舞い散るってくる。
まさに桜に包まれて、なぜか心ははずむのである。
が、ここでは花見の酒がないのである。
花見の宴会は禁止されているからである。
で、その酒はどうするのかというと、縁道の入口にインド大使館があって、例年花見の時期に合わせて、館庭を開放してバザールを催しているから、そこでインドビールを飲むのが庵主の習わしとなっている。
銘柄は「キングフィシャー」である。
うまかというと、その酒別は発泡酒である、水代わりにしかならないビールだが、同時にカレーやナンなども食べられる店も出ているからそこでおなかをこしらえるときにはちょうどいい。
今年のバザール会場は館庭から、大使館の裏にあるアパートの前庭に移して行なわれていた。
東京にこんなにインド人がいたのかと思われるほど多くのインド人を見ることができる。
インドにほれこんでいる日本人もいることがわかる。
世の中は広いのである。
そのバザールで最後に庵主が大好きなホワイトグァバジュースを飲んでから、花見の列に加わったというわけである。
靖国通りを挟んで向かい側は靖国神社である。
その境内なら花を見ながらお酒も呑めたのだろうが、まだ昼間だったから、水代わりのビールにとどめたのである。



|