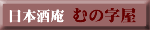
いま「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成19年2月の日々一献
★「獺祭」というお酒★19/2/28のお酒
「獺祭」というお酒がある。
知っている人には読めるが、初めての人は読めない酒銘の一つである。
「だっさい」と読む。が、しかし、読めても、今度は書けないのである。庵主もワープロでなければ、ソラでは書けない。
字が書けたとしても、その酒銘の意味を聞かれたら答えられない。
庵主は、それはダサイ酒だから「だっさい」なのだと思っている。
「獺祭」といえば「磨き二割三分」である。なんと、米を23%まで磨いたお酒である。
庵主に言わせればそれは罰当たりなお酒である。
米を77%も削って捨てて酒を造るなんてのは狂気だというわけである。
いつもの例え話であるが、原料の山田錦を100俵買ってきたら、そのうちの77俵を糠にして捨ててしまうのである。
そんな酒造りをまっとうな酒造りだと思えますか。
お米は一粒でも無駄にしてはいけなと躾けられた庵主は食い物を粗末にするにも程があると思うのである。
お碗によそったご飯を平気で食べ残す人を見る時のそれである。
だから庵主はその酒の名を心の中ではためらわず「ダサイ」と読んでいる。
そういう意味でダサイ酒なのである。
酔狂という言葉がある。
酔うと人は狂うのである。
お酒は人を酔わせる飲物なのである。
その「純米大吟醸磨き二割三分」の新酒ができたと聞くと、つい浮かれてしまうのである。
呑んではいけないその酒を、呑みにいらっしゃいと言われたら、抗(あらが)えないのである。
今年は2月18日が旧暦の元旦だった。
春が明けて四日目の2月21日に「2007獺祭新酒の会」が行なわれた。
その「純米大吟醸磨き二割三分」の新酒が東京にやってきたのである。
山口から持ってきた「磨き二割三分」のバリエーションがすごい。
同じ精米歩合23%のお酒といっても、酒槽(ふね)で搾ったものと遠心分離で搾ったものとがある。
その微妙な味わいの違いが、庵主にはよくわからないが、わかる人にはその新酒を口にすることは幸せの一瞬なのだろう。
美酒との出会いに恵まれた僥倖と、美酒の絶妙な味わいの妙がわかる自分がいるという矜持を一杯のお酒がくすぐってくれるのである。
さらに、遠心分離の二割三分には「元旦届け」と名付けられたおりがらみがある。
そして、これは酒槽搾りの二割三分で発泡にごり酒「聖夜限定」がある。
いうならば、狂気の四重奏が味わえるのである。
それを味わって狂わない人はいない。
磨き二割三分のほかにも会場には磨き三割九分、45%、48%、50%が並ぶ。
同じ精米歩合でも、本生、火入れ・にごり酒とバラエティーにとんでいるお酒は、それらを目の前にして自制できる呑み手はまずいないだろう。
庵主がそうだった。
いま、庵主は花粉症なのである。
時に咳き込み、時に鼻がつまり、時に目が痒くなる。喉が腫れて痛み何を食ってもうまくない日がある。
そんなコンディションでお酒を呑んでもおいしくないのである。
だからこの時期はお酒を呑まない季節なのである。
たまたま、この日は、花粉症の症状が穏やかな一日だった。
お酒がすいすい入る。
普段なら、五勺のグラスで二杯、締めて一合が適量なのに、この夜は体が「獺祭」を快く受け入れてしまうのである。
うまいのかというと、そんなことはない。
今日のお酒は、どれも造られて二、三か月以内の若い酒である。いまの庵主には新酒は評価の対象外の酒である。
お酒はじっくり熟成させた、酒齢1〜2年ぐらいのお酒がうまいと思うようになったからである。
たしかに新酒は楽しいが、それをうまいという勇気はない。良心がとがめるからである。
しかし、それはおいしいお酒なのである。
「うまい」と「おいしい」の使い分けはべつのところで書いたとおりである。
庵主が一番気に入ったのは精米歩合50%のにごり酒だった。
例によって甘い酒である。そして新酒のくせに、まろやかな舌当たりで新酒の固さを感じさせない心地よいお酒だった。
搾りたての鼻につくアルコールの辛さがなかったから庵主には呑みやすかった。
「獺祭」の新酒は、まだまだ、もう一つまだ、今呑むには若い酒であるが、そのほんのりの品のよさが快いのである。
「獺祭」の志向するところと、そうしてできあがったお酒は、そういう酒造りがいいか悪いかということは横に置いておいて、庵主のいう現代日本酒の好見本なのである。

★新しい酒の誕生★19/2/21のお酒
「ドラフトワン」という酒がある。
第三のビールと呼ばれている酒である。
庵主はその第三のビールを代用酒と呼んでいる。
できれば本物のビールを呑みたいけれど諸般の事情があってやむを得ず飲まなければならない酒という意味からである。
しかも、それは麦芽を使った酒ではないから、ビールの定義から外れるイミテーション(まがいもの)ビールなのである。
ビトンの鞄の贋物(がんぶつ)を造ったら偽造で罰せられる。
ビールの贋物(にせもの)を造るということは、それと似ている行為なのである。
だから、いくらメーカーがこれはうまいと広告で声高に叫んでいても、庵主はそれは格下と見るのである。
その酒造りの考え方がいかがわしいからである。
おっと筆が滑ってしまった。贋ビトンを造ることと疑似ビール造りとでは意味合いが異なるからである。
ビトンの鞄の偽造は商標権の侵害であってそれは金持ちの利権を擁護するものである。商標の問題だから、ビトンの贋物のなかには本物と同等品の鞄もありうるが、代用ビールは窮状救済なのだから明らかに劣悪商品造りなのである。やっていることの見掛けは似ているが中身の質が目指す方向が逆なのである。
ただし、そういう行為に対する評価は、庵主においては同じだということである。
金儲けのためとはいえ、なにも好き好んで偽物を造って売ることはないだろうというものである。そういうことを平気でやれる精神の軽薄さが似ているということである。
そんな酒を飲んで気持ちよく酔えるかというのが、能書きが大好きな庵主の心情なのである。それでも十分酔えるという人には代用ビールは福音である。
同じ予算でビールの2倍も楽しめるのだから。
お酒の量が呑めない庵主は、呑む時にはうまいお酒を呑みたいと思うのである。真っ当なお酒を呑みたいと思うのである。
選んでまでその手の酒を飲みたいと思わないのは、そういう庵主の個人的な事情からであって悪意はない。
どうせ呑むなら気持ちのいいお酒を呑みたいからである。
その「ドラフトワン」が変わったのである。
なにが変わったのかというと、アルミ缶に印刷してある星のマークが以前より大きくなったのである。
それだけか、と思って飲んでみてびっくりした。
ちがう、この味はビールの模造品の味ではない。
「ドラフトワン」がビールの味わいの呪縛から解放された瞬間を味わっているのである。
ビールの味わいに似たイミテーションを追いかけていたときの発泡酒や代用ビールの味はひどかった。
こんなまずいものを飲む人がいるのかと、庵主以外の日本人の味覚に不信感を抱いたほどである。
それが売れているというからである。
なんてことはない、だれもが今のテレビ番組はくだらないと知ってて見ているように、代用酒は所詮代用品だということをわかってて飲んでいるのである。
値段が安いからである。
背に腹を替えちゃったのである。いや背に腹は替えられない、でいいのか。
飽食に飽きて健康のために簡食(飽食の反対語のつもり。粗食と違って量を追わない食生活という意味で。体力的に量が食えない寡食とも違う)を選ぶ人が増えたということである。
シンボリック係数だか、インポチック係数だかという太さを表す係数が人気を博していることからもそのことがうかがわれる。
美食よりも粗食という日本人本来の食生活を目指したのがその代用酒なのである。
もっともそのキッカケは不況による収入減なのではあるが。
今度の「ドラフトワン」の味わいはビールの味わいから脱却した闊達な味わいである。
その酸味の表現が軽やかで心地よい。
ビールの苦みのうまさにこだわっていた時には表現できなかった酸のうまさの表情が気持ちいいのである。さっぱりした味をしている。
「ドラフトワン」はすでに代用酒でなく、新しい味の表現なのである。
新しい酒の誕生なのである。
庵主はお酒のうまさはその酸味のうまさにあると喝破した。
呑んでみてうまくないお酒を取り除いていって、残ったお酒の共通点がそれだったというわれである。
日本酒だけではなく、他の酒においても同様に酸味のうまさがないと呑んでいてもうまくと感じないということを知ったのである。
こんどの「ドラフトワン」はその酸味の新しい魅力を引き出したのである。
「ドラフトワン」に乾杯である。
酒を飲みたくないときにでも飲めるアルコール飲料である。
ノンアルコールビールのまずさに辟易していた庵主にとっては救世主のような酒が出現したということである。
ノンアルコールビールというのは、こんなまずいものを造る奴は許せないと思うような酒である。微アルコール飲料である。
「ドラフトワン」はすでに第三のビールではない。
この新しい酒の普通名詞をなんとするのか。
ビー(B)ルより酸味がうまいからエー(A)ルと呼びたいが、すでにエールというビールがあるからそれもできないのである。
エンドウ蛋白とホップが原料だというから、ハッピーホップとでも呼ぼうか。
ハッピーエンドのもじりである。

★今月の読書「闘う純米酒」★19/2/14のお酒
埼玉の「神亀」(しんかめ)は、数多い蔵元の中にあって、純米酒しか醸さない蔵元の先駆者として呑み手の間ではつとに有名な蔵である。
その「神亀」の物語を書いた本がでた。
「闘う純米酒 亀ひこ孫物語」(上野敏彦著 平凡社刊 1575円税込)である。
なにげなく本屋をのぞいていたら、その本が目に入ってきた。
どういうわけか、うまいお酒とか、そういう本は向こうの方から飛び込んでくるのである。
そういうのを酒徳といい、書徳というべきか。
その書徳のおすそ分けである。こういう場合はお福分けというのだったか。
庵主ははっきりいってお酒の味がわからない。
利き酒遊びをやると、純米酒とアル添酒の違いがわからないことがよくある。よくあるというのはウソである、ほとんどの場合区別がつかないからである。
世の中にはアル添のお酒がわかるという人がいる。庵主にはかなわない能力をもっている人がいるということである。
だから、負け惜しみで、利き酒なんかはプロがやることであって、まっとうな呑み手はそんな下種なお酒の呑み方を真似してはいけないといっている。
さすがに下種とはいわないが。そういう品がない呑み方をしたらお酒に失礼でしょうと言い換えているのである。
酒の味はわからないが、それがうまいかどうかは判断できるのである。
うまいかどうかを決めるのは庵主の勝手だから、これはなんら気後れするところがないのである。
そして、このお酒がうまいと喧伝するのは、そういう好みのお酒が増えればうれしいからというごく個人的な理由からである。
ぶらっと立ち寄った居酒屋に庵主好みのお酒があれば、呑めるお酒がなくて生ビールを飲んで、その生ビールさえないときは、仕方なく瓶ビールを飲んでお店を出るという虚しさを味わわなくてすむからである。
で、そのうまいまずいは、案外そのお酒がもっているイメージに左右されることが少なくないというである。
庵主はそのイメージのことをお酒にまつわる「ストーリー」と呼んでいる。
ストーリーが豊かなお酒は呑んだ時においしく感じるということである。呑んでいて楽しいということである。
ストーリーが貧弱なお酒は、呑んでいてもさびしいということである。
だから、お酒を売りたかったらストーリーを作れというのである。
まともにお酒を造っていたら、いくらでもストーリーはあるのである。ストーリーを作れるののである。うまいお酒を造るという意欲だけでもストーリーになるからである。
そしてその気持ちはかならず呑み手に伝わるからである。
現に庵主はそういううまいお酒しか呑んでいないし、そういうお酒でないと呑めないのである。
お酒の味は庵主には覚えられない。一年前に呑んだ同じ蔵のお酒の味を覚えていない。
庵主の場合は、その味わいをいったん言葉に移しかえてその言葉を記憶しているのである。
お酒のストーリーはその記憶を楽にしてくれるということである。
味わいを言葉に置き換えるときに、その言葉をあらかじめ用意してくれるから、言葉の選択に困らなくてすむということである。
神亀は早くからアル添酒をやめて純米酒造りをやっていた先進的な蔵というストーリーがそのうまさを際立たせるのである。
もちろんそのお酒が好きかどうかはまた別の問題であるが。
全量純米酒造りということを、税務署の意向に逆らって、いじめられながらも断行した小川原良征(おがわはら・よしまさ)専務という人がいたというストーリーがいいのである。
おっ、これがその「神亀」か、なるほど、なるほど、小川原良征のお酒か、納得、納得、と思いながら味わう「神亀」がうまいということなのである。
そういうストーリーがないお酒は、呑み手が一々自分でうまいかどうかを決めないければならならないから、呑んでいても気が疲れる。
そういう点では出来合いのものは、便利なのである。一から作るのは面白いのだが、面倒くさいことがある。
ストーリーは、その面倒くさい部分をはしょって、お酒のうまさに迫れるから便利なのである。
純米酒は下手に造ると、上手に造られたアル添酒よりずっとまずい酒になる。
だから、一概に純米酒はうまい酒と言い切る勇気は庵主にはない。
ただ、よくできた純米酒を呑んだときには、アル添酒なんかどうでもよくなってしまうということは事実である。
いい純米酒を口にすると、間違いなく「うまい」と思う世界にひたることができるからである。女もそうかもしれないが、男がうっとりできる世界はそれしかないだろう。
至福という言葉は、庵主は一生に一回しか使うことができない言葉だと思っている。最高がいくつもあるわけがないからである。
しかし、うまい純米酒に出会った時には、至福という言葉はこの時のためにあったのかと納得してしまうのである。
いいお酒に出会った時には、一升に一回使える言葉なのである。
至福という言葉は、普通は、頭がいい人が神に出会った時にそれを使うようだが、庵主はそんな観念的な至福ではなく、舌にしみ入る幸せに至福を感じているのである。
まともな純米酒を造るということは、呑み手とともに幸せを分かち合うということなのである。
三位一体という宗教用語があるが、造り手と呑み手とお酒はいわば三味一体なのである。そのいずれか一つが欠けてもお酒の世界は成り立たないからである。
「闘う純米酒」はそのたとえでいえば聖書ということになる。
純米酒原理主義を標榜するときにはその考え方の拠り所となる本である。
現にそれを掲げてお酒を造れば、実際にうまいお酒を造ることができることが証明されているから、もう二千年来終末が来るぞ来るぞと言い続けてきた聖書の預言のようなホラ話とは違ってその話には重みがあるからである。
今月もまたおいしいお酒の本にめぐり会えたのである。

★お正月の「蓬莱泉」★19/2/7のお酒
名古屋が故郷だという知人がいて、その人がお正月に帰省したときにお正月用に売り出された「蓬莱泉」(ほうらいせん)を買ってきて呑ませてくれる。
「空」とか「美」とかの定番ではないお酒である。百貨店がお正月向け商品として売場に並べるために要請したお酒ではないかと思われる。これが力のこもっているお酒なのである。
庵主は、大阪のお酒とか名古屋のお酒といってもすぐには銘柄が出てこなかったものだが、名古屋に関してはこの「蓬莱泉」の出現で、「醸し人九平次」(かもしびとくへいじ)のほかにも「蓬莱泉」があるということが定着したのである。
もちろんご当地には数多くの蔵元があるのだが、酒銘を知っていても呑んだことがないお酒は庵主にとっては知らない酒ということである。
この二つはいつでも呑めるから知っている酒なのである。
お酒は3本だった。吟醸酒と純米吟醸と純米大吟醸の「吟」(ぎん)である。
精米歩合は順に50%、40%、35%である。
「吟」はラベルに大きく魚の絵が描かれているのですぐわかるお酒である。平家物語の冒頭の「祇園精舎に〜」という文章も描かれている。
2年半の熟成を経て出荷しているお酒だという。
庵主にはうっすらと老ね香(ひねか)を感じられるのだが、知人はこの酒がうまいという。
老ね香は、それが自分にとって好もしいと感じた時には熟成香(じゅくせいか)ということになっている。
あばたもエクボなのである。
「吟」は手に入れるのが大変らしい。
完全予約制になっているのだが、しかし、お正月前になると名古屋の百貨店に何本が並んでいるとのことで、予約なしで手に入るそれを買ってきたのだという。
お酒の買い方にはいろいろ裏技があるようである。
50%の「蓬莱泉」はいい酒だということがわかるが、そつのない味わいでとくによしあしを言うまでもないお酒である。
貶すところもないが、誉めるところもない、さらにへんな癖もない、無難すぎておもしろみもないお酒だった。
堅物のお酒ということである。
写真のレンズに焦点距離50ミリというレンズがあるが、精米歩合50%のお酒というのはなんとなくそれに似ているのである。
こんど、精米歩合の%をレンズのミリ数になぞらえたものを書いてみようかとも思う。案外両者の数字には共通する性格があるかもしれない。
60ミリのレンズは、大方が50ミリを標準レンズとしているのにあえてそれを避けたところに妙味がある。
35ミリのレンズは、正常な見え方ができなくなる一歩手前のミリ数で精米歩合35%のお酒もまた奇矯の一歩手前にあるところなどはなんとなくその性格が似ていると思われるからである。
庵主が気に入ったのは、40%の純米吟醸である。
まだ若いお酒だから、「吟」のような深みといえばいえる熟成の味わいはなく、その分軽いといえば軽くて「吟」の趣(おもむき)と比べると物足りないということになるが、今進行中の味わいは元気がいい。その元気のよさが妙に心を引きつけるのである。
とくにうまいというわけでもないのに、もう一杯呑んでみたくなるお酒だった。
3本呑んでお気に入りが1本ということで、打率なら3割3分である。
またまた、いいお酒を呑ませてもらったのである。
持つべきものはいいお酒を呑ませてくれる知人である。

★晦日の酒★19/2/1のお酒
突然そのお酒が呑みたくなったのは、たまたま通りかかった居酒屋に、本日のお勧めのお酒としてその酒銘が書かれていたからである。
まともなお酒を呑みたいと思っていたからである。
そして、今度もまたきっと変わらぬ味わいにひたれることだろうという強い期待があったからである。
鳥取の「鷹勇」である。
うまい酒かというと、それは庵主がいううまいお酒ではない。しかし、いい酒なのである。お酒に一本筋が通っている、気持ちがいいお酒なのである。
紅おしろいつけて、私きれいでしょうと微笑んでいるお酒ではなくて、すっきりした表情で好きなら遊びにいらっしゃいという誘うこともないが拒むこともないお酒なのである。
姿勢がいいお酒なのである。わかる人だけ呑めばいいといった衒(てら)いもケレンもないところがいい。
そろそろ庵主にもそのよさがわかるかなと思ってその居酒屋に立ち寄ってみたのである。
一月の晦日の夜のことである。
月末(つきずえ)になるとなんとなく締めにお酒を呑みたくなるのは悪い癖である。
べつにお酒を呑みたいのではなく、また一月命をいただいたという感謝の気持ちを態度で表したいと思ったら、いいお酒を呑むしかなかったというわけである。
はしゃいだのでは回りの人に迷惑だし、この喜びを分かって分かってと他人に押しつけることもできない。
それで結局、生きている喜びを、お酒を味わうことで、その味がたしかにうまいということを確かめることで表そうとしたのである。おっ、まだ生きているぞ、という実感にひたるのである。
われ思う、ゆえにわれあり、といったのは頭のいい人だが、庵主の場合は、そんな知性的ではなくて、感覚的に、われ呑(くら)う、ゆえにわれ在りという質素な存在なのである。
その居酒屋で出てきた「鷹勇」は純米吟醸だった。
吟醸酒というと、最近はやたらと香りが高いものが多い。
各県がこぞって香りがでる酵母の開発をしているから、お酒が香水みたいになっているのである。
最初のうちは、吟醸香ですね、と愛でることもできるが、それはすぐに飽きるのである。飽きるだけならいいが、そのうち鼻につくようになる。
酒に香りはいらない。
吟醸酒を香り吟醸と味吟醸に分けことがあるが、香り吟醸の時代は終わった。酵母でいくらでも香りが出せるようになったからである。
いまは出過ぎる香りをいかに押さえるかが酒造りになったのである。
昔は雑味をとりのぞくためだった炭の使用が、これからは強い香りを吸着して取り除くために使われるようになるかもしれない。
時代が変わると意味が変わるということである。
庵主はどちらを取るかといったらもちろん味吟醸の方である。
きちんとお酒を造れば必要な香りは出てくるからしっかり味を造ればいいのである。
そういうお酒の一つが「鷹勇」である。
だから庵主はうまいとは思わないのに一目置いているのである。
そして、時に無性に「鷹勇」が呑みたくなる。
今度の「鷹勇」も呑む前に庵主が期待していた通りの味わいだった。
おもわず、うまいと思ったほどである。
お酒のうまさはこれでいいのだと思った。
庵主が普段呑んでいるお酒はうますぎるというのがわかる。
必要にして十分なうまさが「鷹勇」の純米吟醸にはあった。
一月の最後の夜は、期待通りのお酒が出てくるという幸せにめぐり会えたのである。



|