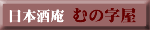
いま「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成19年1月年明けの日々一献
★うまいお酒は少ないということ★19/1/10のお酒
「むの字屋」はうまいお酒を紹介する酒庵である。
店舗はない。
ときどき、「そちらのお店の場所を教えてください」という問い合わせがあるが、ネット上にある架空の酒庵(しゅあん)ですよと答えている。ただし、そこにあるお酒はすべて本物ですよ、と付け加える。
現実の世界にはうまいお酒が多いのである。そういうお酒を愛(め)でているのである。というよりそういうお酒とめぐり会えた幸せを一人で喜んでいるのである。もう二度と会うことはないだろうお酒との出会いを書き残しているのである。
うまいお酒は本物の酒庵で呑んでいただきたい。
「書を捨てよ、街に出よう」といったのは寺山修司である。どういう意味で言ったのかは庵主はよく知らないが、そのキャッチフレーズ(惹句)の語感はいい。
その言い回しをそっくり借りると「書を捨てよ、呑みに出よう」である。
お酒だけは本で読んでいてもしょうがないのである。
まず、活字を読んでいたのでは酔っぱらわない。
そしてまた、お酒の味わいは文字では絶対にわからない。
大まかな味わいの説明はできるが、微妙な違いが言葉では伝えられないのである。
日本酒が持っている基本的な味わいなり香りを表現する言葉がないのである。
専門家には共通の言葉があるのだろうが、それが庵主のような素人にも分かるような言葉になっていないということである。
そこで、庵主は、しょうがないから、そのお酒を呑んだ時に心に浮かんだ思いを書き残しているのである。
面影からそのお酒を思い出そうというわけである。
当然、その味わいは他人にはわからないわけだから、そういう気持ちをもたらせてくれたお酒が実際にありましたよという報告をして、その酒の造り手に感謝しているということである。
米からアルコールを作ることは、本屋にいって日曜酒造りの本を買ってきてそのとおりに作ると2〜3日で簡単に造ることができる。
ただし、法律上はアルコール度数1%以上の飲用アルコールを無免許で造ってはいけないことになっている。
しかし、そのそのようにして造ったアルコールがお酒かとなると、市販のまともなお酒の凄さが分かるというわけである。
そういうお酒が四合瓶で1653円ぐらいで手に入るのだからありがたい。
突然出てきた1653円という金額は、庵主がためらわず買ってもいいことにしているお酒の上限価格である。それ以上の高いお酒は買わない。そういうお酒は庵主には贅沢なお酒だからである。
と書いてくると本当にお酒がうまいと思われても困るので実際のところをちょっと書いておきたい。
うまいお酒は、実は少ないのである。
まず、純米酒がうまくない。庵主にはほとんどうまくない。
というのも、純米酒はアルコールを混ぜたお酒よりうまい筈だという期待をいだいて呑むから、その期待と実物のギャップ(格差)に翻弄されるからである。
理屈ではうまいはずなのに、実際に呑んでみるとうまいと感じないのである。
もちろん純米のうまいお酒はいくらでもあるから、そういうお酒と出会った時にはアル添がどうのこうのという能書きはどうでもよくなるのである。
そういう純米酒のうまさが本当にあるからお酒はやめられないのであるが。
しかし、多くの場合はアル添のお酒より純米酒はうまいと思って呑むとがっかりすることだろう。
上手に造られた本醸造の方がずっとうまいと感じるということはよくあることである。
世の中には添加した原料用アルコールを感知することができる人がいるようだが、庵主はそういう能力がない。
よく、余興でやる利き酒のときに、これはアル添だと感じたお酒が実は純米酒で、これはアルコールがしっとりなじんでいるから純米酒にちがいないと思ったものがアル添酒だったということがよくある。
純米酒の方がアルコールくさいということが少なくないのである。
お酒は呑むしかない。量ではなく、種類をである。
その多くは自分の好みに合わないお酒であるが、一つか二つはいつ呑んでもうまいと感じるお酒が出てくるのである。
数あるお酒の中で、一つか二つである。
だから、いま自分がうまいと満足して呑んでいるお酒があれば、それはそれで十分幸せなのだと庵主は思う。
いろいろなお酒を呑んでみてもいきつくところは案外同じだったりするのである。もっともその遠回りを楽しむのが趣味だからそれはそれでいいのだが。
庵主の好みも大体固まってきたことがわかる。
その好みの範囲を外れたお酒を呑んでもうまいと感じないのである。
いいお酒だとはわかってもそれを体がうまいと感じないということである。
頭で感じた「うまい」はすぐ忘れるが、体で感じた「うまい」は癖になる。
うまい、というのは、また呑んでみたくなるということである。そういうお酒はほとんどないということなのである。多くのお酒は、一口呑めば十分なお酒なのである。
しかしである。時に彗星のように突然あらわれるとんでもないうまいお酒があって……。その先は、もう言えない、書けない。うまい、という感動につつまれて、もう能書きを書くことなんかどうでもよくなってしまうからである。

★2合のお酒★19/1/3のお酒
スバル360という自動車があった。排気量が360ccだからだという。
今の車は1000ccとか1600ccといった100刻みの排気量が普通であるが、なぜ排気量が360ccだったかというと、それはちょうど2合なのだという。
お銚子2本の排気量のエンジンで走っていたのである。
お酒を呑むことを、ちょっとガソリンを入れてくるということがあるが、そこからきたものか。そんなことはないだろうが。
ここで徳利の意味でお銚子と書いたが、お銚子と徳利は別の酒器である。
月桂冠のホームページによると『もともと「銚子」とは、あらたまった酒宴や三三九度などの儀式に用いる、長い柄(え)のついた金属や木製の器のことである。』という。
居酒屋で燗酒を入れて出てくるのは徳利であってお銚子ではないということである。正しくは燗徳利という。
燗徳利は1合とか2合とかの容量だがもっと大きいものもあった。
昔のお酒は今のように一升瓶に詰めて売られていたわけではないから、一升徳利とか五合徳利などの大徳利を酒屋に持って行って酒樽から小分けしてもらっていたのである。
アルコール依存症がアル中で通っているように、燗徳利のことをお銚子といっても同じ意味で通用しているということである。世の中はどっちでもいいということが少なくないということである。
そういうことにこだわる人をマニアと呼んで、且つその繊細な能力を羨望し、且つその能書きを聞くことの煩わしさを敬遠するわけである。
徳利というか、お銚子というかということでは、徳利というよりもお銚子といったほうが語感はいいと庵主は思う。
その1合という量のことである。
人間工学という言葉がある。よく工業製品の広告で、この製品は人間工学に基づいて設計されましたなどと書かれていることがあるが、よく考えたら、人間が使っているものはどれも人間工学にそって作られているのであって、人間に使いにくいものならだれも使わないのである。いや、使えないのである。
人間工学を別の言葉でいえば、人間にやさしいということだろう。
もっといえば、日本人なら日本人の体の大きさに合わせた使い勝手のいいものということである。
一寸、二寸といった単位や、一畳とか一間といった単位も日本人の体つきから導き出された実用的な寸法なのである。
お酒の1合もまた、日本人にとってちょうど一区切りの量だったというわけである。つまり合理的な量なのである。
毎日お酒を呑みたいのだが、どのくらいなら体を痛めないかという質問が健康雑誌などによく出てくる。
そんなに心配なら酒なんか呑まなければよさそうなものだか、そうはできないからの相談である。
普通は1日2合まで、週に1日は休肝日を作りなさいというのが模範回答である。
お酒が好きなお医者さんだと、日本酒なら1日3合ぐらいまでなら大丈夫という人もいるから、たくさんお酒を呑みたい人はお酒が好きなお医者さんに聞くと好ましい返事が返ってくるということである。
適正酒量について正しくいえば、体に合わない人には1滴でも有害だというのが正解である。
それほどアルコールに弱くない人なら、1日2合のお酒というのは妥当なところなのだろう。
お酒を呑み過ぎて体を壊すのは呑んだ人だけなのだから、質問に答えた人には実害がないので、2合までであろうが、3合だろうが、いいかげんに答えても全然問題ないのである。
しかし、庵主の場合は2合のお酒は多過ぎる。せいぜいが1合で適量である。
だから、お店では60ccの小さいグラスで2杯しか呑まない。2杯呑んでもなお一杯の余裕を残しているわけである。
2杯のお酒を呑んで立ち上がろうとしたときに、こういうお酒もありますよと珍しいお酒やもっとうまいお酒が出てきたときに応じられるようにである。
三日坊主という言葉がある。
よくそれが使われるのは日記をはじめるときにである。
年が改まったので今年からは日記をつけようとしても三日も続けたらあきてしまって続かなかったという話はよく聞く話である。
いまはパソコンを使う日記のソフトウェアがあって、それを使っているという人もいる。
ただしパソコンの日記帳には重大な欠陥があるのだという。
紙の日記帳なら一日分のスペースが決まっているからそれを埋めたら終わりだが、パソコンの場合はいくらでも書き込めるからきりがないのだという。
その気になれば、朝寝して1日8時間ぐらいしか起きていなかったときでも、その日記を書くのに8時間以上かかることがあると笑わせていたのはラジオに出ていた笑芸人である。
限界がないものはケジメがなくなるということである。不必要な淫蕩に陥るということである。
お酒も2合までという制約があることで淫蕩に身を沈めることを防ぐことができるのである。
庵主の場合はそれが1合までという線が引かれているということである。
1合のお酒というのはケジメの量なのである。
そのケジメを守っていればお酒は三日坊主にならないということである。
もっともケジメを守らなくても三日坊主にならないのがお酒だけれど。
人は「立って半畳、寝て一畳」という。それだけの広さがあれば人間は生きていけるのだという古人の言葉だが、それに加えてうまいお酒が1合あれば庵主は十分幸せなのである。

★燗酒ができるまで★19/1/1のお酒
初めてはいったお店で燗酒をお願いした。
そこの燗はうまいと聞いていたからである。
季節は寒風が身にしみる冬である。燗酒がうまい時期である。
その時間なのに、お店には客はだれもいなかった。
今夜は物日だからが客の出が遅いと大将は静かな口調でもらしていた。
まずお酒を選ばなくてはならない。
どれもいいお酒を揃えているからその中から一つを選ぶのに悩む。
「おこぜ」を選んだ。初めて呑むお酒だからどんな酒なのかはわからないが、酒祭りには燗がうまいとあったからその言葉を信じた。
酒に不足はない酒祭りだからその中にあるお酒ならどの酒を頼んでもかまわないのだが、ちょっと酒祭りを読んでみたかったのである。それほど味のある酒祭りだったからである。
「おこぜ」の能書きから呑んでみよう。それがおいしいのである。
庵主などは面倒くさいことはやりたくない方だから、その能書きを読んだだけでお酒を呑んだような満足感を感じてしまうお酒である。
漫画家の尾瀬あきらが実際にこのお酒に手をいれてきたお酒なのだという。
尾瀬あきらといえば、「夏子の酒」で多くの若者に日本酒のうまさを紹介した漫画である。庵主も全巻買ってきて読んだものである。
お酒は一食品であるが、それには、まず水がよくなくてはならないということがあり、原料米がどのように作られているのかという問題があり、その米を作る農地の土は大丈夫なのかということまで逆上って知らなくてはならないということで、日本人の食い物のよしあしを図るバロメーターであるということなのである。
米を食べることからパン等の小麦を食べるようになった人には日本酒のうまさは体が理解できないのではないか。
パンやピザやスパゲティーをたべならかお酒を呑んでもうまくないからである。そういうときにはワインだからである。
現在の日本酒はいろいろと問題を抱えているお酒なのである。
その尾瀬あきらが造りに参加してできたお酒が「おこぜ」である。
なぜ「おこぜ」というのか。庵主は知っているが、そのネタは別の機会まで取っておくのである。
「おこぜ」を造った蔵元は「睡龍」(すいりゅう)を世に出して一躍有名になった奈良の久保本家酒造である。
一躍有名といっても、庵主のお酒の世界に、そのとき初めて飛び込んできたということである。
「睡龍」はそのラベルがおもしろいのである。
どうおもしろいのかというと、龍が瓶を巻き付けているような形状のラベルなのである。
すでにそれを見たことがある人なら、そのことを言っているのかとわかるだろうが、知らない人はどんなラベルなのか想像がつかないかもしれない。
今はネットを探せばお酒の瓶を撮った写真がすぐ出てくるから、興味がある方は検索してみるとそれを見ることができるだろう。
「おこぜ」はアキツホの65%で醸した生モトの純米酒である。
庵主が生モトのお酒は苦手だということはいつも書いている通りである。
どこが苦手なのかというと、そのにおいである。
乳酸由来のにおいだと人に聞いたことがある独特のにおいがうっすらと時には激しく感じるのである。
老ね香に似ているにおいである。
生モトのお酒は力強い酸味が魅力だという。
ネタ元の「銘酒いづみ屋」のHPにいい言葉があったので引用しちゃう。
『 加藤[克則:庵主 注]杜氏の造られるきもとは最高に素晴らしく、クセが多いきもとではなくキレも良く、スッキリとしていて辛口です。
私は一年中きもとの純米をぬる燗で呑みたい方ですが、一番このきもとの良さが出てくるのは秋から冬にかけてほどよい熟成をした時です。』
ほら、呑みたくなってきたでしょう。
時は冬、まさに今。だから「おこぜ」のぬる燗を頼んだのである。
無口の大将は、といっても庵主が初めて入ったお店だったから話すこともないから無口でいいのだが、まず水を張った直径20センチぐらいの鉄鍋を火口に掛けた。
ガスの炎が水をじわっーと温めいく。
お湯になったころを見計らって、大将は取ってのついた徳利に「おこぜ」を入れてその鍋の中にいれる。 その間、待っている時間は長い。
他に客がいないこともあって大将は鍋の前に付きっ切りで燗の様子を見つめている。
しばしあって、大将は徳利を鍋から取りだして徳利の表面に指をあてて温度を見計らっている。
徳利の表面を布巾でぬぐったのでこれで「おこぜ」のぬる燗が呑めるかと思ったら、もう一度徳利の胴の部分に指を当てて温度をみたあと、再び徳利を湯の中に戻したのである。
店の中の時間は緊張感をはらんで静かに流れていく。
庵主の期待は徳利を見つめている視線に込められている。
大将は徳利を見つめながらもその気配は徳利で跳ね返って庵主に注がれている。
やがて、徳利を鍋から取りだして先程の手順を繰り返した。
徳利の表面が綺麗に拭かれた「おこぜ」のぬる燗が庵主の前に出てきたのである。
「ぬる燗でよろしかったですね」と大将。
陶の猪口が添えられている。
さっそく一杯目を猪口に注ぐ。
すぐには呑まない。
まずその香りをかいでみる。
アルコールがツンとこないのはもちろんだが、ぬる燗でもアルコールのにおいが先にあがってくるものがあるが、それは確かに呑みにくいと思う。
それが燗酒なのだと思わされた若い人が日本酒を嫌いになることは必定だろう。
出会いのお酒がよくなかったということが多いのが日本酒なのである。
呑んでみる。
かすかに生モトによくある、庵主の苦手なにおいがする。
あえてうまいとはいわないが、まろやかな味わいが楽しめるお酒である。悪くはない。
それよりもなによりも、頼んだ肴がうまかった。
一つは生のからみすみである。もう人は二伸の切り子である。
小さな器に入れて出てきた二品に「おこぜ」のぬる燗がうまい。
この酒とこの肴、お酒を呑むのが楽しい一瞬である。
お酒の伝統を感じるのである。
お酒によく合う肴をよく考えたものだと酒呑みの先達に知恵と工夫に感謝するのである。
うまいお酒を呑むということはまさに感謝の気持ちでお酒を味わうということなのである。
うまいお酒を造ってくれた人に、うまい肴を揃えてくれた人に、そして、それらのうまいものを生み出してくれたこの日本という風土に生まれたことに。



|