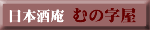
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成17年3月の日々一献
★名門のお店とあろうものが★17/3/30のお酒
池袋にあるお店である。名門である。
そのお店で、1合徳利が明らかに小さいのである。微妙に小さいのである。酒祭りに150ミリリットルとか120ミリリットルと明確に書かれているのならいい。しかし、1合の値段がいくらいくらと明記してあるのである。1合というのは180ミリリットルのことである。
そういうのは不正表示というのではないか。容量350ミリリットルと書かれている缶ビールに330ミリリットルしか入っていないとしたら、そんな商売をしているビール会社は社長が頭を下げただけではすまないことだろう。
あるいは、と庵主は「賢察」するのである。家賃が高いのだろう池袋の繁華街にあるお店である。東京の6畳間は畳の大きさが微妙に小さいというから、そのお店の1合徳利もまた団地サイズなのかもしれない。
「てやんでぇ、これが江戸前サイズってもんよ。江戸じゃ、当たり前のチンケ徳利(どっくり)を知らねぇのか」といわれたら、北海道生まれの庵主はすごすごと引っ込んでしまう。
いや、それは本当は呑み手に必要以上の酒を呑ませないための客の健康を気づかったお店の智恵なのかもしれない。多少酒の量が少なくても1合呑んだと思えば気分は一合なのである。少ない量で酔えるのだから体にはいい。そういう徳利を健康徳利と呼んでおこう。
いまは是正されていることだろうが、以前、泡盛の蔵元で瓶詰のときに微妙に量を減らして詰めていたところがあったと聞いたことがある。
非を直すなら今のうちである。客から指摘されてからでは遅過ぎるのである。
そして、同じお店でぬる燗を頼んだらほとんど常温のような温度で出てきた。まともに燗がつけられないのである。酒にはくわしいはずの名門である。冷蔵庫から出してきたお酒をそのまま出すような呑ませ方しかできないのだろうか。
いいお酒を揃えているだけに、また、名門の誉れ高い店であるだけに、惜しい、としかいえないのである。
というより、名門のお店ともあろうものが、そんな酒の出し方をしていて恥ずかしくないのかと思う。みっともない様を目にして、呑んでいる庵主の方が恥ずかしくなってしまったのである。

★純米酒の水準★17/3/23のお酒
日本酒は純米酒というのが酒呑みのあこがれである。なにも好んでアルコールを添加した醸造酒を呑む理由がないからである。ただ、一度途絶えた技術の復活は呑み手が思っている以上に容易ではないようで、手慣れたアル添酒のほうがずっと呑みやすいということが現に起こっていることである。
あるいは造り手のほうも居直って、アル添こそが現代の日本酒技術だと胸を張っていう人もいるほどである。うまい酒を安く造るのだから文句はあるまいという主張である。む、一理ある。
いい材料で作ったまずい料理と、材料は粗末だが食べてうまい料理とではどちらを選ぶかといったら、材料が毒でないかぎり、庵主はためらわずおいしい料理のほうを取る。酒も同じである。
しかし、造る人が造ったら、純米酒のキレのよさは呑んでいて小気味いいのである。わざわざ選んでまでアル添酒を呑むことはないと思ってしまう。
まずは長野の酒「大雪渓」(だいせっけい)の特別純米から呑む。
酒にさわやかな風(ふう)を感じるのである。「うまい」という味わいではない。が、いやみがまったくない。そして、「うまい」わけではないのに味に心ひかれるものがある。
ほら、女の人を好きになるときに、はじめはたいして好きだとは思わなかったのになんとなく心ひかれていく感じである。心が好きと思う前に、もう舌が好ましく思っているのである。そんな感じのお酒である。
庵主の好みに対してちょっとすげないと感じられるクールな味が庵主の気持ちをしっかりとらえてしまったのである。
つぎに「富美川」(とみかわ)の純米無濾過生酒を呑む。
これも思っていたよりキレがよかった。思っていたというのは以前「富美川」を呑んだときの記憶に照らしあわせてということである。もっともそのときの「富美川」は大吟醸だったかもしれない。比べることのできない話ではある。
この純米酒の味わいもまた、「大雪渓」の特別純米同様に、品がいいのである。
ちょうど躾がしっかりしている家庭の子供のようである。そのふるまいに気にさわるところがない安心感と好もしさを感じるように、ああ、いい酒だなという安心感と満足感を感じるのである。酒の味わいに心が落ち着くのがわかるのである。
そして、やっぱり(庵主にとってのやっぱりだが)「開運」である。ひやおろしがあった。順番として最後に呑む酒である。
これは「うまい」お酒である。あきらかに酒のうまさがある。甘みの程よさが庵主の好みなのである。辛口と称して、やたらとアルコールに頑張らせたお酒とは違う本来の米の酒のうまさが身と心にしみてくるこういうお酒が、庵主は呑んでいて楽しい。こういう気の合うお酒に出会えるということがうれしいのである。
純米酒で、醸造アルコールを薄めて飲んでいるみたいな辛口がほしいというのなら焼酎を飲んだほうがずっとずっとキレがよくて気持ちがいいのではないだろうか。焼酎なら翌日の酒の抜けもいいと聞く。
余談になるが、焼酎は本当にキレがいいのか庵主はよくわからない。庵主が焼酎を呑むときは、いつも何種類かを飲み比べて呑むものだから、翌朝はきまって胃腑にアルコール感が残っていて、焼酎はしっかり残るというのが常で、焼酎は翌朝のキレがいいという経験がないものだからよくわからないのである。
その点、お酒は適量未満しか呑まないから翌朝の目ざめは爽快なのである。ようするに呑み過ぎるから翌朝まで残るというのが真実ではないのだろうか。
庵主はただ酔いしれるための辛口なる日本酒は好まない。醸造酒の、前夜はうまい酒を呑んだぞという余韻が残る目覚めがいいのである。一杯のお酒で二日間楽しめるのである。すっと酔ってすっと抜けていく酒ではなんとなく損をしてような気がする。ようするにケチなのかもしれない。
お酒は米の面影がなくてはおもしろくない。ワインみたいな日本酒といった、何から造ったのかようわからんようなお酒などは、最初からワインを呑めばいいのであってわざわざ日本酒を選んで呑む楽しみがないではないか。
そして、庵主の苦手な乳酸由来の老ね香のようなニオイ(磨いた酒にはそれは少ない)がしない純米酒のさわやかさに庵主の好みは傾くのである。
今宵は、そういうきれいな純米酒を3杯呑んだのである。そしてきれいに酔ったのである。お酒を呑んだという気持ちよさだけが心に残ったのである。

★限界でも呑める一杯★17/3/16のお酒
もう呑めないと思った。思ったというより体がストップをかけているのがわかる。それ以上アルコールを体内に入れることに明らかに抵抗しているのがわかる。酒はもういい、と。
十分に酔いが回っている。いや頭で思っているより酔っていることは間違いない。場内で出会った知り合いが、酒臭いよと言っていたからである。場内一の酔っぱらいをやっていたのである。
場所は幕張メッセで開催されたフーデックスの会場である。食品の見本市である。酒はもちろんのこと、肉から魚から、パンだうどんだ蕎麦だカレーライスだと多くの食材が出展されている。中には試食はできなかったがワニやニシキヘビの肉まであった。おっと、庵主は爬虫類は食わない。
会場は広い、一日では全部見ることはできないほどである。
庵主の目当てはお酒である。ワインや輸入物のスピリッツ類もあったが日本酒や焼酎などの国産酒を重点的にみる。みるといっても、呑んでみるなので酔ってしまうのである。
全部は呑みきれない。気になるお酒だけを呑むことになる。
「七冠馬」(ななかんば)である。「国士無双」である。「黒松翁」(くろまつおきな)である。生モトの「大七」(だいしち)である。そして最後に呑んだのが「千代むすび」だった。
その間にもこういう機会でしか呑めない下手物の酒や、熟成酒などをたっぷり試飲していたのである。
「千代むすび」にたどりついたときには、完全に呑めない状態だったのである。
が、勧められるままに呑んだ純米大吟醸の「忠」(ちゅう)の燗酒がうまかったのである。うまかったというより、体がすうーっと受け付けてしまったのである。呑めないはずが呑めてしまう。「忠」の実力をあらためて知らされた。
限界にあっても、うまい酒なら呑めてしまう。だから酒は、いやうまい酒は体に毒なのである。
水分が足りなかった。出展されている仕込み水(を詰めたというペットボトルの水)を試飲した程度では間に合わない。こういう会場には水をたっぷり持って行く必要があると痛感したが、来年は見に行くことはないだろう。呑みきれないことが分かったからである。いや、体によくないということが分かったからである。
でもおいしかった。

★予兆、そして発症★17/3/9前後のお酒
花粉症の季節である。
庵主も花粉症である。とはいえ、去年もそうだったが、今年もそれほど花粉症の症状が激しくないのである。今年は去年に比べて花粉の飛散量が三十倍とかいって脅迫ともとれるような余計なお世話の報道がなされているので戦々恐々としているのだが、以前なら決まってあった朝起きるときの連発くしゃみが出ないほどである。
体が花粉症に慣れてしまったのだろうか、以前のように頭がどんよりしている日が続くと行った症状がないのでありがたい。
とはいえ、なんとなく花粉に反応しているような感じはしているのである。
2月26日の朝に今年初めてその予兆を感じた。起き掛けに鼻がちょっとむずむずしたのである。あるいは空気が乾燥しているせいで鼻が渇いていたのかもしれない。
その後も、くしゃみの連発、目が痒い、鼻がつまる、喉が痛む、頭がなんとなくすっきりしたないということが起こらず、今年はこのまま行くかなと思っていたところ、今日の(3月6日)の朝である。くしゃみが出た。
おっ、花粉症の症状である。アレルギーのせいか喉が少し痛んでいるようである。目にかゆみがある。いままで気にならなかったが、体はたしかにアレルギー反応を起こしているのがわかる。
ところが、それほど気にならない程度なのである。
根拠のない説を強引に繰り広げる。
花粉症の症状がおだやかなのは、いい日本酒を呑んでいるからなのである。日本酒には花粉症の症状を緩和する薬効があるということが体験的にわかっている。
市販されている花粉症の薬というのは対症療法薬であって、アレルギーをなくする薬ではない。それで症状がやわらぐのならいいのだろうが、全然効かないのである。
鼻水を押さえる薬をのむと、水分の分泌を抑えるように作用するのだろう、だから同時に喉が渇いてしまう。喉が渇くとこんどは喉がやられてしまうのである。
ところが日本酒の効果は、特定の症状に効くというのではなく、それぞれの症状を緩和するという形で押さえてくれるのである。やさしく押さえてくれるのである。
酒だからまずは呑み過ぎないことに注意しなければならない。沢山呑んだらいっぱい効くかというとそういうことはないので適量を呑みつづけることである。
呑む酒は純米酒である。アル添酒でもかまわないようだが、酔うために呑むのではないので、純米酒を少量(1日30ミリリットルを夜に呑む)呑むのである。真っ当な日本酒を、お酒の味がわかるという人なら選んでうまい純米酒を呑むことで花粉症をやわらげることができるのである。
日本酒を呑んでいる人は、花粉症には抗うことなく、だまっていい日本酒を呑んでいればいいということを知っているのである。
ということで、今夜も花粉症のために一杯だけ薬を戴くのである。
と、のんびり書いていたらとんでもない、とうとう花粉症が出たのである。そうなったら、おちおち酒なんか呑んでる場合ではない。
3月8日は気温が上がって花粉がよく飛ぶ日だった。その日、うっかり高をくくって街中を歩いてしまったのである。翌9日の朝、目覚めるとまず喉が痛んでいた。夜間、鼻が詰まっていたのである。鼻で息ができないから口で呼吸をしていたのだろう、ただでさえアレルギーで腫れ気味の喉はいっぺんに痛んでしまう。
と、起き掛けにくしゃみの連発である。鼻がムズムズしていつまでもくしゃみが止まらない。顔がはれぼったいのである。酒を呑んだわけではないのに火照っているような感じなのである。鼻がつまって鼻水が出るからどうにも頭がすっきりしない。目が痒い。とてもじゃないが、酒の味を楽しんでいるどころではないのである。
これからうまい酒がつぎつぎに出てくる時期だというのに、まったく。

★おっかなびっくり★17/3/7のお酒
うまいお酒が揃っている銀座のそば屋である。
「明鏡止水」「正雪」「長珍」「醴泉」などが酒祭りに並び、さらには今回の地震で大被害を受けた小千谷の「長者盛」まであって、お好きならば「萬寿」の1500円というのもあって、へぎ蕎麦といっしょ呑むお酒には不足のないお店である。
その中で庵主が選んだのは、一合1500円、1100円、900円、850円とあるなかで一番安い750円の「磯自慢」の特別本醸造である。
庵主には高い酒を呑むという習慣はないからである。ただうまい酒を頼んだら結果的に高かったということは往々にしてあるが。
「燗酒はできますか」と聞いてみたら「うちでは、燗酒は末広をお薦めしていますと」とのことだったが、ためらわず、「それなら磯自慢をぬる燗で」とお願いした。
「お酒は一合でよろしいですか」ときた。通常二合徳利だけれど一合でよろしいですかと聞いてきたのだろうが、それなら「五勺でお願いします」と言おうとして押し止めた。つい見栄をはってしまったのである。ほんとうは五勺で十分なのに。
この前(といってもかなり前なのである)呑んだ「磯自慢」の本醸造(その時も特別本醸造だったかもしれないが)のぬる燗が大当たりだったものだから、これまでそのことを吹聴してきたので、ほんとにうまいのかを確かめたかったのである。
無責任といえば無責任であるが、次から次に新しいお酒が目の前に現れるのである。同じ酒を二度呑むことなどそうそうめったにあるものじゃない。
きれいな女の人に会ったら、その顔を忘れられないように、うまい酒というのは一度あったら忘れられなくなるのである。正確には、その顔形ではなく、美人に会ったという強い印象(=インパクト)がであるが。「むの字屋」はそのインパクトをうれしそうに書きとどめているというわけである。ほんとうにうれしいのである。
だから、「磯」の本醸造のぬる燗が出てきて口をつけるときは、じつはおっかなびっくりだったのである。もし、ぜんぜんうまくなかったらどうしょう。
が、舌に乗ったときのまろやかさ、というのか、舌当たりの感触のよさというべきか、その味わいは絶妙なうまさだったのである。よかった。ほっとしたら、期待をうらぎることのなかったその味わいがまたいちだんとうまく感じたのである。
あと一枚、うまさを剥いだら、うまくもなんともなくなるという寸前の軽やかなうまさを感じさせてくれるのである。値段が高い「磯自慢」を呑んでも庵主はあまりうまいと思ったことはないが、この特本はいい。好きだ。
うまい燗酒は安い普通酒を燗にしたときのようなツーンとくるアルコール臭はないとは書いてきたが、あれはウソである。この「磯」の本醸造には、なつかしいツーンがほのかにあるのだ。しかし、口にふくむとそれは雲散霧消してしまい、ただうまいと感じる温もりだけがここちよく喉もとを、切れよく通り過ぎていくのである。
はぁーー、うめぇ。ここちよい。
銀座は中央通りの小松の裏の通りからはいる地下の店、へぎ蕎麦の「大剛」(だいごう)である。

★エールだ★17/3/2のお酒
博石館ビールがあると、庵主はためらわず「うまい」と思ってしまう。ベアードビールを見るとべつに飲みたいわけではないのについ飲んでみたくなる。よなよなエールの誘惑にも庵主は弱い。
パブロフの犬ではないが、それぞれのビールは、庵主の心の中では「うまい」という言葉と固く結びついているからである。
博石館の「ニーワヴァイス」は、エールビールの味わいである。ほっとする。ビールを飲んでいるぞという気分にひたることができるのである。
ラガービールの味を都会的だとしたら、エールビールは田舎っぽいのである。なんとなく手造りといった感じがするのはただ庵主の先入観なのだろう。
エールが手作り料理とするなら、ラガーは工場で造った加工食品のような、そんな違いを思い浮かべるのである。だから、手作りのほうに親しみを感じるのである。手作りが必ずしもうまいとは限らないのだが。
ラガーがちょっと気取った女の子だとすれば、エールはきさくな女の子といった感じである。庵主はどっちも好き。
2杯目はベアードビールである。「帝国IPA」である。
にがい、そして、この苦いところがこのビールのキモである。ニガイビールをあえてニガイとは言わずに飲み干すのが粋なのである。こんなニガイビールのどこがうまいのかというと、そのニガイビールをさもうまそうに飲むという仕草を演じることができるのが楽しいのである。
うまそうに飲んでいるのを見て、だまされて口にした人がおもわずまずくて、いや正しくは苦くて顔をしかめたときに、このビールが飲めないなんてまだひよっ子だなと気取って見せることができるのがカッコイイのである。男をかっこよく見せるビールなのである。ニガイのをぐっと耐えて飲むビールなのである。
最後の一杯は博石館のバーレーワインを飲む。ビールなのに、リキュールのような趣である。庵主にとっては最後にちょっと甘味がほしいときの締めの一杯なのである。最後といっても、庵主はビールもまた2杯しか飲めないから、それは3杯目のビールということである。
そして、隣に座っていた西洋風男外国人が、達者な日本語で、何かの会でエールばっかり続いたら、中の一人がスーパードライが飲みたい、ラガーを飲ませろと叫んだという話をしてくれた。
ラガーもまたうまいのである。

★もどかしさ★17/3/1のお酒
農口尚彦杜氏のお酒「常きげん」山廃純米無濾過生原酒・五百万石を呑む。
その力強い味わいに圧倒される。すごいパワーである。その風格といい、力強さといい、酸味のしまりといい、日本酒の実力を感じる。
実力というのは、お酒を飲んだときの充実感と満足感である。その一杯で、いい酒を飲んでいるという幸せ感に満たされるお酒であるということである。
五百万石だという。山田錦がエースだとしたら、五百万石は二線級のピッチャーである。にもかかわらず、一線級の投手にひけをとらない全力投球のみごとさにすっかり感心してしまったのである。
と、いいながらも庵主はそれを「うまい」とは書いていない。
たぶん、と庵主は思うのである。それは目一杯に踏ん張ったお酒の悲鳴だと思われる味なのだと思うのである。
いくつかのお酒で味わったその味の正体がいまでもわからない。というよりその味わいを、いや味わいというより香りといったほうがいいかもしれないが、その風味を人に伝える言葉が庵主にはないのである。
専門家に聞けば、ナントカ酸カントカのニオイだと教えてくれるのかもしれないが、どのニオイだと聞かれても、酒の味わいの中に含まれているこういうニオイだと説明できないのだから、それを確かめるすべがないのである。
しかし、明らかに、その味はある。
その味を感じたいくつかのお酒はというと、そのどれもが造り手が神経を研ぎ澄ませて造った勝負服ならぬ勝負酒といっていいお酒なのである。
そういうお酒ではなにかが起こっている。それによって生じたその味を、庵主はなんとも表現できないのである。もどかしいのである。あるのにそれを人に伝えることができないのだから。
その味のことを、庵主は内々にはただ「力(りき)み」と呼んでおきたいと思う。
庵主はその力みのあるお酒が苦手なのである。
案外、庵主が力みと呼ぶその味が米の味なのかもしれないが、もしそうだとしたら、いいお酒というのはそれを殺して醸し上げた味わいなのだと庵主は思う。
なんでもさらけ出してしまった味というのは呑んでいて疲れるのである。
芸事でも、10の力があっても5か6ぐらいで演じてもらうから見ていて心地よいのである。それを素人のように10に近い力を込めて演じられた聞いている方が疲れてしまう。
お酒もまた究極のお酒というのはあっても、限界の酒といいった苦しいお酒は迷惑なだけなのである。

 
|