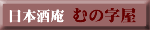
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成16年6月の日々一献
★悲しい現実★16/6/30のお酒
これは好みの問題だと枕を振っておく。好き嫌いのことだから、それが好きな人はそれはそれでいいのである。
美貌のタレントでいえばよくCMに顔を出している藤原紀香と菊川怜。庵主の好みで言えば、菊川は嫌い。紀香は好きだ。だからといって、菊川がだめで、紀香がいいということではなく、人それぞれの好みがあるということである。菊川がだめだったらCMに使う会社があるわけがない。菊川はある人には、いや多くの人たちには魅力的なのである。ただ、庵主にとってはちっとも興味がない女なのである。
「越乃寒梅」があるから呑んでみてといって勧められた。お酒を出してくれるお気持ちがうれしい。それが美女なのである。お酒よりそっちのほうがうれしい。
で、お酒を呑んでみる。
その時の庵主の心境を言えば、前の晩にお酒を呑みすぎたために体が酒を呑みたいという状態ではなかったこともあって、「越乃寒梅」ならあえて呑むこともないという気分だった。
しかし、名声に期待して口をつけてみた。
うまい酒というのは、ほんとうに体が求める酒である。気持ちでは呑む気がなくても体が抵抗なく受け付けてしまう酒である。
その「うまい」と思う味が人それぞれなのである。庵主は日本酒でいえば辛口の酒がだめである。呑めないことはないが、もう一口呑みたいという気が起こらない。
庵主が好むのは甘い酒である。というのも少量しか呑めないから最初からインパクトのある味の酒でなくてはならないのである。これもまた人の好みなのである。
「越乃寒梅」を呑んでみると、体が全然興味を示さなかった。頭の中では、これはけっして悪い酒ではないとは理解しながらも、アル添酒というのはこういうお酒なのかという思いで呑んでいたものである。
「越乃寒梅」にも別撰とか無垢とかの違いがあるのだが、「越乃寒梅」の何を呑んだかよくわからないものの、庵主には気合がはいっているお酒かどうかはなんとなく分かるが、アル添酒の違いはよく分からないからなんとなくアルコール添加を感じさせる酒だったということでそこまでは詮索しない。
たとえば、「久保田」の「百寿」と「千寿」の違いが、庵主にはわからないのである。そんな微妙なアル添の違いを区別して飲んでいる人がいるのだろうかといつも不思議に思っているのである。
新潟流のこういうお酒をきれいなお酒とか、水のようにさわりのないお酒とかいうのだろうが、庵主には買ってまで呑みたいというお酒ではなかった。
前夜の飲み過ぎで体力が弱っていたのだと思う。体が弱っているときはお酒を呑むものじゃない。せっかくのお酒がうまくないからである。なお、うまくないお酒はいつ呑んでもうまくないというのは庵主の経験則である。そういう点では好みはそれほどぶれなることがないということである。せっかくお酒を勧めてくれた美女の顔を見ながら、もっとうまい酒が呑みたかったというのがその時の感想である。
その前に飲んだ、普段なら抵抗なく飲んでいる発泡酒がまずくて飲めなかったのだから、この夜は相当飲み疲れていたのである。
実はそういう時に飲んでもうまいと感じる酒を知っているのである。庵主の長い経験による賜物である。

★昼間っからお酒×★16/6/26のお酒
昼間っからお酒を呑むというのは日本では御法度である。そんなけじめのない生き方は、やればできるがやってはいけないというのが世間の常識なのである。
ただし、なにごとにも例外があって、ご隠居さんが昼間から蕎麦をたべながら燗酒をのむというのは老後の楽しみとして許されているのである。長生きの余得である。
それができるようになるのが日本男の楽しみなのである。呑めない人は無理にそれをすることはないが。
やればできるがそれをやってはいけないという規範=けじめが世間様の目というものなのである。人殺しはやる気になれば誰でもできる。包丁もあれば野球のバットとか首を締める紐類がいくらでもあるのだから人を殺す道具には事欠かない。しかし、それをやっちゃおしまいだよ、というのが常識である。常識というのは相手もそう認識しているだろうという安心感のことである。だから、アメリカみたいに多人種がまざった社会というのは理想の社会などではなくて実はかなり緊張度の高い社会なのである。人種差別に鈍感な人しか暮らせない社会なのだ。それが見える人ならノイローゼになる社会である。アメリカでやたら精神科に通う患者が多い理由はそんなところにあるのだと思う。
国際化と称して、隣近所に黒人だの東南亜細亜人だの、白人でもそうだけれど、異人種が混じって暮らす社会はそれぞれの規範が異なる場合があるから安心が得られない社会なのである。落ち着かないといいかえてもいい。いまでもほとんど日本に同化している在日朝鮮人ですら軋轢があるのだから、多人種が混ざり合って暮らす社会というのは庵主は願いたくないのである。
なにも国際化と称して(国際化というのはそれで儲かる人の方便であってそれが正しいというものではない。国際化を声高にいう人のうさんくささはだれもがよく承知していることである)生活習慣が異なる人たちがいっしょに暮らす必要などさらさらないのだから。
韓国でとれた米、水はエビアン(あっ、これは硬水か)、杜氏は出稼ぎのブラジル人みたいな日本酒を呑みたいと思いますか。そんな物を造る必要性がないのと同様である。
庵主は、お酒は午後6時から午後10時までとしている。だから午後6時が待ち遠しいこと。時計をみて正6時に「解禁! 」と飲む生ビールのうまいこと。
それはさておき、昼間っからお酒を呑む人がいるのである。それをふしだらといわないで何といおう。
その日、庵主は誘惑に負けてしまったのである。
「第2回 究極の静岡吟醸を愛でる会」が都内で午後2時から開催されたからである。
「開運」「初亀」「志太泉」「高砂」「喜久醉」「花の舞」とあって、さらに「小夜衣」「國香」「君盃」「忠正」「英君」と東京にいたのではなかなか出会えない銘柄が並んでいるのだから呑まずにはおかれない。
仕掛け人は吟醸番さん。静岡のお酒にぞっこん惚れた呑み手が主催する会なのである。それでこれだけの美酒を一堂に集めたのだからその執念には頭が下がる。静岡のお酒のうまさを知っている人には垂涎の飲み会である。それもそのはず、静岡酒の応援団長といってもだれも異議をとなえないだろう目黒の清水さんがしっかり後押ししている。もうその名前を聞いただけで、この会には万障繰り合わせてでも出席したくなるのである。それだけの信用があるビッグネームである。選球眼もいいのだが、静岡のお酒の実力がまたすごいということなのである。
会場には期待を裏切らないお酒が並んでいた。
庵主は、はっきりいって、そのラベルを見ただけでだいたいの味わいというか、そのお酒の気魄を想像することができる。だから、あえて呑むまでもないのだが、ちょっと気になるお酒をつい一杯口にしたら、あとは体が勝手に酒を欲してしまった。そう、静岡のお酒はほんとうにうまいのである。
昼間からこんなうまいお酒を呑んでもいいのだろうかと、はじめは日本人として良心がとがめたが、呑んでいるうちにだんだん幸せ気分になってきて、庵主はとうとうけじめを忘れてしまったのである。
静岡酒の誘惑に負けてしまったのである。
深く反省。でも女子(おなご)の理屈と静岡のお酒の誘惑には絶対勝てないのである。

★「一品」★16/6/23お酒
特別純米酒「一品」(いっぴん)。
南部杜氏佐々木勝雄と襷(たすき)ラベルにある。
蔵元は茨城県水戸市の吉久保酒造株式会社。
佐々木勝雄杜氏といえば「東北泉」で名をならした名杜氏である。東北泉を辞めたあとは茨城の蔵元に移ったとは耳にしていたが、茨城の吉久保酒造だった。
山田錦で磨き55%である。
佐々木勝雄という金看板を掲げたお酒である。口にする時ちょっと緊張した。
「水のようにさわりのない」さらりとしたお酒である。
普通「水のようなお酒」というのは悪口である。たしかにきれいな水のようであるかもしれないが、それはうまみもないスカスカのお酒だったということが多い。水のようなお酒を呑むなら、庵主は黙って水を飲む。庵主が呑みたいのは技のあるお酒だからである。技のないお酒ならはっきりいって庵主でも造ることができる。
が、しかし、「一品」の特純は、奥が深い。ほんとうに、水のようには喉につかえることなく、喉元をなめらかに通り過ぎていくのである。
水は実際に飲んでみるとわかるが、結構喉につかえるものである。この「一品」にはそれがない。
香りがあるわけではない。いまどきの匂いぷんぷんのお酒に辟易している庵主はそれだけでもありがたい。酒は化粧品じゃないのだから、うまけりゃいいのである。
呑んですぐ感じるうまさもない。庵主は呑んですぐわかるうまさを好むのだが、それというのも庵主はお酒を小さいグラスで一杯しか呑まないからである。しかし、そういうお酒は2杯は呑めないといつも言っていることである。
アル添の普通酒とか本醸造酒が、呑んでいるうちにその味わいのスカスカなところが分かってくると、よくもまあこんな上手に日本酒もどきを造ったものだなあと白けてしまうが、そしてその手の酒を呑みやすい酒だと主張する造り手もいるのだが、この「一品」にはそういう逃げはない。
ちょうど薄味の吸い物を口にしたときのような、じわっーと沸き上がってくるうまさを感じるのである。
酒は造り手である。いくらいい原料を使ってもへたな人が造ったらそれなりのお酒しかできないのである。
お酒は呑めばなくなってしまう無形文化財である。それを今庵主はふんだんに呑ませてもらっている。ただしくは、そのお酒がたたえている気魄を味わっているのである。
庵主はアルコールには本当に弱い。ビールを小さいコップで一口飲んだだけで顔が真っ赤になってしまう。そしてそれが酒量の限界なのである。
お酒の正体がアルコールだけなのだったら、庵主は呑めなかっただろう。アルコールはいうなれば乗り物。それに乗っかっているなにかがお酒の魅力なのである。そのなにかのことを庵主は気魄と呼んでいるが、その気魄が庵主の心をひきつけるのである。
佐々木勝雄杜氏の「一品」にはそれを感じたのである。
いまなら、池上の「BON」(ボン)〔090−4208−9149〕で呑むことができる。

★純国産の食料はいまや純米酒だけ★16/6/16のお酒
日本の食料自給率は40%を切っているということでその問題点が以前から指摘されている。輸出するほどに生産量がある米国はもちろん、フランス・ドイツも自給率は100%を越えているという。食料自給率は国家の安全保障の面からもないがしろにできない問題なのである。べつに戦争に備えてというわけではなく、国民の健康を守るためである。
バブルの頃には、お金を出せばいくらでも外国から買えるのだから国内の農業の保護などはしなくてもいいという勇ましい意見が強かった。
それで何が起こったかのかというと、食品添加物がいっぱいはいった食品とか、腐敗防止剤がたっぷりかかった食品とかの得体の知れない輸入食品を与えられて、慢性的な疾患にさいなまされる生活がもたらされたのである。
和食が健康にいいとはいっても、豆腐とか醤油とか納豆を作る大豆はほとんどがアメリカからの輸入品であるし、蕎麦や、梅干しの梅などは大半が中国からの輸入品だという。
中国などから輸入されてくる野菜類にいたってはどうやって腐敗を防止しているのか考えるとそら恐ろしくなるではないか。
そういう中で唯一純国産品といえる食品は日本酒の純米酒だけである。国産の米、国内の水、そして日本人の手によって醸し出されたものである。国産食品の最後の砦なのである。
これが本醸造酒になると添加されているアルコールが輸入品である。そういう状況をグローバリズム(全地球主義)というのだろうが、地産地消が本来の食い物なのではないだろうか。
ところで、純米酒の速醸モトに使う乳酸菌が、これまでの培養で育てた乳酸菌から値段の安い合成乳酸菌がよく使われるようになったという。意外とそのへんが輸入品だったりして。もしそうだったら、最後の砦「純米酒」もすでに崩れかかっているのである。

★「純米大吟醸 阿部亀治 しぼりたて生酒」★16/6/9 のお酒
阿部亀治といえば、酒造好適米(ではなかったっけ。酒造米だったかもしれない。あえて調べないで書きつづけます)である亀の尾を明治26年に発見して育種した人とある。その亀の尾の発祥の地である山形県余目町の鯉川酒造が亀の尾で造った純米大吟醸ということである。
いい酒だった。酸味がしっかりしている。
最近庵主はこの酸味のいいお酒によく出会う。やたらと香りの強いお酒が多くなってきた日本酒の中で、このところ酸味がうまい、本当にうまいのである、そういうお酒がしきりに庵主に近寄ってくるのである。日本酒の新しい傾向を先んじて味わっているのではないかという思いがある。
「阿部亀治」は出会えることだけでうれしいお酒の一つである。
お酒を口に含んだときの緊張感がなんともいえないのである。お酒に、唇でふれ、舌で味わい、口の中で感じる、その一つひとつがいとおしいのである。こういうお酒を庵主はけなげなお酒という。
そういう心がときめくお酒が実はいっぱいあって、ただ本数が少ないからなかなかにはめぐり会えないのだが、日本酒を呑みつづけているうちにそういうお酒は向こうの方からやってくるようになるというのが庵主の実感である。
継続は力なりという言葉になるほどとうなずくのである。
なんでもそうであるが、たまたま呑んだ「阿部亀治」の亀の尾がうまかったからといっても他の亀の尾で造ったお酒がすべてうまいというものではない。亀の尾がうまいのではなく、造り手の技が上手だからうまいのである。
年に一回開催される「亀の尾サミット」に行っていろいろと呑んでみると、がっかりするような亀の尾のお酒もあるから、お酒の違いを実際に味わってみるとそのことが身をもって納得することができる。
だから、お酒はたくさん種類を呑んだほうが勝ちだと庵主はいつも思っているのである。

★晦日(みそか)の酒★16/6/2 のお酒
月末になると、ちょっといいお酒を呑んでみたくなる。いつもうまい酒を呑んでいるのだから、ことさらその月の最後の日に美酒にひたることもないのだが、なぜか気分がそうなるのである。しかも意志が弱いものだから、気がついたら酒場のカウンターに座っているのである。
いつもうまい酒を呑んでいるというと、日々贅沢をしているようだが、庵主はお酒はうまい酒しか呑めない体質なのである。しかも酒量は酒亭のご主人が顔をしかめるほどの少量である。庵主はすこしも売上に貢献しない客なのである。
いいお酒は少量でも十分に力がこもっているので、それだけで体が満足してしまうのである。満ち足りた気持ちになるのである。
一升酒を呑む人は不経済な体質の人ですねと庵主は思うのである。体質の違いは個性だからよしあしをいっているわけではない。
奈良の「八咫烏」(やたがらす)の大吟醸を呑みたいと思った。斗瓶囲いである。
うまい。
庵主がその時呑みたいと思っていたとおりの味である。期待どおりの味わいである。この味が呑みたいと思ったときにその通りの味が出てきたときはうれしくなってしまう。もうこの一杯で十分に満足である。気持ちのいいお酒を呑ませてもらった。
どういうふうにうまいかは敢えて書かない。庵主がうまいと納得する味なのだからおのずとその味は優雅に決まっているからである。あまくてまったりした大吟醸である。一杯呑んだら二杯目はいらない、いや2杯目は呑めないお酒である。二と2は意識的に書き分けている。
それですませてもよかったのだが、次に「酒一筋」の赤磐雄町の大吟醸を呑んだ。平成十二年度醸造酒である。
お酒の特徴を言い表すのには女性のイメージにたとえるとわかりやすいというのが庵主の実感である。またそのお酒の器量はは相撲にたとえるとわかりやすい。
それでいうと、「酒一筋」の赤磐雄町はまさに横綱の風格をたたえたお酒である。
酒に力がある。それでいてそれをひけらかすようなハッタリがないのがいい。いい酒は悠然としているのである。声高に主張しなくてもその品格のよさが伝わってくる。そして押しが強い酒なのである。
「獅子の里」の大吟醸を呑んでみる。+6とあるから、かなりの辛口と予想してはいたが、庵主が呑める限界の酒だった。
悪い酒だというのではない。透き通るような辛口の酒だったということである。もちろんそれはアル添のしすぎでスカスカの味わいになった酒とは全然別の毅然とした味わいである。力作である。こういう凛としたお酒を口にすると気持ちがいい。
さいごの一杯に呑んで、澄んだ気持ちになってお店を出たのである。
五月の晦日の銀座でである。

★山廃というお酒★16/6/1 のお酒
「山廃純米酒 貴酬 春霞」(きしゅう はるがすみ)が目に入ってくる。そういうものである。呑みたいと思っていたお酒が目の前にある。
山廃の春霞は、色がうっすら黄色がかっている。呑んでみると、濃厚で厚みがある酒である。しっかり造られた山廃であると思う。だが、山廃の酸味によるにおいと、お酒を熟成させたときのちょっと紹興酒のようなニオイと、ひね香とがどう違うのかが庵主にはわからない。みんな庵主のニガ手な味わいである。古くさいお酒のニオイとしか思えない。その手の酒を好んで呑む気はしない。
いいかげんな山廃ならそんな味わいが出ないから、本気になって造ればこの手のニオイが出てくる山廃をあえて造る必要があるのだろうかと思ってしまう。
しかも山廃という言葉はひょっとしてマイナスイメージの言葉なのではないか。庵主は本醸造という言葉に全然疑問をもっていないように、山廃という言葉も当然のこととして全然そうは思わないのだが、お酒の知識がない多くの人には産廃を思わせる腐ったようなイメージを抱かせる言葉なのではないだろうか。もしそうだとしたら、そういう言葉を平気で使っている日本酒業界のセンスを疑わなければならない。
「純米吟醸 丸本屋 生酒」(まるもとや)。岡山の「竹林」(ちくりん)である。ヴィンテージとあって14BYとあった。「竹林」の最高酒である。磨きは50%である。
生酒には二つの味わいがあって、一つはただただフレッシュなだけの敢えて呑まなくてもいいものと、もう一つがこの「丸本屋」のような深みのある生酒である。前者をただ若いだけの生酒とするならば、後者はしっとりした生酒である。
前者の生酒を呑まなくてもいいというのは、まずいからというのではなく、どれも似たような味わいなのでこれといった特徴が感じられないので、呑んでいても面白くないということである。
「丸本屋」を呑んだら、生酒の厚みを感じるのである。
「刈穂 稔り」吟醸酒生酒。いい酒である。ちょっと渋みがあって、それがまた庵主には最後の酒としてぴったりだった。
もちろん、生酒としては後者にあたる酒である。









