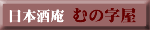
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成16年4月の日々一献
★カード★16/4/28 のお酒
庵主はカードは持たないことにしている。使いますかと聞かれたら「使いません」と拒絶することにしている。今それを通そうとするとけっこう軋轢(あつれき)があるのである。
ほおっておくとあっという間に枚数が増えてかえって不便だからである。使わないときには邪魔で必要なときにすぐに出てこないので煩わしいだけだからだ。
カードを持っているとお買い物代金が割引になりますといわれるが、さいわいなことにいまは、庵主は好んで値段の安い酒を飲まないように、数%のお代の割引をエサにつられて嬉々としてカードを受け入れるほど貧乏ではないのである。
お金の支払は居酒屋で学んできたからいつもニコニコ現金払いである。ツケで呑むことを潔しとしない。人の金で呑むことをよしとしない。まして社用とか公金で呑むことがあったときは極力遠慮して、といっても庵主は五勺しか呑めないからその遠慮はほとんど意味がないけど、人の金を目当てにお酒を呑まないことにしている。そんなことをしたらお酒に失礼だからである。いや、酒がまずい。
いい男が、クレジットカード(借金札)のポイントを稼ぐために支払をカードでやっている様を、CMの世界ではかっこいいということになってるのだろうが、庵主にははしたないとしか見えないのである。自分の買い物をカード会社にみんな見られても恥ずかしいとは思わないのだろうか。羞恥心はないのか。
次には、カードをいっぱい持つのは不便でしょうから、1枚でいろいろに使えるICカードを持ちましょう来るのだろうが、庵主は個人が特定できる仕組み(=カード)が不愉快だと言っているのである。呑むたびに庵主が呑んだお酒が記録されるようになったら、知っている人が見れば庵主の飲酒内容は贅沢の極みである。そんなことは恥ずかしくて他人には知られたくないのである。
いつも好んで呑んでいるお酒が分かればコンピューター(庵主は「電能」と呼んでいる道具。「電脳」ではない)が分析して、あなた様が呑むにふさわしい高級酒をご案内することができますのでぜひその便利さに浴してくださいということになるのだろうが、お節介なことである。第一、カードで麻薬が買えるか、と言っていたカード拒否者がいたが、そのうち、ご親切なカードは、いったん登録されたアルコール依存症の患者がお酒を買おうとしたら購入不可として支払を認めないということもやってくれるかもしれない。そういうのを便利というのだろうか。そういうのは監視といいます。
以前は、手がふさがっているので扉を開けるのに足で開けたら不躾とされたものだが、いまや自動扉なるそれに輪をかけた不精扉が蔓延している。中に入るタイミング(呼吸)が合わないと殺されてしまう回転扉というのも流行っているという。扉を開けるのも命懸けなのである。そういう電動式扉を便利というのだろうか。
酒ぐらい、好きに買いたいのである。ときにはまずい酒を呑んでみたいこともあるのだ。いまだに糖類を使った酒を造っている「雪中梅」を最近呑んでその技にびっくりしたことがある。いつもいつも高級酒しか呑めないというのでは不自由の極みでしかない。カード会社が考える「便利」というのは、ふりがなをつけると「ありがためいわく」なのである。
とはいっても、カードは、正しくいうとカードを使った人々を管理する方法は、どんどん進化してやがてカードも時代遅れとなり、眼球の光彩や指紋や声紋で個人を特定してそれと支払とが繋がるというとっても便利な仕組みが作られていくのだろう。そんな時代までは庵主は生きていないだろうと思うとありがたいことである。
瞳が濁っている盲とか、事故などで手足を失った指なしとか、癌などで声帯を取っちゃったカタワ(庵主がいま使っている辞書ソフトにはなんと片輪がはいっていない。そのうち、めくらと打ったら、目の不自由な方と変換される辞書が出てくるのではないかと心配しちゃうのである)はそうなってもやっぱり差別されるのだろう。不憫なことである。そんなときに宗教は、片輪者の心を癒してくれるのだろうか。いっしょになっていじめてくれることだろう。なんてったって、まず宗門カードがないと信者にしてくれないことだろうから。
ようするにうまいお酒を他人に監視されることなく存分に呑めるのは今だというのが結論なのである。
余談ですが、庵主はクレジットカードや会員カードなどのカードを定証と訳しています。与信定証、会員定証というわけである。そこまでカタカナ言葉を毛嫌いすることはないだろうが。

★近代社会とは己(ひと)を殺す社会である★16/4/24 のお酒
近代社会とは、すなわち現在の人間の社会というのは、「あらゆる可能性を誰か別の者の権利に委ねてしまう社会のこと」だと読んで虚を衝(つ)かれた思いがした。
出処はマツオカセイゴーである。松岡正剛で出てくる人である。
「政治は議員にあずけ、法律は弁護士にあずけ、食事をレストランにあずけ、洗濯をクリーニング屋にあずけ、笑いを芸能タレントにあずける。」と続く。そういわれてみるとたしかにそうであるが、そのことが、すなわち分業というのが当たり前だと思って疑ってみることもなかったのである。
すなわち、自分が持っている能力を自主規制することが当たり前だという生き方のことである。天から授かった能力を殺して生きることなのである。
「機能快」ということばは、渡部昇一の著作で読んだ。これもハタと手を打ったことばである。
人間は自分に備わっている能力を発揮することで快楽を感じるようにできているというのである。
たとえば、自転車に乗ること。最初は乗れないが、乗れるようになると気持ちがいい。庵主は女でないのでよく分からないが、女の人はその能力が備わっているのだから子供を生むことは快感なのだという。
料理もうまくつくれたときは内心で快哉を叫びたくなるものである。なるほど、自分が持っている能力を発揮することは快感なのである。
法律で一般の人の酒造りを禁止しているのは、女の人に対してお前は生んではいけないと出産制限をしているようなものである。
素人が質のよくないお酒を造って健康に差し障りがあるといけないから、国が責任をもって高品質のお酒を造って上げるのだという親切心からなのだろうが、たしかに高品質の普通酒にはそのお気持ちからくる誠意がしみじみと感じられるのである。
庵主としても、その建前はありがたい。選ばれた人しかお酒を造ってはいけないのだから、造り手に対して呑み手が満足するお酒を造ることを平気で要求できるからである。
むかし、カレーの「私作る人、僕食べる人」というCMに対して女性団体から、それでは女は男の料理奴隷ではないかという強硬な抗議があって、メーカーは即そのCMを引っ込めてしまったということがあったが、お酒の世界ではそのような非難の心配をすることなく、庵主は「あなた造る人、ボク呑む人」という実にありがたい立場に置かせてもらえるのである。
すなわち造り手は、庵主がうまいというお酒を造らなくてはならないのである。抗弁権はない。もし造り手が庵主の気に召さないお酒を造ってきたら、造り直せと言えるのだからたまらない。これほどの優越感を感じる立場はあるだろうか。卓袱台をひっくり返す星一徹の気分なのである。
近代社会になっても、食うことと病気は他人の能力におまかせできない事柄である。桑田次郎(今は桑田二郎)の漫画に「おしっこにいくなら、いっしょにおれの分もしてきてくれ」というのがあったが、食うこと、出すことは自分でしなければならない。自己責任なのである。
お酒を呑むことも、それ以前に呑むお酒を選ぶことも、他人がやってはくれないことである。
だから、庵主は先に日本酒に目覚めた者として、いうならばせ先覚者として、いまだうまい酒を味わうという機能快を知らない人に自腹をきってまでもその快感を教えているのである。
あっちの酒はまーずいぞ、こっちのお酒はうーまいぞ、と。

★ぴったり五勺★16/4/21 のお酒
破竹の3連敗から脱出するお酒を庵主は思い浮かべていた。必勝の投手はだれだろうと。
数有るお酒の中から直感で「王祿」(おうろく)の名が頭にうかんだのである。
島根の「王祿」なら、庵主の期待するところをその酒は応えてくれるだろうという予感はあった。
なにげなく入ったお店に、ずばり「王祿」があったのである。導かれているという思いを強く感じる。
「王祿」の純米吟醸と即決した。
正一合の蛇の目の猪口である。なみなみと注(つ)ごうとしているのを八分目で制して、と時すでに遅く、九分目を越えたあたりで酒は止まった。多分、この量では多いだろうなという気はしたが、野球のボール一個ぐらいの量である、ゆっくり呑めばちょうどいいかもしれないという甘い見方をしていたのである。
無色透明の酒が多い中で、猪口の中をのぞくと明らかに黄色い。うっすらと黄色いのである。
匂(にお)いをかいでみる。香りは高くはないが、艶のあるお酒の表面からは中身のあるお酒がもっている気品のある雰囲気が伝わってくる。そのひかえめな気風がいい香りなのである。この酒は間違いないと感じる瞬間である。
しっかり匂いの感触を楽しみながら、いよいよ口に含んでみた。
おみごと! である。うまい! といっても同じだが、庵主の期待にぴったり応えてくれたそのお酒の気合にすっかり感心してしまった。庵主の気分とぴったり合ってしまったのである。こんな気持ちのいい味はない。
酸味のうまさなのである。甘い酒ではない。が、酸味の美しさが甘美なのである。それをセクシーといったら、ちょっと色っぽく感じるけれど、いいのである、さわやかな魅力をたたえているのである。
料理を頼んで、せっかちな庵主にしてはいつになくじっくりと時間をかけて、味わいながら、楽しみながら「王祿」の冴えにひたっていた。そばにそのお酒があるということだけで心が豊かになる感じがするのである。
が、猪口の中のお酒が半分ぐらいになったときに、庵主の酒はぴたりと止まってしまったのある。体は正直である。わかっているのである。自分の限界を。
まだどれぐらいあるのかと猪口の中を見ると、ほぼ半分の量が残っていた。正一合の半分だからぴったりと五勺である。庵主の適量を、正しくは限界を目で見て知ったのである。
最初から小さい猪口でもらうべきであったとは思う。しかしである。生ビールをジョッキの底に少しだけいれて飲んでもうまくないように、一合入りの猪口になみなみと注がれたお酒の上の方のおいしい部分を口にするということが酒のうまさを存分に味わうためには正しい呑み方だと庵主は分かっている。とはいえ、ご飯粒一つでも粗末にしてはいけないと躾けられた世代だから、お酒を呑み残すということに罪悪感を感じて、そのことがかえってせっかくのお酒のうまさを内心の節度が働くことによってそこなってしまうのである。損な性分である。
「南」(みなみ・高知のお酒)の濁りを開けてみましょうといって、カウンターの中のご主人が注意深く一升瓶の栓を抜くと案の定瓶の口からは一気にお酒が噴き出した。噴き出したお酒は瓶の口から二十センチほども噴水のように宙に舞ってあふれた。見ると一升瓶の上三分の一ほどが空になってしまっている。
もちろん、主人は心得たもので、瓶の下には大きめのボウルを置いてあったから、お酒はこぼれたわけではない。
以前、噴き出したお酒をあわてて止めようとして栓をしようとしたら、カウンターに座っていたお客様の服に掛かってしまい、お詫びにいい酒を一升で勘弁してもらったが、貰った酒が旨かったということで、そのお客様からまた服にかけてくれと言われたと冗談をいっていた。それからはちゃんとボウルを置くようにしたという。
たまたま「南」の濁りを開ける場に出会ったものだから、カルピスサワーのような色をした濁り酒を御馳走になってしまった。
東十条の『あら川』でのことである。

★破竹の3連敗★16/4/14 のお酒
阪神が弱かった頃、連敗を脱出してやっと勝つとスポーツ新聞の見出しは「阪神1連勝」と書いて盛り立てるのが阪神ファンに送るエールだった。万が一、連勝するようなことがあると「破竹の2連勝」ということになる。
庵主が昨日呑んだお酒は破竹の3連敗だったのである。
茨城の「菊盛」(きくさかり)の純米大吟醸無濾過生が1杯目だった。
山田錦の45%である。これは十分にうまい酒だった。のだが、実はこの前に青森の「じょっぱり」の吟醸仕込みを呑んでいたものだから、「菊盛」の甘さが異常に甘く感じられたのである。
本来なら、最初にこの一杯を呑んだなら、あまみよし、香りも必要以上でなくてよし、酒の厚みもよしで庵主は十分に満足してその日を終えたことだろう。長生きしてよかったという思いで店を出たに違いない。
しかし、「じょっぱり」ではいやされなかった味わいを求めてこの名店に入ったのである。美しすぎる酒はいらなかったのである。ただ、満足を味わいたかったのだが、1杯目はいつもなら気にならないうまさが煩かった。
2杯目は静岡の「花の舞」の本醸造にした。すっきりしたお酒が欲しいと思った。
「花の舞」ならその純米吟醸の豊かな味わいを知っているから、本醸造もまた味に厚みがあるだろうと思ったのである。
本醸造というのはアル添酒だということをしっかり感じさせてくれる味わいだった。もちろん「花の舞」である。この本醸造だけを呑んだら十分に、いや十二分にきれいな呑める酒なのである。じつにきれいな呑みごこちが気持ちいい。しかし、この日は「じょっぱり」を呑み、そのあとに不足を補おうとして「菊盛」の純米大吟醸を呑んで行き過ぎてしまい、もとに戻そうとして呑んだ本醸造が先の2本のあとでは今一つ物足りなくて、かえって欲求不満が募ってしまったのである。
焼酎の「なかむら」の穣(じょう)があったので、度数で締めようと決めた。
小さいグラスで頼むと同時にチェイサー(追い水)も出てくる。
これはお湯割りにするといいですよというのを振り切ってストレートでもらう。仕上げの酒が呑みたかったのである。きりっと締めたかった。
が、度数が37度という中途半端なのである。といってもけっしてまずいというのではない。しかし、43度の味わいを心に描いていたところに37度が出てきたものだから肩すかしをくってしまったのである。
3連敗、しかも破竹の3連敗であった。
どれもいい酒だったのに、庵主が思い描いていた味わいと一つずつずれていたためにとうとう空振りの三振だったのである。
最初に呑む酒をまちがうと修復できないということを感じた一夜だった。
ダメなときは、その日は諦めたほうがいいということである。

★3月の締めのお酒★16/4/7 のお酒
3月の晦日(みそか)に、女の子と呑んじゃった。
とある会が思ったより早く終わったので、じゃあ、みんなでうまいお酒をちょっとだけ呑みに行こうということになって、そのメンバーの中に若い女の子が何人かいたのである。
もちろんお酒を呑んだことがない年頃である。
まず、自分が呑める量しか呑むなと注意した。呑んでみて自分の好みに合わなかったり、これ以上は呑めないと思ったら残してもいいといってから小さなグラスにお酒を注いだ。
2〜3種類の味わいのちがうお酒を呑み比べてもらうので、味わいをしっかり記憶に刻みながら味わってごらんと今日のお酒の呑み方を案内した。
わかりやすいお酒からということで、「十四代」の純米吟醸にした。米の表示はなかった。
かおりよし、味はほんのあまめで、初心者向きである。酒は呑めないという男の子がこれなら呑めるという。
「臥龍梅」(がりゅうばい)の純米吟醸をつぎに呑んでみた。これはあまさを振り切った端正な味である。辛口のうまさを湛(たた)えた酒である。もうすこしあまい感じの酒かと思って頼んだのだか、思っていた味わいとは違っていた。しかし、これだけ味わいの違いがはっきりしていると、初めてお酒を呑む人には二つのお酒の違いがはっきりわかるからかえって好都合だった。
三杯目に「鍋島」の純米を呑んだ。これはすごい。お酒が秘めている弾むような、いやはじけるような、口中いっぱいに広がるそのパワーに圧倒される味わいである。発散する力からみなぎっているお酒である。
一緒に呑んでいたお酒を呑みなれている無口な呑み手がそれを感じて感嘆のあまり「この酒はすごい」と口にしたのである。庵主は得たりと思ったが、若い子にはその違いがよくわからなかったようである。
「この酒を最初に呑んでいたら、さきの二つのお酒はひ弱に感じてその旨さの印象が薄れていたところだった」と、庵主は呑んだ順番がよかったことを内心で喜んだのである。
一人の女の子は宮崎県の生まれで、日本酒はだめだということで芋焼酎を呑んでいたが、これも一杯ごとに違う銘柄の芋を味わってもらったら、その味わいの違いがおもしろいと喜んでいた。「十四代」にちょっと口をつけてもらったら、このお酒はうまいといったのである。日本酒を知る人が一人増えそうな気配がする。

★どこの世界でも知らないうちに★16/4/1 のお酒
ある新聞社の校閲部長のところに新聞記事に対する苦情が来たという。文化部の記者が書いたコラムに引用した森鴎外の文章が現代仮名遣いになっていたのをとがめるものだった。
その記者に「原文引用の際は、仮名遣いも原文のままにするように」と申し入れたところ、記者がコラムに取り上げた書籍に引用されていた鴎外の原文がことごとく現代仮名遣いに直されていたという。現代仮名遣いの方が今の読者には読みやすいからという親切心からだろう。いや、その方が本が売りやすいからというのが正解かもしれない。要するに読み手を馬鹿にしているのである。
「ら拉」とか「建ぺい率」と表記して平然としている「よみうり新聞」(庵主の愛読紙)や「あさ日新聞」なども底意はそんなところにあると思われる(異体字は読者に読めないだろうと慮(おもんぱか)ってひらがなを使用しました、って言われるとすごく失礼でしょう)。難しい漢字をひらがな書きにするのは、俺達は大学出てるから文字が読めるけど、読者は中学程度の学力しかないだろうからそれは親切心だというのである。自分が作っている商品自体を馬鹿にしているのである。だって辞書を引く手間をおしむほど向上心のないズボラな読者しか読まない商品をなんのために作っているのだろう。新聞の作り手は自分の仕事に対する矜持はないのだふうか。
もちろん、新聞社が知っていても言えないところを皮肉っているのである。そういうのを質が悪いという。
見た目はよく似ているのであるが、現代仮名遣いに直した旧仮名遣いの文章は似て非なるものである。味わいが違う。そのよってくる精神性の高さが全然違うからである。
日本酒もそうである。いつの間にか、アル添酒が大手を振って跋扈している。(経済的に)呑みやすいからである。売りやすいからといったほうが本当のところなのだろう。
純米酒もアル添酒もよく似ているのである。はっきりいって庵主には呑み比べてもその違いはわからないほどである。しかしその精神は全然違う。志とするところが異なっているのである。その微妙な違いがわかるということが文化なのである。バターのかわりによく似ているからといってマーガリンを使えますか。
文化の味わいというのはその民族の心遣いなのである。こだわりといってもいい。何にこだわるかということなのである。はっきりいって、実用的にはどうでもいい部分の味わいのことである。
小津安二郎という映画監督がいた。「東京物語」とか「秋刀魚の味」という映画を作った人である。その映画では、場面が変わるとまずその舞台を示す画面がはいる。たとえば、場面が工場に変わったら、工場の煙突から煙が昇る風景だけのシーンをややしばらく挿入するのである。この映画をテレビで放映するときには上映時間より短い放送時間に合わせるためにこういうシーンが真っ先に削られていたものである。その部分がなくてもストーリーはちゃんと分かるからである。ところが、そういう一呼吸の部分が小津映画の味わいなのである。テレビ放映の時は未熟なテレビ患者、おっとどんなテレビ看者でもわかるようにとストーリーを優先させてやってはいけないことを平然と行なっていたのである。味わいのない病院食のような映画を文化だと称して垂れ流していたのである。
アルコールの味がしない酒とか、甘くない砂糖を、それぞれ酒だ砂糖だといっているようなものである。テレビはタダで見ることができるから、長い間それに気が付かなかったのである。タダほど高いものはない、の実例である。
これって、著作人格権の侵害ではないのか、と今にして気がついた。庵主はテレビを持っていないので最近のテレビがどうなっているかはわからない。
庵主が呑みたいのはお酒であって、アルコールのはいった飲物なのではない。アルコール依存症ではないから大量のアルコールは必要がない。だから、うまい酒しか呑まない。いや、そういうお酒しか呑めないのである。「だって人間だもの」。
お酒に秘められている文化の香りを味わいたいのである。
日本酒にかぎらず、典籍でも、温泉でも、鶏卵でも、ちょろちょろ変わる教育指導要項も、知らないうちにいつの間にか中身がすり替えられていたのである。日は4月1日であるが、そのことはウソではない。








