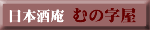
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成15年12月の日々一献
★傀儡国家★15/12/26のお酒
たまたまはいった大衆食堂で目にした「ビックコミックオリジナル」。「龍」第311話の脚注。「作品中の満州は現在の中国東北部。かつて日本が一方的に取り決めた傀儡国家の名称」。
庵主は心の中で赤字をいれる。語句の位置を正しく入れ換えるのである。「傀儡国家日本がかつて一方的に取り決めた名称」と。
東京政府のうしろにアメリカがぴったりとくっついていて、アメリカに言われる通りに動いている時の首相の姿が操り人形を見ているようである。操りの糸が見えるのがいけない。傀儡国家の定義が今日の日本にそのまま当てはまるというのが悲しい。それを知っていながら営業上けっしてそのことを書かない新聞しかないので庵主は新聞を読んでいると欲求不満になってくるのである。あー、つまらない。もっと面白い新聞が読みたい。
そのつまらなさを癒してくれるのが、まっとうな日本酒なのである。本物にふれることで心がはずむからである。いまの新聞は読んでもちっとも心がはずまないではないか。
戦後、長く日本酒の世界を席巻していた悪名高き三増酒の起源は満州にあったと本にある。戦時中、満州では原料となる米が不足して、まともに造ったのでは需要を満たすことができなかったことから、清酒もどきのアル添酒を造って供給したという。そのことが戦後の三増酒という大悪(たいあく)の呼び水となったのである。戦後の酒造家は良心がマヒしてしまっていたのである。酒造家を責めない。戦争に負けるということはそういうことなのである。
いったん導入された制度はなかなかもとに戻せない。それにかかわる人がそれで生活するようになるからである。その制度を急にやめろと言われたら死ねというようなものだから、当事者は制度の廃止に対して徹底的に抗戦してくるからである。
さすがに今は三増酒を目にすることは少なくなったが、アル添はなお全盛である。その酒をまずいとは言わない。量を呑まない庵主はただそれを選んでまでは呑みたくないと思う。アル添をすぐやめろとはいえない。それで食っている人達が必至になって反対してくるからである。また、反対の理由はいくつでもあげられるからである。
「戦後の代用酒であるアル添酒を造るのはもうやめようよ」というと、「純米酒でもまずい酒はいくらでもある。それよりアル添のほうが実際には呑みやすいことが多いのである。呑み手の好みを制限するのは間違っている」。「伝統的日本酒は純米酒である。アル添という紛い物の酒をおおっぴらに造るというのは日本人の恥である。今日メイドインジャパンは世界各国で高品質の代名詞として使われているときに、お膝元の日本酒が代用品のような酒であるというのはいかがなものか。酒を造る人間としての自尊心はどこにあるのか」というと、「酒は時代とともに変わってきている。いま呑まれている酒が本物のお酒なのである。いまどき大八車で貨物輸送をしようとする人がいないように、自動車という新しい技術が開発されて荷物運びはトラック輸送が当たり前となっている。同様に、日本酒の造り方も進歩しているのである。いまは精米歩合も江戸時代とはちがって高精白となっている。昔のように低い技術で造っていたときの酒と現代の酒を比べて今の酒に非をならすのは、トラックをやめて荷車に戻れといっているようなものである。いたずらに進歩をめざすという人間の性を否定することは現実にそぐわないできない相談である」。
どんなことでも、意見を聞いたなら、ああ言えばこう言うでいくらでも反論はできるものである。
生きていることと死んでいることは、論理的には同じであるという笑い話をきいたことがある。「生=死」を証明するという。等号の両辺に同じ数字を掛けても割っても値は変わらないのだから、両辺を2で割る。「生/2=死/2」となる。両辺は等価である。すなわち、半分生きているのと半分死んでいる状態は同じである。よって生と死、生きていることと死んでいることは同じことであるという。
この伝で行くと、うまい酒とまずい酒も同じものになるから、一方を排斥することはできないことになる。
ビトンやグッチにだってニセモノがあって、その需要があるというのが世の中なのだから、日本酒のまがいものも毒ではないかぎり放っておいてもいいのじゃないかということもできる。
ビトンやグッチならニセモノの横行で損をする会社があるから必死になってニセモノの排斥が行なわれるのだろうが、日本酒ならそういうこともないだろうからなにも急いでアル添酒を排除する切迫性はないのである。
ただ、アル添酒はアルコールという観点からそれを添加したという事実だけで税金を高くすればいいのである。アルコールの摂りすぎは体によくないよという親切心からである。それでもその手の酒が呑みたいという人は自由に自分の体を痛める快感にひたっていいのである。
信念に基づいて、俺はアル添酒を造りたいという人は造ればいい。そして、その手の清酒はリキュールとか合成清酒と表示して、本来の清酒とは明確に区別して呼べばいいのである。
マーガリンを、似ているからといってバターと称して売ったら、今時の消費者はそれを不当表示として怒るだろう。そういう商売をする人は非難を免れないことだろう。そうならないように、お酒の造り手はお天道様の下を堂々と歩けるように正道を歩いてほしいのである。
徴税のための傀儡酒だけは造らないでね。

★この店がうまいよ★15/12/24のお酒
口コミである。お酒がうまいお店があったよと教えてくれる人がいる。だから、すぐに確かめに行くのである、庵主は。
どんなお酒を呑ませてくれるのだろうかという楽しみよりも、そういう評判のいいお店をやっている人に会いに行くのである。お酒を大切に扱っている人の心ばえを見に行くのである。ここにも同好の志がいるという安心を味わってくるのである。
日本酒は酒だけ呑むというのならこんな手抜きの趣味はない。酒なんか、酒販店をさがせばどんな酒でも手に入るといってもいい商品である。
庵主の子供の時分は切手収集というのがはやっていた。業者に踊らされていたのである。記念切手をシート買いする小学生に注意しない郵便局もその業者の一味だった。切手屋さんに行くとカタログに載っている切手は全て売られていて、てっきり物がないので高値を付けているのだと思っていた「月に雁」も金を出せば手に入るのだということを知って切手集めがばかばかしくなった。見たい切手は切手屋に行って見てくればいいのだから、なにも自分で揃える必要がないと知ったからである。コレクションを切手屋に預けてあると思えばいいのである。収集道をだれも教えてくれる人がいなかったものだから、庵主の切手収集はその次元で終わってしまった。
幻の酒と喧伝されている酒でも、本当に手に入らない酒だとしたら、要するに買う人がいないので物がない酒ということだから、酒が売れないことには蔵元が成り立たないので、それは幻なんかではなく絶滅した酒ということになる。恐竜酒とでも呼んだほうがいいだろう。
「求めよ、さらば与えられん」というのは、聖書の言葉だったろうか。お酒も、呑みたいという思いを抱くと、なぜかその酒とめぐり会えるものなのである。そういう経験が庵主には何度もある。お酒が庵主を呼んでいるのではないかと思うことさえある。ということは日本酒の世界というのは庵主が思っているより狭い世界なのかもしれない。
聖なる言葉に、なるほど、思い立ってまず行動を起こすことが夢をかなえるコツなのだと知るのである。個人にとっては初めての体験ではあっても、ひもとけば先人がすでに経験したことであるということが記されている宗教の書は智恵の集大成なのだろう。そしていくつかの宗派が並立してあい争っているのは、人はなかなかに人となじめるものではないという智恵を示しているのだろう。なじめないのなら離れて暮らせばいいじゃないか。きらいな奴と顔を付き合わせて暮らしていくるからいさかいになるのである。
きらいな人や、きらいな酒があっても当たり前のことであるという智恵がそこに見いだせる。石版に刻まれて残されていたという記録はあるいは前の文明の名残なのかもしれない。いま生きている人間のしきたりなんかは、五十年前とか、百年前といったつい最近に始まったものも多い。その程度のことを昔から伝わってる真理と勘違いしていることが少なくないのである。
日本酒も、戦前のお酒は昭和17年以前は米だけで造った純米酒であった。それまでの伝統的な造りにアルコールをいっぱい混ぜて増量した今日の破壊的な日本酒は、二千有余年の歴史を誇る(庵主はいつも疑問に思っているのだけれど、日本の歴史ってたった二千年ぐらいしかないのだろうか。中国は四千年だというのに。もっとも建国二百年ぐらいの米国がお山の大将をやっているのが今の地球のありさまなのだから、歴史書をいくら読み返しても本当の事はわからないというのが庵主の実感である。日本の古代史なんかは遺跡が出ることにコロコロ変わるし、そもそも歴史書というのがだれかの都合のいいように書かれている本なのだから表面を読んだのでは本当の事がわからないのは当たり前のことなのである。歴史の本を読めというのは出版社の宣伝文句である。こんどのイラク派兵にしても先の戦争の時とちっとも変わらないアメリカの罠に日本は前回と同じような反応を繰り返している。いくら歴史書を読んでいても人は変わらないということを知るだけでなんら役には立たないのである)わが国の悠久の歴史の中では、つい最近造られたお酒なのである。さらに庵主が日常的に呑んでいる吟醸酒にいたっては昭和五十年頃からふつうの人でも口にすることができるようなったお酒なのである。吟醸酒を長い伝統に培われた本邦の誉れの酒と勘違いしはいけない。昔は今みたいに高精米ができなかったから、それはつい最近造られはじめた狂い咲きといっていいお酒なのである。呑み手も、その贅沢の極みに酔っているのである。うますぎる酒の世界に足を踏み込んで狂喜しているのである。酒自体はうまいものであってはならない。呑みすぎちゃうからである。うまいのは酒を呑む場の雰囲気でなくてはいけないのだ。
一人で超別嬪酒を呑んでいるときのゾクゾクする気分は堕落の極みといっていい。でも、堕落したいのである。そういう酒は人に語りかけてくるからである。人間の記憶をよびさます魔力を秘めているからである。酒の力で狂うことができるからである。いまはどうか知らないが、昔の坊さんが大麻をたいて狂気にひたって神をみたり、てっとりばやく仏といっしょになったように錯覚したりしていたのと同じ悦楽を凡夫は酒で味わうことができるからである。聖書に出てくるツノが何本もある獣とか、いくつもの動物が合体した獣などは大麻でラリって見た幻覚なのではないと思っている。素面で読んだら何をいっているのか意味がわからないのである。聖書のその部分は読む方も大麻の助けを借りないとその面白さが理解できないのではないのか。本に書かれた説明を読んだだけで大吟醸のあのうまさを理解できるわけがないように。なお、いま大麻はわが国では御禁制であるから、聖書のクライマックスを存分に味わえる人は少ないのである。
庵主は幸いお酒が呑めない体質だから、ちょっと味わって終わりである。だからお酒のクライマックスを知らずに終わるのだろうと諦めている。とはいえ、その門前に立って、扉を押したのである。そして、ちらっとその中を覗いたのである。中を見たことがあるというところが庵主のささやかな矜持である。
そんなにいい酒とされていないお酒でも呑んで楽しい場がある。酒で話がはずむと時がある。そんな時は酒がうまい。一人で酒を呑むという行為は実は中毒症状なのではないかと思うのである。いわゆるアル中は正しくは依存症という。アルコール依存症である。精神的に酒の誘惑から離れられないのだろう。
酒がうまいお店があったと教えてくれる人は、その店でいい雰囲気のお酒を呑んだのである。うまい酒を呑める場を得た人なのである。その場があるところが居酒屋なのである。
居酒屋に行くと、うまい酒とうまい肴と、おいしい話題がある。燗酒もうまい季節になったし、ちょっと寄って行きましょうか。
懐は今ちょっとさびしいが、心をあっためて帰りたい。

★「鶴齢」の意外や意外★15/12/17のお酒
新潟県塩沢町の「鶴齢」(かくれい)。
庵主は新潟のお酒と聞くとつい身構えてしまう。また淡麗辛口、いや淡麗すぎる薄酒と思い込んでしまうからである。そういうお酒が一世を風靡していたからである。水のように呑めるいい酒だねという。お酒を沢山呑める人はそれがいいのだろうが、庵主は量が呑めない酒呑みだからそれではダメなのである。最初からうまいと感じることができる甘めの少しアルコール度数が高い酒でないといけない。これは好みの問題である。だから新潟の酒と知ると、選んで呑むまでもない、ついでの時にでも味わっておけば十分だと思っていた。
「鶴齢」という酒銘もデパートなどに並んでいるのをよく目にしているが、見ると新潟の酒なので、あえて呑んでみたいと思うことはなかった。
が、先入観というのはよくないということを思い知られされたのである。
「鶴齢」を呑む。
まずは「源左衛門」(げんざえもん)純米のにごり酒。庵主は、この手の酒は評価しない。いやできない。どこの蔵のを呑んでもさほど味が変わらないからである。どれもうまいのである。いや、うまいと思わされるのである。その手の酒は口当たりがいいから、そう感じるのである。
評価はしないけど、この手の酒はうまい日本酒を呑んだことのない人を日本酒の世界にいざなうときに、まずこの酒を呑んでもらうと興味をそそらせる酒だということを知っているから、日本酒の悪口をいっている人に最初に呑ませる酒としては重宝なお酒なのである。
おりがらみとか、うすにごりなどの炭酸がまだじゅわじゅわ生きている口に心地よい日本酒は食前酒、いやまっとうなうまい日本酒を呑む前のイントロとして、酒を呑む前のお酒だから酒前酒として最適なのである。
「源左衛門」の一杯で、さあ、酒を呑むぞという気分になった。
びっくりしたのは「平野屋」(ひらのや)である。本醸造の生原酒である。
これがすごい。うまいのである。技をことさら主張することのないひかえめな大吟醸を呑んだときに感じるおだやかな品を感じるいいお酒なのである。
そう、お酒の品格がいいのである。味わっていると、その品が自分の中にしみわたってくるような優雅な気分にみたされる。酒が心にしみてくるのである。こういうお酒と出会えるから日本酒はやめられない。呑むのをやめるには惜しいのである。
日本酒は文化である。日本人がそれを嗜まなければ文化がすたれる。だから文化をきちんと継承するために庵主は努めているのである。努めるだけの価値がある。
ときにデーターだけは大吟醸というお酒に出くわすことがある。精米歩合は50%以下である。米はたしかにいい山田錦を使っている。裏ラベルに書かれているデーターを見るとはたしかに大吟醸なのである。しかし、味はというとたしかに悪くはないが、もっともっと値段の安いお酒のほうがうまいなぁと思う大吟醸があるのだ。本醸造の「平野屋」はそういう大吟醸よりずっとずっと味わいがあるいい酒である。手にはいったらお買い得である。
「鶴齢」の初代蔵元の名前が平野屋源左衛門である。この二本で蔵の姿勢と矜持を十分に感じることができる。気品のある味わいにうたれた。
美山錦の特別純米を呑んでも、特別純米の無濾過生熟成原酒を呑んでもその気品のある味わいは変わらない。十分な味わいをたたえたお酒である。この日用意されていた純米大吟醸は呑むまでもないと思うほどである。庵主が美人の厚化粧と呼ぶ必要以上にうまい酒になっているはずである。そのとおりだった。値段のことを考えなければうまい酒ということである。
また、一つ新潟のうまい酒を知ったのである。
ところで、ワープロを使っているから気にならないが、これを手書きにするとなると「鶴齢」は漢字2文字で書く酒名としては最高画数ではないかと思われる。昔の人は草書でさっと書いたのだろうから画数が多くてもさしつかえなかったろうが、字の書けない庵主はいまワープロの便利さに感謝しているのである。

★農口尚彦杜氏の語り書きが出た★15/12/10のお酒
「菊姫」の、いや、いまは「常きげん」でお酒を醸している、農口尚彦(のぐち・なおひこ)杜氏の聞き書き本が出た。「魂の酒」(ポプラ社刊。1650円税別)である。塩野米松氏が杜氏の話を聞いてまとめたものである。お酒でいうなら吟醸酒の味わいに仕上がっている。こういうふうに造るとうまい酒ができるという経験が語られている。呑み手である庵主の考え方と造り手の考え方とがそう離れていないことがわかるのである。それで安心した。間違った道には踏み込んでいなかったと。
この本はまた「菊姫」の先代の社長である柳辰雄氏の名言集としても読める。カギカッコの中に書き留められているその言葉には、庵主が物作りに期待する最低水準が間違っていないことを裏付けてくれるものがある。そういう信頼を寄せられる商品があるということがうれしいのである。商品なんてものは、所詮他人が使うものであり、粗であってもいっこうに作った人は困らない。用が足りればそれでも買うという人がいるからだ。ただ、物を作るというという矜持(きょうじ)だけが手にとって喜びを感じる商品を作り上げるのである。
「結局は自分の満足のいく酒だけは造らんと、わしの酒を待っとる人がいますからね」と農口杜氏もいう。酒に限らず、それが物作りなのである。
庵主はその矜持を感じる商品を手にしたときに物を買う喜びを感じるのである。そういう物を身の回りに置くことでいい物とめぐりあえたという充実感にみたされるのである。いい物が持っている気品が気持ちいい。あわてて安い物を買う必要はないのだ。
酒は、造り手の矜持がこもっていればその味わいの好き嫌いは別にしてうまいものなのである。
「わしは酒飲みではないから、そんなにたくさん飲んだことはないわけですね。ですから人の話をよく聞きます。柳さんも飲めない。飲めない二人が酒を造るんですから」と。
この蔵元にしてこの杜氏あり。そして庵主はそういうお酒を呑ませていただいていたということなのである。
そして、「喉を通して、飲んでこそ本当に消費者の感覚だと思うんです。」という。そうなのである。庵主は一度口にいれたお酒は勿体なくて吐き出すことができない。だからいわゆる利き酒というのができない。そんなことはしなくてもいいと思っている。うまい酒が呑みたいのである。からだがうまいと納得するお酒を呑みたいのである。呑み手である庵主はそんな利き酒のまねごとはしなくてもいいことなのだ。お酒ははちゃんと喉を通して味わう。それが正しい呑み方なのである。
もっとも、庵主は趣味で写真を撮っているのだが、ぜったい上手にはならないぞというアマチュアとしての誇りがあるから、プロフェショナル用と書かれたフイルムを見るたびに、買えばいい写真が撮れるというそのプロフェショナル用フィルムなるものを横目に見てはフィルム屋はアマチュアが心置きなく使える値段が安いアマチュア用フィルムを作れと毒づくタイプだから、本道を外しているのかもしれないが。

★燗酒のぬくもりにうっとり★15/12/3のお酒
「この酒、ぬる燗にしてください」と頼んだら、「うちでは大吟醸はそのまま召し上がっていただいております」とやんわり燗をつけるのを断られたことがある。はっきりいって慇懃無礼である。というより、うまい燗をつけられないのである。酒が吟醸酒になってからというもの、ただ冷やして呑ませておけばいいということになって、燗の技術が蔑(ないがし)ろにされてきたからである。瓶からグラスにそそぐだけというのとちがって手間がかかるということもある。
最近は焼酎がはやっていて、焼酎は日本酒に比べて管理に気をつかわないですむから扱いが楽だねといっている居酒屋も多い。日本酒をおいしく呑ませようとすると管理が大変なのである。
大吟醸のぬる燗をあっさり拒絶されたのだが、庵主がこの時分に庵で呑む燗酒は「あら玉」の改良信交の大吟醸のぬる燗であり、純米の「竹林」のふかまりである。あたためるとお酒の味わいがふくらんで、冷や(常温のこと)では感じられなかった隠れていた魅力が顔をみせてくれるので呑んでいて楽しくなる。滋味といっていいおいしさが口の中に広がって、からだ全体にそのぬくもりがしみてくるようなほっとする呑みごこちに心がくつろぐ。
「ああ、いま生きているな」という実感がわいてくる。大吟醸を呑みながら「贅沢をしているな」という恥じらいも感じる。そのはざまのくすぐったさがなんともいえないのである。
話は変わって、庵主が通う居酒屋である。
「燗酒! 」と頼んだら、阿吽(あうん)の呼吸で「お酒は何にしましょうか」などと野暮なことを聞かずに燗の用意をしてくれた。ややしばらく待ってやっとおまちかねの燗酒(ぬくもり)が登場した。小振りの筒状の丼にお湯をはって、徳利がその中につかって出てきた。まず一杯は美人の仲居さんが徳利とそろいの猪口についでくれた。いいねぇ。
味は、グーである。おっと失礼、おだやかなぬくもりの中にやわらかな酒質が舌にここちよいお酒である。アルコールがツーンと鼻をついて思わず顔をそむけたくなるような酒であるわけがない。舌にまろやかなぬくもりである。身があったかくなる。そして心がほんわかとあたたまる。
酒はうまけりゃいい。スペック(製品の仕様のこと)を聞いても意味がないし、酒銘を聞いても、再び出会うことはないだろうから無意味なのである。だから聞かない。この満足できる燗酒の優美なうまさの前にあってはそんなことはどうでもいいことなのである。
だまっていても満足できるお酒が出てくるというところに、庵主がまともな居酒屋によせる安心感がある。うまい酒はまっとうな居酒屋で呑むものである。
ちなみに、「お酒はおろちです」とは教えてくれたが、どこの酒だか、庵主は知る由もなかった。







