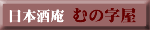
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成15年9月の日々一献
★贅沢のしかた★15/9/24のお酒
芝居がはねたあとで呑むお酒は、芝居のうまさに合わせた酒を呑みたい。
まずは「鳳凰金賞」(ほうおうきんしょう)である。播州山田錦 純米吟醸無濾過生酒。精米歩合50%。平成14酒年度醸造とある。限定酒とある。
香りが華やかな酒である。一杯目に呑むと、口の中にさわやかな気分が満ちあふれる。とはいえ、この酒を2杯呑めといわれたら庵主はためらわず断る。いま流行りの花酵母のような鼻につく香りではないが、香りが十分に出ているのである。だから最初の一杯として呑みたいお酒なのである。いうなれば高級酒前酒といったところである。
「万齢」(まんれい) 特別純米 中汲み 槽搾り 無調整を仕上げに呑む。庵主の適量は2杯である。酒は五勺とは言っているが、なあに頑張れば一合ぐらいの酒はなんとか呑めるのである。
精米歩合55%の特別純米である。純米酒がこれだけの味を出しているのを現に口にすると、アルコールを添加して呑みやすくしたのが本醸造ですといういいわけを聞くと、こと味に関していうならば白々しく聞こえるだけである。値段の点を考慮すると確かに本醸造の方が呑みやすいにはちがいない。
まともに造れば純米酒はアルコール添加の助けを借りなくてもうまい酒なのである。ちょうど未来劇場の芝居のように。

★目をみはる★15/9/17のお酒
発泡酒「味わい秋生」(ローソンで350ミリリットル缶145円税別)は紅葉を配したカラフルなパッケージである。赤い色にそそられて手にとりたくなるようにできている。
同じ冷蔵庫に並んでいた、ビールの「秋味」(ローソンで350ミリリットル缶198円税別)がその兄貴分である、と庵主は見て取ったのである。二つともパッケージの色使いが似ているのでてっきり同じメーカーの値段違い商品と思ってしまったのである。
が、「味わい本生」はサントリーで、「秋味」はキリンだった。
そっくりショーである。目をみはるほどによく似ている。はっきりいって紛らわしいのである。たまたま庵主が手に取った缶が安い方の発泡酒でよかったが、お金がないときに、うっかり高い方の缶ビールだったら「すいません、お金足りません」とえらい恥をかくところだった。
この二つ、おそらくサントリーのパッケージの方が後追いだと思われる。サントリーの缶ビールのデザイナーって創造性が要求されないのだから可哀相と庵主は同情してしまう。
うちの缶ビールのデザインは京都山崎の紅葉ですから、キリンのたった2葉の貧相な紅葉とは華やかさが一味違いますといったところなのだろうか。要するに広告のサントリーのデザインとしては芸がないと庵主は思うのである。いや、似ているけどちょっと違うというところが芸なのかもしれない。
山口さんも開高さんも、そんな体質に本当は苦労していたのだろうなと今は思うのである。お二人にも良心があったろうから。でもそれを感じさせないところに庵主はご両人に義の人を見る思いがするのである。一番おかしかったのは、山口瞳氏がサントリーが成人の日に決まって載せる広告に「若者よ、本物を大切にしよう」と書いた文案である。同氏の苦り切った表情が目に浮かんできて可笑しくてしょうがなかった。歳を重ねて、さすがの義人江分利満氏もとうとうさばけてしまったのである。
で、「味わい秋生」は充分うまい発泡酒なのである。はっきりいって、庵主の舌では「麦芽たっぷり1.3本分(当社比)」の「秋味」と区別がつかないほどにしっかりした味わいのビールなのである。サントリーの執念が、ついにビールに肩をならべた記念すべきビール(法律上は発泡酒であるが、その味はすでに)である。
目をみはるという言葉をこの味わいに贈りたい。庵主は今複雑な思いである。この手のうまい酒を造ってもいいのだろうかという、酒造りに対する基準がゆるぎかねない味に直面したからである。
いまはやりの発泡酒は、日本酒の普通酒や不当表示といってもいい本醸造と称する酒と同様に本来は代用酒なのである。そんなものを相手にするのは人間としての自尊心を捨てるようなものだと思っているのだが、そのことはまたこれまで日本人が培ってきた文化に逆行する時代錯誤の行為であると思っているのだが、こうして本物と違いがわからないほどに仕上げられると自分の目が信じられなくなるのである。
本物とほとんど変わらない偽札を造っては喜んでいる人を高く評価することができるかどうかということである。
わかった、わかった。あんたの腕前のすぐれていることはわかった。でもその腕をもっとまっとうなことに使った方がましなんじゃないかな、と庵主は思うのである。
ニセモノ作りが後ろ向きの技術であることがわかると代用酒造りのむなしさを庵主は感じてしまうのである。でも、本物とほとんど変わらないとなると、なんてったって本物より安いのだから思案はゆれるのである。
本物とほとんど変わらないものを一言の下にはねつけてしまうと、とんでもないことになるからである。名画とされている「モナリザ」はその多くが印刷という代用品(この場合は都合のいいことに複製品という言葉を使うことになっている。画商は商売がうまいのである。)によって人々に記憶されている。代用品はまちがっていると断定すると、私も含めて大方の人の頭の中にある名画の世界は間違ったものがいっぱい詰まっていることになる。そういう不純なものを文化として享受しているということになる。本物が全ての人にいきわたらないものなら、代用品で多くの人にその恩恵を満たした方が人々の役に立つからいいことなのではないかと考えられなくもないのである。
印刷された名画を代用品として拒否して名画を知らない人生と、ウソでもいいから名画の雰囲気を知っている人生はどちらがましかということである。
でも、金を出してむなしさを飲みたいとは庵主は、今は思わない。貧乏になって、先立つものに不自由するようになったときには、その思いは現実に則したものに変わっていくかもしれないが。

★「宗玄」にスター街道を見た★15/9/10のお酒
新人タレントが一気にスター街道をつっぱしる様をいくつか見てきた。最初はそこらへんにいるイモねえちゃんや芋あんちゃんにしか見えなかったタレントがあっという間に燦然と輝いて見えるようになるから不思議である。
少女はみるみるうちに美人になり(顔だけでなく、女の子は脚の線もきれいになる)、少年は男でありながら色気を漂わせるようになる。華を感じるようになるのである。その華が気持ちいい。
第一印象である。この子は売れるという直感が素人でも働くのである。ちょうど相撲好きな人がまだ新入りの力士の卵を見て、将来の出世を直感してひいきにするようなものである。これと見込んだ力士が予想通りに力をつけて上に昇っていくのを見るのは快い。出世力士を見つけたという矜持に一人顔がほころぶのである。(その能力だって天から授かったものであって、自分のせいではないのだけど、やっぱり自分のものであるかのように錯覚してうれしく思うものなのである。俺には人とはちがって物を見る目がある、と)。
さて、お酒である。
石川県珠洲市の「宗玄」を呑んでいて、このお酒はスター街道をつっぱしっていると感じたのである。坂口幸夫杜氏のお酒である。
「純米無濾過生原酒(55%)八反錦」、「同雄町」、「同山田錦」を呑み比べてみる。
米の違いが明瞭に出ている。どれもが庵主の口に合う味わいである。能登杜氏の造る酒ということもあるが、やっぱり杜氏の腕がたしかなのである。
酒も絵と同じ。作家の気合が作品に出てくるのである。作家の名前は知らなくても、絵に味を感じることがある。酒もだれが造ったか知らなくてもうまい酒はうまいのである。いいものを造ったからといってだれも得するものではないが、造り手の自尊心が手抜きを許さないのである。その姿勢をいま呑んでいる酒に感じて庵主は涙するのである。うまい、といううれし涙である。
もし、その気合の入ったお酒がなかったら、庵主は日本酒をこうして口にすることはなかっただろう。
せんだって、藤田嗣治の「アッツ島玉砕」を見たくなって、国立近代美術館に立ち寄ってみた。その絵は展示されていなかったので、ついでに収納作品の展示をざっと流し見したのだが、駒井哲郎の版画や香月泰男の絵はちらっと見ただけでも絵がひめている気合を強く感じて庵主の心を引きつけるのである。もう何十年も前に造られた作品なのにその生命力はいささかも衰えていないのである。すごい、と思う。
お酒を呑んでいても、それに似た気合を感じることがある。お酒はまた芸術品なのである。
庵主はそれを「宗玄」のブルーラベルという。青い文字で「宗玄」と書かれているラベルが貼られている青い一升瓶にはいった「宗玄」の純米吟醸無濾過生原酒(50%)のことである。これも魅力的な味わいである。
そして「壱」。特純吟「壱」生原酒である。これは1年寝かせた純米であるが、そのお酒の力のあること、まるで駒井哲郎や香月泰男の作品に感じるようなパワーを感じて呑んでいてワクワクしてくるのである。
「能」は純米大吟醸の斗瓶取りである。庵主はこのお酒には恨みがある(委細、別稿)。うますぎるのである。
そして「宗玄」の大吟醸である。斗瓶取りのこのお酒は一升で1万円という。値段にふさわしいお酒である。
庵主は最初の一杯である「純米吟醸八反錦」の酸味のまろやかさで十分に満足してしまった。値段も安いのである。庵主は必要以上にうまい酒はあえて呑まない。そういうお酒を美人の厚化粧と呼んでからかっている。
必要にして充分の味が庵主の好むお酒である。
「宗玄」はそういうお酒をきちんと造ってくれるのである。

★「サントリー」は酒の肴★15/9/7のお酒
つい最近のあるホームページ(いまはウェブページというのだったっけ)に出ていた話題。
『以下、引用。
サントリーのウイスキー瓶は色がついている。「サントリーオールド」などの瓶って黒いでしょ。あれは品質管理だといいつつも、実は年数がたつとウイスキーそのものの色が薄れるから瓶に色をつけているんだという話を財界担当記者より聞くがどうなんだろう。一方ニッカウイスキーの瓶には色がついていないという。これは色をつけなくとも中身の色が変わらないという自信の表れなんだとか。なんだかなぁ。
引用終わり。』
かわいそうに、あのサントリーはいつもからかいの対象なのである。災害用の保存食じゃあるまし、そんなものすぐ飲んでしまえばどっちだって変わらないじゃないか。ねぇ。その上、水で薄めて飲むのである。色なんか飲み手の好みでいくらでも薄くできるのである。どこどこ堂のお餅は長くおいておくとカビがはえる。一方、なになに堂のお餅は長くとっておいてもカビがつかない。といわれたって、カビが出ないほうがおっかないというものである。という援護射撃はウイスキーの場合あたらないか。じゃ、これはどうだ。ブラックニッカの瓶は真っ黒なんだけど。
で、どこでオールドを買っても同じ色であるようにとちょっと色合いを整えるためにカラメルを使ったりすると、蒸留酒から糖分が出たという笑い話になってしまうから、弱小の焼酎メーカーじゃあるまいし、サントリーがそんなえげつないことをするわけがないのである。と書いておこう。
みごとな広告でしっかりと酒の普及に貢献しているメーカーに対するやっかみである。あこがれの裏返しである。野球の選手ならだれでも巨人のユニホームを着たいように、だれもがサントリーのバッジを付けてみたいのである。ただ間違ってもサントリーからお呼びがかからないから拗ねてしまうのである。アンチ巨人ファンと同じようなものである。サントリーを愛しているのである。庵主などは「三鳥居ウィスキー社長の年頭挨拶」という笑い話などを作っちゃうほどある。
上司は悪口を言われるようになったら一人前。大企業は人に恨まれるようなったら一流の証。人の口にのぼるのはそれだけりっぱに(りっぱな、ではないのでご注意)仕事をしていることにほかならない。「サントリー」を口にできるということはそこそこの酒飲みになった証なのである。まっとうな酒とは何かということに目覚めたということだからである。
サントリーオールドを酒の肴にするというのは、とっくにその使命を終えた時代遅れの話題だと思っていたが、いまなおそれを口にする人がいるのである。悪いこと(酒税法のウイスキーの定義のことを言っているので)はできないものである。いや、いや「美名は人の噂も七十五日で忘れられていくが、悪名は百年にうち響く」といったところか。ひょっとすると、オールドを飲んだことがない若い人も酒飲みの教養としてその噂をいつまでも楽しむのではないだろうか。
季刊誌「サントリークウォーター」あたりが、「ウイスキーを楽しく飲むためのオールドの小話百選」みたいな特集を組むかもしれない。庵主も、ウイスキーを楽しんで飲むためになら、その小話の特集に、百は無理にしても二、三十ぐらいなら執筆に応じられそうである。
(余談。これが同様の「日本酒を楽しんで呑むための小話百選」なら、庵主は百個全部書けます。)
田舎から東京に出てきた人が、いっぱしの東京人を気取るためには二つの教養が必要であると庵主は教えられた。一つは西武資本の悪口を言えるようになること(もっとも悪口を教養というのもなんであるが)。そしてもう一つがサントリーを揶揄できるほどの酒の知識を身につけることである。
念のため、ここで言うサントリーとはその会社のことではなく、まがいものを認める酒税法の体質のことである。税収のために虚構を認めることがわが日本人の生き方にとって容認できる範囲なのかという価値観に及ぶ話題であるということである。たまたま文化的活動にも積極的なサントリーがその象徴として引用されているにすぎない。ただ、無闇に文化活動に金を使う企業というのは本業でなにかうしろめたいことをしているのじゃないかなと邪推してしまうところが庵主の性格の悪いところである。それにサントリーなら大会社だから酒飲みのいう悪口なんか相手にしないだろうという甘えにおいてである。お酒会社が酔っぱらいの悪口に茶々を入れると、じゃ酔っぱらう原因を作った酒を売っているのは誰だということになって、自業自得になってしまうからである。庵主はいま「味わい秋生」を飲みながらこれを書いているものだから。
素直な庵主は、疑うことなくその2点を実行したのである。西武の悪口(よいしょ本のこと)は本屋に行けばそういう本を並べたコーナーがあるからひたすら読みまくった(そういえば、中国人にだまされて倒産したヤオハンのヨイショ本はいまはどうなっているのだろう。みんなほっかむりしているようである。その手の無責任な本を並べているコーナーということである)。麗しい2兄弟の物語としてである。西武2兄弟の切磋琢磨は、東京人の良識に照らし合わせて、それほどに愛されているのである。知らなかった。
人は金持ちに生まれた御曹司が誠実に生きる姿を素直に認めたくないのだろう。おれはこんなに苦労しても、いまだもって税金を払わないですむ身分になれない。それなのにあいつらはなんだ。恵まれているではないか、というやっかみ半分である。世界の大金持ちの中に名を連ねているはずの堤義明さんの名前を恒例の高額納税者名簿に見ることがないところに、あこがれても到達することのできない堤さんの人徳を感じるからにほかならない。
西武は東京人にとってはあこがれのスターなのである。そのクールな様が自分の欠点を見るようなものだから可愛いくてたまらないのである。大阪人が、今年はともかくふだんは常敗の阪神をくそみそに貶しているようなものである。好きなのである、阪神というどうしょうもない球団が。この程度ならおれと同じぐらいだと親しみを感じるからである。
落語の世界ではあいつの噺は俺と同じぐらいだ思ったときは、相手のほうがずっとうまいというのが定説である。西武も阪神もそれと同じような錯覚をいだかせるのである。そこが人気の秘密である。
サントリーの方はというと、いろいろサントリー本を読んでいるうちに、庵主はうまい日本酒があることを知ることとなった。そういう意味で、うまい日本酒にめぐり会いたくなったら、サントリーの本を読みなさいと庵主は勧めるのである。これは冗談ではない。酒税法の仕組みがわかるからである。酒を造るということがどういうことであるかを、サントリー本を読むことでじっくり勉強できるからである。
酒がうまいかまずいかは広告ではなく自分の舌に聞けであり、酒の善し悪しは酒に込められている気合にあるということである。そしてある程度以上の量の酒を造るとその気合を維持することができなくなるということを経験的事実として知ることになるのである。
人は騙せても、舌はだませない。

★「菊源氏」大吟醸金賞受賞酒★15/9/3のお酒
静岡に「菊源氏」という酒がある。いや、あった。つい最近造りをやめてしまったのである。
蔵元は旭化成株式会社である。社名を見ると、庵主はなんとなく合成酒を作っているような感じを覚えるが、しかしその大仁酒類工場で造っている「菊源氏」は本物のお酒である。小室恵一杜氏が造っている。いや、造っていた。去年までのことである。最後の造りを終えてしばらくして亡くなったのである。
虎は死んでも名を残すというが、杜氏は亡くなってもその酒は残るのである。ただし全部呑まれてしまったら、もうその酒はこの世にはなくなってしまう。しかしそのお酒を呑んだ人の心の中にはいつまでも残るのである。やがてその呑み手もいなくなって、そのお酒は文献の中にだけ歴史として残るのである。
流通在庫を追いかけて「菊源氏」の大吟醸を手に入れた。この酒はいうなれば遺作である。いまはなき酒を偲ぶ会みたいなものである。庵主が初めて口にした「菊源氏」は戒名が長い。「独立行政法人酒類総合研究所主催平成十五年全国新酒鑑評会金賞受賞酒」である。
鑑評会の受賞酒である。栓をあけたときにえもいわれぬいい香りがたちこめる。呑むとあまい。庵主の好みである。とはいっても鑑評会のお酒である、やっぱり線が細い味わいなのである。品がいいといってもいい。きれいな味わいの酒なのである。女の子なら匂いやさしいあでやかな美人なのである。それを好むもよし、君子危うきに近寄らずでもよし。
と思いながらも、グラスにいれた「菊源氏」はすうーと体にはいっていく。また一杯。そしてさらにもう一杯。
庵主、久しぶりにお酒を呑み過ぎてしまった。
ところで、「利休梅」の流通在庫はまだあるのだろうか。







