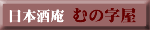
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成15年1月の日々一献
★バニラアイスの泡盛まみれ★15/1/23のお酒
庵主は食い物屋に行ったときにはまずデザートから決めるのが通例である。
東京で数多くの泡盛を揃えているその店では「バニラアイスの泡盛まみれ」を味わうことにした。仕上げにちょっと甘いものが用意されていない店はこころもとないが、この店なら呑んだという満足感にひたることができる。
なお、バニラアイスには泡盛もいいが、南部美人のオールコージをかけるのもうまい。
まず、「瑞泉」の30度を呑む。これが庵主の泡盛の基準酒である。キレよし。ヌケよし。ただし、庵主ははっきりいって泡盛のカオリがまだなじめない。日本酒の「うまさ」が心にしみてくるうまさだとすると、泡盛・焼酎のうまさというのは庵主の体ではまだまだ観念的な「うまさ」なのである。からだがうまいと納得するうまさではなく、頭の中だけで納得しているうまさなのである。だからうまい日本酒とうまい泡盛があったら庵主はためらわず日本酒をとる。
次に呑んだのは「千年の響」43度。樽貯蔵で10年。予想通りウイスキー風である。これはこれでおもしろいが、ウイスキーみたいな泡盛なら、最初からモルトウイスキーを呑めばいいのであって泡盛の意味がないねとカウンターのお兄さんと意見が一致する。そういう泡盛もちゃんと置いてある店である。ついでに本醸造の「黎明」もあるのだ。マニアックな酒の揃え方をしているお店であることがわかるだろう。
そして最後に「泡波」である。30度。基準酒である「瑞泉」と比べると霧がかかったような味わい。写真でいえば紗(しゃ)がかかった感じである。「微妙に塩分を含んだ波照間の水が生み出した独特のあじわい」とカタログ本には書かれている。泡盛にポカリスウェットをほんのちょっぴりいれた感じの味である。
その店は、泡盛の味をひきたてる料理をこころがけているといっていたが、たしかに料理がうまい。庵主にとってはクセのある味である泡盛がスイスイとおいしく呑めてしまうのだから、呑んで食べれる重宝な店である。東京の酒事情は本当に極楽である。

★酒は純米、燗ならなお良し★15/1/18のお酒
庵主が日本酒を飲み始めたときには、坂口謹一郎先生はすでになく、その名前を知ったときには山田正一先生はあい前後して亡くなり、一日本酒ファンとしてはいまやただ一人「先生」と呼べる人である上原浩先生の「純米酒を極める」(光文社新書・税別750円)が出た。
庵主はいま、たとえば山田錦を使ったお酒は文句なくいいお酒であるとか、お米を究極まで磨いたお酒は心をこめて造られたうまいお酒だ、とかの日本酒の宣伝文句をとりあげて「必ずしもそうとはいえないよ」という内容の「日本酒の嘘」という本を執筆中なのだが、この本を読んだら庵主のいいたいことがほとんど網羅されているのである。
山田錦にもピンからキリまであるとか、米は磨けば酒がうまくなるというものではないとか、柱焼酎=アル添というのは詭弁であるとか、呑む立場にある庵主が思っていることが造りの専門家も同じように思っていることを知って意を強くしたのである。
この本が出たらもう庵主の「日本酒の嘘」は必要がないのだが、ここは上原先生に左袒して呑み手も賛意を示しているぞと書き続けたいと思っている。
この本が指摘しているいくつかの、いやいくつもの問題点は重鎮の上原先生にしてはじめて書けることなのである。業界の関係者は本当の事を書くとさしさわりが多いから、わかっていてもはっきり書くことができなかったのである。
日本酒という呼び方は純米酒だけに限定せよという主張は庵主がすでに述べた考えと同じなので心強い。アルコールを添加した酒は大吟醸、吟醸酒であっても清酒とするべきだろうという。庵主は清酒を甲級と乙級に分けて、大吟醸・吟醸を「甲級清酒」とすれば耳で聞いたぶんには高級な酒というイメージは確保できるのではないかと冗談で書いたことがある。
日本酒の輸出の可能性については庵主は異存があるものの、この本の中に書かれている「風変わりな新型酵母が続々と開発されている」とか、「日本酒というのは、秋の完成を目指してつくるのが本当だ」とか、「生酒など製品以前の半製品である」とか、「問題なのは、お金を出してでも飲みたいと思う酒が少ないことだ」と今の日本酒の問題点をつぎつぎにまな板にのせていく筆の運びは痛快である。版元が集英社なら、書名は「痛快日本酒学」となっていたにちがいない。そして、「酒は純米、燗ならなお良し」とうまい酒を呑む喜びを心に描かせてくれる。ロマンだなぁ。
これらはまだ本文がはじまる前の「まえがき」に出てくる指摘なのである。本文にはいるとその指摘はさらに透徹したものが続々と出てくるから読んでいてワクワクすること請け合いである。
「消費者の日本酒離れは深刻であり、生産者の大半は赤字経営に陥っている。しかし、私なりのより正確な言い方をするならば、売れなくなっているのは日本酒ではない。清酒である。」といった指摘から日本酒のこれからの方向を認識することができる。
ここでいう日本酒とは「純米酒のことである」。清酒とは「醸造用アルコールを添加した酒は日本酒と呼ぶべきではない。あくまでも清酒だ」との定義による。
「酒造家は、本気で需要を拡大させていこうと思うなら、ただ飲まれるだけではなく、飲みつづけられる酒をつくらなければならない。」と今後の進む道まで書いてある。
「日本酒においては無理な値下げ競争などすべきではない。そんなことは清酒にやらせておけばいい。……純米酒はそんなに安くできるものではない。良い酒をつくって適正な値段で売る。それでいい。」と心構えまで諭してくれるのである。
本もお酒とおんなじで、中身がしっかりしているものは読んでいておいしいのである。美酒の味わいに似た本である。
こういう本を読むとまたお酒を、燗酒を呑みたくなるからいけない。ただ、うまい燗酒というのがほんとうに少ないというのが庵主の実感なのである。

★最初が肝心★15/1/13のお酒
サントリーは成人の日になると決まって「さあ二十才だ、どんどんお酒を飲もう」と、何も知らない若者を悪の道へ誘(いざな)う広告を打つ。サントリーは、広告は、一番上手な会社なので、業界を代表して次代を担う(にな)若い世代に、姑の嫁いびりのように、古参兵の新兵いじめのように先代から受け継いだ毒習に若い者(もん)を誘い込むのである。俺がやられたのだからお前らにも味わせてやる、という無批判な陋習(ろうしゅう)の押しつけである。いわば若者に対する大人からの宣戦布告なのである。まともな武器も持っていないあわれな二十才のために助言を書かねばなるまい。
酒、焼酎、麦酒という悪の枢軸酒にだまされてはいけない。またワインだのウイスキーだのカタカナ酒に日本人の魂を売ってはいけない。あの人たちは金儲けのために二十才の人たちを甘い言葉を使って食い物にしようとしているのだから。
でも大人には後生をからかうことでしか溜飲をさげることができない人が多いから、そういう振る舞いが大人の基準だと思い込んでしまうととんでもない回り道をすることになるのだ。
庵主はいつも酔っぱらっては思うのである。酔って無駄に流れた空白の時間というのは、いうなれば自殺してそれ以後の時間を空白にしてしまうことと同じではないかと反省することしきりなのであるが、よく考えてみれば近代資本主義社会はひたすら効率を追求してお金を儲けることが目的みたいで、その手の考え方をビジネスというのだけれど、その合理性とやらを追求していくと究極は人間がいないのが一番合理的ということに行き着くという絶対矛盾の時代に生きているのである。世にないほうが合理的な自分の存在というのを認めることができるわけがない。人間(自分のこと)の幸福よりひたすら合理的な経済活動が望ましい、なんてそんな冷たい考え方に付いて行けますか。人間はなんといっても己(おのれ)が一番大切なのである。無駄がなくては生きていけないのである。
そんな中で酒を呑むということは、合理性とか効率とやらの狂気の思想に合法的に反旗を翻(ひるがえ)す行為なのである。相手の武器(きはん)で、相手の攻撃を躱(かわ)す行為なのである。でも。
躱しきれないでしょうね。
サントリーの成人の日広告はこれまでなら山口瞳とか伊集院静などの手練(てだれ)の文筆家の技で若者にお酒は人生の味わいを深めるためにはなくてはならないものだとばかりに言葉巧みに(たぶら)かすというのがお家芸だったのだが、今年は広告文案家の手によるものである。最近は、禁煙といい、禁酒といい、反対勢力が力をつけてきたから、アルハラという言葉が使われるようになった時代にお酒を飲みましょうなどという文章を書いたら身が危ないということに利口な文筆家は気づいて怖(おじ)けづいたにちがいない。だから金さえ出せば文章をひねりあげる広告文案家の出番とあいなったのである。
その広告文案は「最初が肝心」と締めくくってある。肝心を文字通り読んではいけない。その忠告は広告文案家の一片の良心の吐露なのである。大切、と読んではいけない。酒を無闇に嗜(たしな)むことは「肝心」、すなわち、「肝臓が心配ですよ」という意味なのである。それは、あけおめ(あけましておめでとう)とか、おつかん(お疲れさま、乾杯)といったサントリーのグレコト語である。
そして、最初に出会う酒がいいお酒であっておいしく呑めればいいのだが、そうはいかない。庵主もそうであったように、酒との最初の出会いはどうでもいい酒であることがほとんどなので、本当にうまい酒を知るまでに相当の年月を要するのである。うまい酒があるということを知るまでに、そして本物のうまい酒に出会って口にするまでに。
というのも、いい物というのはそうたくさん作れるものではないだけに、何も知らない人が最初からいい酒に出会うことはまず無理といっていいからである。
たとえば一流品といわれている商品がいい物なのかというと、広告して売られている一流品などは「一流品」というブランド(商標)の高価が取り柄の大衆向け商品なのである。本当にいい物というのは広告するだけの数量が作れないものなのである。知っている人だけが手にすることができるものなのだ。うまい酒も同様に本数が限られているから広告されることなく流通しているのである。だからどこにいい酒があるのか最初は分からないというのが普通なのである。
いい日本酒と高値が売りの「一流品」との違いは、日本酒は物がいいのに値段が適正であるというところにある。味にそぐわないおかしな値段をつけて出すと蔵元の見識を馬鹿にするだけの判断力を日本酒の呑み手はしっかり弁(わきま)えているからである。だから日本酒の世界は大人の世界なのである。「一流品」の買い手にはそういう知性は必要ない。見栄を買っているからである。したがってそれは安くてはいけないのである。両者は求める価値観が違うからである。人種がちがうのである。よしあしでなく違いである。一方は自分の内側に価値を求め、片方は自分の外側に値段をみせびらかすことで自分の存在価値を支えようとするものである。その人にとってどちらの方が己の存在を確かめることができるかという生きかたの違いだけなのである。
ときにはまずい酒を飲まなければならない場を避けられないとは思うが、お口直しのうまいお酒があるということに希望をもってほしい。
そのようなうまい酒はどこにあるのか。まずはこの「むの字屋」に通うことである。うまい酒への近道がここにある。
と、読み返してみると、あのサントリーより質(たち)の悪い広告になってしまった。で、甘い言葉の文章にだまされないということも大人の基準なのである。

★ビールで乾杯★15/1/11のお酒
ビールの味を知ってしまったのである。それまではビールなどはキリンでもサッポロでもアサヒでもサントリーでもどれも似たようなものだと思っていた。
それもそうなのである。ピルスナータイプの同じビールなのだから。それさえ知らなかったのである。日本酒は普通酒の味しかないと思っているようなものである。ビールもまたその手の味しか知らなかったのである。呑めないことはないが、ちっともおいしくない酒であるということが共通点である。
庵主にも飲めるビールがあることを知ったのは、地ビールの先駆者の一人であるマイケル・トシさんに出会ってからである。
茨城で「菊盛」を醸している木内酒造のBOP醸造でビール作りの手伝いをしてからビールの香りのよさに気づいたのである。ビールの多彩な色合いとホップの香りに酔いしれてしまった。要するにビールの色香に迷ってしまったのである。
沼津にベアードビールという小さな地ビールの醸造所がある。ほんとうに小さい。そこでブライアンさんが造るビールがうまいのである。ビールに華がある。飲んでいて楽しいのである。
小さな醸造所に併設されているレストラン「フィッシュマーケット・タップルーム」にビールが好きな仲間が集まってブライアンさんが作ったビールを飲んできた。
そこで飲んだ「ウィートワイン」の香りのよさと味のうまさは大手メーカーのビールでは絶対に味わえない絶品である。
ことしも年頭から衝撃的にうまい味のビールに出会えた。ビールで乾杯! という気分である。心がウキウキしちゃうのである。

★司牡丹船中八策特別純米原酒生詰★15/1/8のお酒
池袋演芸場の初席8日の夜の部はお客が十二人である。ツ離れはしているが、ただでも客席が少ないのにその小さい客席が大きく感じられる。噺家のくすぐりではないが、まさに寄席に通うという客はエリートなのである。
寿輔の話にしこたま笑わせてもらった。客が多いときなら他の客の笑いにまぎれてなに憚ることなく思いっきり笑うことができるのだが、なんせ客が十二人なのである。他の十一人の爆笑をさらにしのぐような大笑いをするというのはなんとなく気恥ずかしい。目立つから、そうなると高座から当方を重点的に攻めてくるということもありうるのだ。これ以上笑いの爆弾をおとされたのではたまらない。それで可笑しさをこらえながら笑っているものだから、余計その可笑しさが爆発するのである。お腹の皮がよじれるような可笑しさにたえていた。寿輔の着物はいつも素敵である。
トリは夢楽だった。小天華が代演でその手品が見られなかったのは残念。
寄席がはねてから寄った店にはひやおろしが五本並んでいた。
「一ノ蔵 純米生詰 +2」、
「司牡丹 船中八策 特別純米原酒生詰 +8」、
「日置桜 特別純米生詰 +5」、
「風の一輪 純米吟醸生詰 +2」、
「くどき上手 純米大吟醸生詰 +1」である。
こういうようにお酒を並べてもらうと酒を選ぶ楽しみがある。呑まなくてもいい酒を消していく消去法でなく、全部呑みたい中からどれを選ぼうかといううれしい選択だらである。この酒祭りを見ているだけで庵主は呑まなくても満足してしまうのである。あれこれその味わいを想像できるお酒の揃えだからである。酒銘と造りが書いてあるのでそのお酒の味わいを想像することで十分楽しめるからである。
どうやら庵主は舌で酒を呑んでいるというよりも、その能書きで呑んでいるようなのである。酒は、呑むと酔いがまわってくるからニガ手なのである。酒は酔えるから楽しいんだと会長(初出。委細省略)はいうのであるが。
庵主が選んだお酒は、とある事情があって「司牡丹」である。民芸風の手作りのグラスに正一合の酒が入って出てきた。手作りのグラスといってもグラスの厚みは薄く作られているからお酒の味をそこねることはない。
酒のにおいをかいでみる。硬い。あきらかに日本酒度がかなりプラスに傾いているにおいである。以前、「船中八策」を燗にしてもらったら、キレのよさがあってさっぱりした酒だったという記憶がよみがえってきた。案外豪気な酒だったのだ。
口にすると予想どおりの味わいである。酒祭りを見たら+8とあった。その味わいの由来は酸味にあるのだろう。この酸味を好む人にはこの酒の味わいは絶品である。しかし庵主の舌にはつれない味としか感じないのである。もちろん格調のあるいい酒である。好き嫌いは別にして深い味わいをたたえている酒である。ただこの味わいの酒は庵主の好みではないということを確認したものである。そしてまた一合の酒が呑みきれないという自分の体質も変わっていないということも。今年もまたおいしいお酒を五勺だけである。

★初詣の甘酒★15/1/6のお酒
庵主が住んでいる地の神社さんは市谷亀岡八幡宮である。その威徳にすがって神殿の一つ柵を隔てた隣地には予備校の校舎が建っている。ご利益がある神社なのである。
小さな神社であるが、お正月のきれいに清められた境内にはすがすがしい気がただよっている。凜とした緊張感につつまれていてここちよい。
茅の輪(ちのわ)が設(しつら)えられている。物知りな人がいて、茅の輪を二度、三度とくぐっている。一度くぐって、すぐ左に回って、またくぐって、今度は右に回ってまたくぐり、それで終わりかと思ったら、もういちど左にまわってくぐっている。それからお賽銭箱、いや拝殿に向かうのである。
知らないことは前例にしたがうのが無難である。なにかいいことでも起きるのかと思って、そのとおりにまねしてくぐってみた。
庵主のお賽銭はいつもどこでもご縁玉一つである。だからつねにご縁玉を持ち歩いている。初詣でもそれはかわらない。
お参りには請求書的お参りと領収書的お参りとがあるいう。
請求書的お参りとは「おいしいお酒を呑ませてください」というような、神様にお願いごとをするお参りである。
領収書的お参りとは「いつもおいしいお酒を呑ませていただきありがとうございます」というような感謝の祈りである。
請求書的お参りをする人は、物の売り買いと勘違いしてたくさんお賽銭を出すと願いがかなうと思っているようである。神様と取引(ビジネス)しているのである。いっぱいお賽銭を出しても儲かるのは神主さんだけである。多額のお賽銭はそれはそれで役に立っているから笑うことはない。ただ神様はきっとそのほほえましさを笑っていることだろう。初笑いをありがとう、と。
庵主のお参りはもちろん後者である。物知り人のお賽銭がいくらだったかは見えなかった。
初春の境内では甘酒が振る舞われる。お賽銭の多寡にかかわらず小振りの神コップに入れた甘酒をすすめてくれる。
この甘酒がありがたい。ぬくもりがうまい。
庵主はちょっとだけだがお酒が呑めるのがありがたい。おいしいお酒が秘めている氣(き)を口にして元気をもらうことができるからである。お酒のぬくもりがおいしいのである。
お酒が呑めないという人がいる。アルコールを受けつけない体質なのである。そういう人はお酒を呑むことはない。お酒が出てくる場では、いちおうお酒を盃にいれて、形だけ口をつければいいのである。呑むことはない。お酒を呑むということは、「盃の上をわたっていく風を味わうことなのである」。その香気にふれて神を感じることなのである。それを呑んでしまうというのは意地きたない人なのである。さわやかな美味しい風にふれて、その酒を呑んだらもっとうまいに違いないとつい欲を追って道を踏み外してしまったおろかな人なのである。お酒を呑めない人はその香気につつまれるだけで呑まずに幸せだけを手にすることができる恵まれた人なのである。
庵主は境内で甘酒を口にして、つい、きりりと冷えているお酒を呑みたくなってしまったのである。
�








