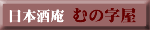
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成14年10月の日々一献
★神無月卅一日★14/10/31のお酒
大塚の酒亭『こなから』のおしながきには神無月卅一日と書かれた紙が貼られている。薄手の板で作られている表紙に貼り付けられている紙は、明日はきれいに剥がされて霜月朔日という新しい紙と取り替えられるのだろう。
ぶらりと覗いてみたら珍しくカウンターに席が空いていた。ここにきて急に肌寒くなってきた十月の最後の日のことである。庵主にとっては初めての『こなから』である。
さすがに酒の揃えが粋である。
「早瀬浦」吟醸
「早瀬浦」純吟
「くどき上手」八反錦44%(この一升瓶が実は今庵主の手元にもある。とある不純な動機から購入した久しぶりの一升瓶なのである。それがまたうまい酒なものだから日々残量がみるみる減っていくのである。本件詳細は後日掲載)
「東洋美人」
「歓びの泉」
「磯自慢」本醸造
「美丈夫 夢許」大吟醸
「義侠」
「開運」
「土佐しらぎく」吟醸
「伯楽星」
「初亀」
など二十種類の酒が酒祭りに掲げられている。静岡の酒が三つというのがうれしい。どれも呑まずにはおけない酒銘の中から今日はどれを呑もうかと思いを巡らすとそれだけでも十分にお酒を楽しむことができるほどである。酒の揃えのおもしろさがそこにある。
で、庵主はその二十種類の酒銘を一生懸命覚えて来たつもりだったが、いまとなってはこれだけしか思い出せない。造りの違いまでは覚えていない酒もある。というのもこの魅力的な酒祭りに幻惑されて、つい酒量を越えて三杯も呑んでしまったからである。さわやかな酔いとともに記憶がすみやかに淡くなっていく。久しぶりに酒を呑んで肩にきた。庵主は呑みすぎると肩が凝る質なのである。
『こなから』の酒祭りには、酒銘にはちゃんとふりがなが振られている。
山田錦を「やまだきん」と読んでいる人がいたという話を聞いたことがある。酒好きが聞くとそれは笑い話であるが、その世界に馴染みがない人には正しく読めない言葉というのが少なくない。「正法眼蔵」って読めますか。知っている人には無意識に読める漢字がそうでない人には意外と読めないのである。
酒の名前でも「醴泉」とか「獺祭」などは、多少漢字には強いと思っている人でも読めないものである。だから『こなから』の姿勢は正しい。
ちなみに庵主は「亀泉」と「能古見」が読めない。きせんか、かめいずみなのか、また、のこみでいいのか、のごみと濁るのかがわからない。ふりがなが振ってあれば安心して頼めるのであるが、この酒は酒銘を名指して注文することができない。
「あのお酒を頂戴」であり「その繁桝の隣にある酒ください」となるのである。
カウンターの隣の席に座っていた若いOL風の二人連れがそばがきを食べ終えて帰るのと入れ替わりに二人連れのご婦人が入って来た。「義侠」を何杯か重ねていた。おみごと。お酒を知っているのである。楽しんでいるのがわかる呑み方である。ほんとうにおいしそうにお酒を呑んでいる。
庵主がそばがきに付いてきた薬味の山葵をなめるようにしてその甘さを味わっていたら、「わさびっておいしいですよね」と声がかかった。そうなのである。山葵はツーンとくる前にほんのり甘い味わいがあってその甘美な一瞬がなんともいえないのである。ツーンときたら酒を含んで包み込んでしまう。庵主は同じ味を知る人がいると知って思わずご婦人たちと顔を見合わせて微笑んでしまった。

★珠玉のビール★14/10/29のお酒
かなり酔いが回っていたのである。しかしそのビールのうまさははっきり覚えている。というのもそれまでのほろ酔いを一瞬にさますような画然としたうまさに圧倒されてしまったからである。これはビールではない、とその味わいの妙味に魅せられてしまったのである。一度飲んだだけではその味わいの深さをはかりしれない魔性のビールである。飲むほどにますますひきこまれていく妖婉なビールである。
博石館(はくせきかん)ビールの2年眠らせて熟成させたというバーレイワインである。スーパービンテージである。ギネスビールのような真っ黒い色をしたビールであるが、その味わいにはなんともいえない品のよさが感じられる。
人品に、庵主のような自称中流階層しかしてその実態は細民に近い位置にいるという境遇にある大衆の生活感情とは一線を画して明確にその違いが見て取れる美しい立ち居振る舞いの憧れとしかいえない優雅な品性があるように、品のよさは一朝一夕には身につかないものだけにそれを目にしたときの気持ちのよさと己の育ちではあのようにはなれないという諦めからくる素直な羨望に包まれた美しいものを見ることは快感にほかならないのである。それは心ときめく快感である。
その快感に魅せられたのである。その一杯を口にするまでにうまいビールを何杯か飲んでいたから庵主は十分に酔っていた。にもかかわらず、そのビールを飲んだときのうまさは庵主が知っているビールを越えたものだった。
たしかにビールだ。がしかし、これはビールの味ではない。庵主がこれまで飲んだことのあるビールの範疇を越えている。想像を越えたビールなのである。
甘い飲み物を「甘露」という。たえなる味わいを「醍醐味」という。このビールはいうならば「珠玉(たま)」のような美しさなのである。
ビールというと、夏場のビールメーカーの広告のようにジョッキかグラスでぐびぐびと飲むのがおいしいかというと、すべてのビールがそういう飲み方でうまいというものではない。じっくり味わいながら飲めるビールがいくらでもあるのだ。
これまでの日本のビールは水がわりに飲んでもおいしいビールしか造って来なかったのである。それがビールのすべてだと思わされていただけのことなのだ。知らなかっただけなのである。もっと言えば、それしかないものだと今までは騙されつづけてきたといっても過言ではない。その騙されていた範囲からはみ出したところにある真実に出会ったときに、世の中にはほんとうに美味い酒があることを知るのである。真実に触れることの滋味を味わうのである。
日常の生活の中で何かおかしいとか、なんとなく食い物がおいしくないというときには、嘘を聞かされ、嘘をたべさせられていることを疑うといい。真実のうまさをあじわうと心が納得する、からだが喜ぶのである。今の日本がなんとなくおかしいと感じるのも建前としての嘘がまかり通っているからである。だからなぜかすっきりしないのである。頭の中がすっきりしないものだから、からだまでなんとなくおかしくなってしまう。本屋に行けばそれなりの真実を書いた本が並んでいる。そういう本を読みながらいい酒を呑むときの酒のおいしいこと。得心がいくことで心のもやもやがすっきりするのである。人間には本物を見たときに快感を感じる感性が備わっているようである。真実の書(ふみ)を肴にして呑む酒はうまい。
大手のビール会社が造ってきたこれまでの日本のビールに関していうならば、万人向けのだれが飲んでもそれなりにうまい味を作り上げてきたのだからそれはそれですごいことである。
しかし時代は変わった。もっとうまいビールが飲みたいという需要が発生したのである。いわゆる地ビール(これ、もっといい言葉にならないのかな。地酒じゃありまいしネーミングがよくない)の醸造所が認められるようになってから日本のビールは夜明けを迎えたのである。
どこで飲んでも同じ味わいのこれまでのビールを共産主義ビールというのなら、やっとビールの味の選択ができる資本主義ビールの時代になったということである。共産主義が人間を駄目にするための壮大な実験であったことがわかる。ビールを飲んでいると見えてくるのである。
ビールの種類が一つしかなかったとしても生きていく分にはいっこうに差しつかえない。それで十分ビールなのだから。種類が増えると今時の事務用電話機のように機種ごとに微妙に使い方が異なることから却って使いにくいということさえ起こりうる。携帯電話機にいたってはよくもまあこんなに次から次に下品なデザインを思いつくものだと感心するほどの盛況である。種類が多くなるとろくでもないものが氾濫するというのが現実である。
とはいえ、酒は飲めばなくなってしまう一時(ひととき)の快楽品だから、いろいろ種類があったほうが浮気な庵主としてはうれしいのである。こと食い物、飲み物に関しては毎日同じ物を口にすると飽きてしまうという人間性から種類はたくさんあった方が精神的にも正しいのである。また偏食が体によくないことはよく知られているところである。
そして話は博石館の珠玉のビールに戻るが、サワーグラスに注がれたそのビールの気品のある味わいに庵主はすっかり魅了されてしまったのである。
庵主がこれまで知らなかった世界を覗いた思いがした。

★仄聞(そくぶん)★14/10/26のお酒
ふだんは呑むことがないが気になるのが新潟の酒。あまりにも綺麗すぎて呑んでも心にかかるものがない酒が多いというのが庵主の印象である。
よくタバコにある1mg(これって何が1mgなんだろうか。タバコ喫みに対する愛情がわずか1mgといったところか) みたいに吸っているのだか吸っていないのだかわからない頼りない煙のような味気なさを庵主は新潟の酒と聞くと思い浮かべるのである。
酒量のない庵主は、最初に口に合わない酒を呑んだときに、では次のもう一杯はあらためてうまい酒を呑もうということができない質(たち)なので、いつも最初の一杯が勝負なのである。 そういうわけで新潟の酒を呑むことはほとんどない。
その新潟の酒にうまいのがあるということをほの聞いた。
新潟の酒は淡麗辛口だと思われているが、すべてがそうなのではない。地元に行って呑んだら、けっこう濃醇な酒が呑まれているという。
「君の井」がそういった酒だったという。庵主はまだ「君の井」を呑んだことがない。
さらに「越の華」に四合瓶 4,000円の酒があるという。これは味がしっかり厚みがあってうまいという。しかもその上に 7,000円の酒があって、これが圧倒的にうまかったという。金賞受賞酒をそのまま詰めたものらしい。一升瓶に換算すると14,000円前後の酒ということになる。たしかに相当な値段だがそれだけの価値はあると呑んだ人が悦楽の表情を浮かべていた。
こういう体験談が聞けるから居酒屋はまた呑み手の学校でもあるのだ。学校とは情報を交換する場、体験を共有する場である。

★物は言いよう★14/10/22のお酒
以前、読売新聞のうさんくさい記事について、そのいいかげんさに困惑して軽口をたたいたことがある。酒に関する一つの事件について全国紙の読売新聞と地元紙の南日本新聞が載せた記事の内容が正反対だったのである。読者はどっちを信じたらいいのか判断できない。全国紙の信用度に賭けるか、やっぱり地元紙の密着度を信頼するかである。しかし一つだけ判断はできるのである。新聞の記事などはあてにならないものだということだけは。ニュース商品とはそういうものである。
雑多の中から何が起こっているかの事実を拾わなくてはならない。その手間と暇が面倒なのである。費用が大変なのである。だから貧乏人にはいい情報が手に入らないということになっている。
その点、貧乏人でも最初からいい物が手に入るのはしっかりした酒亭がいくつもある日本酒である。その店を訪れれば最高級の日本酒に接することができる。しかも酒には嘘がない。呑めばよしあしがすぐわかるのだから。そのお店に信用があるのである。
新聞も講読料はもっともっと高くてもいいから質のいいニュースが読めるものがあればいいのだけれどその願いは叶わないようだ。いい店がない。もっともそこまでやったら新聞社としては採算が合わないことはわかっているからこの注文はイヤミである。
ニュースの信憑性については宗教にもそれをいったキャッチフレーズがあった。「信じる者は騙される」と。もっとも騙されるの部分は救われると言い換えられているのだが。そう、宗教も一つの商品である以上、きれいな言葉でその商品を包むことは当然のことなのである。だれだって汚い包装紙に包まれた商品なんか欲しがらないからである。
さて、その新聞記事は焼酎の製造に関する不正(というより笑って見逃せるささいな出来事)を糾弾するものだった。あれは、思えば、読売新聞の、食品の不正表示に対してはどんな小さなことでも断固として許さないという意志表示なのである。だから事が起こってから数か月もたっている事件であるにもかかわらず一面を使って堂々と報道したのである。いうなれば国民の食い物の安全と健康を護ろうとする男気の表明である。えらい。
読売新聞はこと飲食物に関してはどうでもいい些細なことでも不正表示は許さないぞという強い意志表明なのである。主義主張の表明だったのである。
その心意気やよし、である。力強いペンの味方を得て、今時なにを食わされているのかわからないで健康を損ねている国民(これ庵主のこと)にとってこれほど頼もしいことはない。
このように書くと読売新聞のあの新聞記事の真意が正しく伝わるというものである。
そういえば、何年も前から言われているアメリカから輸入されているレモンに防腐剤としてとんでもない毒薬が使われているという話はその後大丈夫になったのだろうか。輸入物の果実は何が使われているわからないので恐ろしくて庵主は食べる気がしないけど。
そのうち、読売新聞は国民の健康のために飲酒を控えようというまっとうなキャンペーンを始めてくれるような気がする。
もっとも本日の読売新聞には堂々2面見開きの「立山」の広告が載っていたから、当分はその心配はないようである。新聞あっての広告ではなく、広告あっての新聞なのだから。
読者は広告様のおかげでありがたくも世間で日々起こっている一定の「真実」(この程度のウソを教えておけばいいだろう)と特定の「正義の実現」(この見方以外の方向を見てもらっては困るよ)を読ませてもらっているのだから。
ただほどこわいものはない、というのもよくいわれていることであるが。
もっとも、お金のない人には有代の世界には円がない、おっと誤変換、縁がないわけだからこわいもこわくないも無関係で、いつもこわい世界に晒されているという境遇には変わりはないのである。ね、ご同輩。
ただ、おいしいお酒には真実がある(もちろんカッコ抜きの真実である)というのが「むの字屋」のキャッチフレーズなのである。その真実がうまいのである。
世の中がなんとなくおいしく思えないのは「真実」がいかがわしいからなのである。ということを庵主はおいしい、まともな、杜氏の気魄がこもっているお酒を味わいながら知ったのである。
今夜もまた真実を一杯だけ。

★「刈穂」の技がさえる★14/10/18のお酒
「日本酒度+23 刈穂 山廃純米 原酒 番外酒」。
庵主がやたらと+(プラス)の高いいわゆる辛口の酒が好きでないということは常々書いていることである。辛口が悪いということではなく、もちろん好みの問題である。
その店に「刈穂」の日本酒度+23の酒があった。
日本酒度はプラスがいわゆる辛口、マイナスが甘口の酒といわれている。いわれていると書くのは、必ずしもその数字と呑んだときの感じが一致しないからである。庵主が好む酒は+3〜+5ぐらいで甘い酒である。マイナスになると明らかに糖分による甘さが感じられるのでちょっと辟易する。プラスでも+5ぐらいだと十分に甘く感じる酒が少なくないのである。
とはいえ、プラスも7から8以上になると明らかに辛口タイプの味わいになってくる。庵主がいうところのスカスカの味わいの酒である。その味は、庵主が「うまい」と書くところのほんのり甘いとしか表現できない味わいがほとんど感じられない酒のことである。庵主にとってはつまらない味の酒である。
肌触りでいえば、甘口の酒がふっくらした柔肌だとしたら、辛口の酒の感触は痩せてきりりとしまっている固い肌あいといったところである。
さわったときに、すぐには愛情を感じないのである。庵主はただ一杯しか呑めないものだからそれでは満足できないのである。触れたときにぬくもりを感じるのがいい。
以前「刈穂」の+12で十分ひどい目にあったからことがあるから(ただ単に その酒が庵主にとってはちっともうまくなかったというだけの意味である)、+23というのは「雪の松島」(+20という辛口の酒がある)の向こうをはって数字だけ上げるためにアルコールをたっぷり添加したちっともうまくない酒だろうと危惧した。しかしその酒を置いている店は信用を重ねた酒亭である。その店が店に出している酒に間違いはないだろうという期待はある。
小さいグラスで半分だけもらうことにした。
スカスカの酒だと思って口にしたら、味に艶がある。もちろん辛口の酒のつれなさはある。そのところが庵主の口に合わないのである。しかし、つれない味わいの中にちゃんと味が残っている。味わいが残っている酒なのである。
アル添だとばっかり思っていたのだが純米酒である。アルコール度数が19〜20度となっている。山廃の酸味がうまく出ているせいか、米の酒の力強さをどしんと実感したものである。
これは企画して造った酒なのだろうか。番外酒としているところを見ると偶然できた美酒なのではないだろうか。この酒を設計図どおりに造ったとしたら、「刈穂」の技に脱帽するのである。いや設計図通りでないにしても+23でこれだけ味わいのある酒を造ってくれたことがうれしい。
ため息の出る出来ばえの超辛口の酒だった。

★縮小率80%★14/10/15のお酒
庵主は強度の近眼で高屈折率の値段の高いレンズを二つも使用している。物の本に人間の体を成分に分解して売ったとしたら数千円にしかならないという計算をしていた本があったが、人の価値を物(ぶつ)として見たら 庵主は己の価値よりはるかに高価な眼鏡を掛けていることになる。こういうアンバランス(不均衡)を見栄というのだろう。庵主はいつも見栄をはって生きているのである。
「眼鏡を掛けている人がみんな目が悪いといえるか。眼鏡を掛けている人が目が悪いというなら、じゃあ帽子をかぶっている人はみんな頭が悪いのか」というくすぐりがセントルイスの漫才にあるのを思い出した。これはいつ聞いてもおかしい。その一つまえのセリフを省略したからこれだけではおかしさがわからないかな。
「馬でさえバケンがあるのだから、人間に人権がなかったらおかしいよな」というのは庵主の高校の先生の言葉である。
その人権というのが、この歳になっても庵主は意味がわからないのである。「詩」とか「少女趣味」とかもう何十年も生きているがいまだに意味がわからない言葉がいくつもある。
「男女ドウケン」については古今亭圓菊から寄席で教わった。
「旦那さんが埼玉県出身で、奥さんも埼玉県出身、だから男女ドウケン」だと。したがって東京都とか北海道では男女ドウケンではないのである。だから離婚が多いのである。女が強い。
庵主の眼鏡のフレーム(枠)が少し緩んできたので調整してもらったところ、同じレンズなのになぜか見え方が突然変わってしまったのである。これまでの見え方より一回り物が小さく見える。その感覚の違いで目がひどく疲れるのである。
B6版の本が文庫本の大きさに見える。本を手にしたときの実感と目で見ているときの大きさが違うと本を読んでいてもその味わいが変わってしまうのである。本の味わいが伝わってこないもどかしさある。その違和感で気が疲れてしまう。
そして、強屈折率レンズの力によって物が小さく見えることでなにがいけないかといって、ちょっと離れたところにある一升瓶が四合瓶にしか見えないというのが寂しい。
手元にある酒がはいったグラスも一回り小さくみえるのでその味わいが違ってしまのうが困るのである。
入れ歯にすると酒の味が変わると聞くが、見え方が変わっても酒の味わいが変わるのである。
まったく目が悪いということは不便なことである。庵主はそろそろ近視から老眼に目が切り替わるころで要するに更年期なのかもしれない。いらいらする原因は肉体のちょっとした変化にあるのかもしれない。
それにしてもほとんどの人が目が悪いという社会では、まともな視力を維持している人がかえって異常ということになる。このことに厚生省(いまは名前が変わったのだっけ)はなんとも感じていないのだからあの省に健康を預けると殺されると不安になってくるのが悲しい。
そういえば、異常な方が「普通」であるというのは何となく日本酒の世界に似ている。これは大蔵省(ここも名前を替えて批判をかわしているのだっけ)の管轄である。やはり数十年ごとに社会を攪拌しないと淀みがたまるものらしい。かといって人間の社会を攪拌すると混乱が起こるから狂気の人が出てこないとそれは叶わないのである。
庵主が一つだけ望みをかなえてあげようといわれたら、ためらわず「金も、女も、地位も、名声もいらぬ。あたしゃ、まともな視力がほしい」と願うのである。
そういえば「健康がなにより。健康だったら命はいらない」というくすぐりもあったっけ。

★意外★14/10/13のお酒
新潟の三梅(さんばい)というのがある。新潟の酒の三大銘酒を謳ったキャッチフレーズ(惹句)である。
「越乃寒梅」、「雪中梅」、そして「峰の白梅」である。
「越乃寒梅」は呑むまででもない。いつでも呑めるから。「雪中梅」は庵主は呑んだことがない。甘口の酒らしい。そして「峰の白梅」も庵主はまだ呑んだことがなかった。
新潟の酒が淡麗辛口という当たりに当たったキャッチフレーズで好評を博していることはご承知のとおりである。
しかしである「峰の白梅」の「純米無濾過」を呑んだところ、これがすごい。なんと、庵主好みの、こってり、まったり、かろやかでさわやかな甘口なのである。
新潟の酒は、味に昔の日本酒のような古さを感じさせないところにモダンの感覚があってそれが都会では好まれているということには異論がないと思う。世の中はライト感覚(深みを追うことなく 軽い感じで てっとり早く楽しめるということ)が売れる時代なのである。新潟酒はその流れに合っているのである。よしあしではなく、時代の流れである。
とはいってもすべての新潟酒がそうだというわけではない。「峰の白梅」の「純米無濾過」に庵主は舌はここちよくいやされたのである。これなら庵主にも呑める、と。もっとも「峰の白梅」が造っている他の酒は呑んだことがないので、庵主のお勧めはこの「純米無濾過」に限ってである。
あたりまえのことであるが、その蔵元にうまい酒があるといっても、そこで造っている酒がすべて同じ品質であるということではない。あくまでも庵主が呑んだその一本だけについての感想なのである。
さあ、新潟のおいしい酒(庵主にとって、ね)を求めて街に出かけよう。

★「露堂々」「伯楽星」★14/10/7のお酒
堂々たる酒銘である「露堂々」(つゆどうどう)。石川県鶴来町出身の「手取川」の純米大吟醸である。
おーっ、いかにも大吟醸といったまったりした酒質である。一口含んだだけでいい酒であることがわかる。そして十分にあまい。このあまいは、甘いではなく、旨(あま)いである。砂糖のような ただ甘い甘さではなく、甘露といった感じのじわーっとしみてくるあまさである。だからあまさがここちよい。
しかし、ただ一杯だけしか呑めない酒なのである。たしかにうまいが、あますぎる。呑み手がその貫祿に負けてしまうのである。もちろんまずいといっているのではない。力(りき)のはいった酒である。だから二杯も、三杯も呑むと呑んでいて力負けしてしまうのである。
まさに「露堂々」。一滴にその酒のすべてが感じられる力作である。
庵主は最近は力作よりも精米歩合が60%ぐらいの酒に心傾くのである。高い酒がうまいのは当たり前である。それよりもそこそこに米を削って造られた酒で十分ではないかという生活感情が芽生えてきたのである。贅沢に過ぎることを美しいとは思わなくなってきた。ただそれだけのことである。
磨きは60%でいいとはいっても、それは吟醸酒の分類に入るのだから、それでも十分贅沢な酒なのである。それでうまくなかったら、造り手の腕が笑われるだけである。買い手の選択眼はここでは問わない。
そして、純米吟醸の「伯楽星」(はくらくせい)。「愛宕の松」(あたごのまつ)が挑んだ吟醸酒である。その気合が感じられる吟醸酒に仕上がっている。こういう気合が伝わってくる酒がまたうまいのである。

★ふるさときゃらばん★14/10/5のお酒
本来カタカナ表記をする言葉をひらかなで表記するというのが庵主はきらいだ。「ら致」(最近は拉致と書かれるまでに出世したこと喜ばしいことである。北のあの人のおかげである。あの人も終生少なくとも一つだけはいいことをしたことになる)とか「建ぺい率」という表記を見るときの嫌悪感ほどではないが、なんとなく趣味の悪さを感じてしまう。そういうセンスを田舎臭いといったら田舎に失礼か。「きょうかい酵母」という最初から品のない表記に比べたらまだましだといってもフォロー(なぐさめ)にはならないか。
で、その「ふるさときゃらばん」というのはミュージカルを演じている劇団である。そのミュージカルが面白い。外国の演劇の脚本を使って、ときには金髪のカツラをかぶって出てきて人物の名前がそのままナターシャとかピーターとか字幕付の外国映画を見ているかのような高級演劇に比べると、ふるさときゃらばんのミュージカルは自前の脚本で日本を演じるのである。なんとも泥くさいのである。だから面白いのである。安心して見ていられるということが何よりである。奇をてらった酒もおもしろいが、安心して呑める酒が心安いのと同じである。
ミュージカルというのは、劇中なぜか突然役者が歌を歌い始めるという珍奇な芝居のことである。歌を唄う必然性を問うてはならない。芝居は何をやっても面白ければいいのである。
真面目に演(や)ったら深刻すぎて見ていると心の負担になるような題材を音楽というというオブラートに包んで人に示すというのがミュージカルという表現方法だと思っている。もっとも耳に快い音楽を楽しむだけの音楽劇でいいと考えてもそれはそれでいっこうにかまわないのだが。
ふるさときゃらばんは、いつも、観客を 憤(いきどお)らせて、泣かせて、笑わせて、喜ばせて、力づけてくれる不思議なミュージカルを見せてくれるのだ。終演後の出口でお楽しみが待っている。それはじつはサービスではないのだ。観客をお芝居のストーリーに引きずり込んでしまうというそのテクニックをはじめて経験したときのショックはいまでも忘れない。観客の前に一本の線を引いて、こっち側がお客さん、その向こう側が花の舞台という安心の建前をそのテクニックは一気にくずしてしまったからである。
宝塚ならこのテクニックは使えない。一本の線の向こう側は夢の世界だからである。それをやると夢がさめる。ところが、ふるさときゃらぱんのミュージカルはそれができるのである。そういうテーマなのである。
おいしい芝居を見た後は、やっぱりいい酒を呑みたくなる。
中国人が「日本人はなぜ悲しいときに酒を飲むのでしょう。酒は楽しい時に飲むものじゃありませんか」といったというのを読んだことがある。なるほど、加えておもしろい芝居を見たときにもいいお酒がふさわしいのですよと庵主はいい添えたい。
酒は「美の川 杜氏謝恩の酒 金賞受賞酒」だった。
庵主は新潟の酒は普段は呑まないと常々書いているが、「美の川」は「良寛」で一目置いているからためらわず頼んだのである。
この酒の味なら庵主の口に合う。新潟の酒はいつも必要以上に綺麗すぎて味わいが薄いというのが庵主の感想である。そこが呑みやすいという人もいるのだが、庵主は量を呑まない酒呑みなのでそれでは呑んでも満足感が残らないからである。
「美の川」の金賞受賞酒には杜氏の気持ちを感じたのである。いい芝居といい酒にめぐまれた夜だった。

★黒松翁★14/10/3のお酒
うまい酒である。三重県津市出身の「黒松翁」(くろまつおきな) のことである。
庵主好みのうまい酒である。庵主がニガ手な酒というのはアルコールくさい酒なのである。逆にお米の味わいが残っている酒が庵主はうまいと思う。米の味わいというのは麹の香りと麹の味わい(酒粕の味のことである)のことである。
「黒松翁」は米の味わいを楽しめる酒である。呑んでいておもしろい。一つの酒の中にいくつもの味の変化を味わうことができるからである。
「黒松翁」といってもいろいろなランクの酒があるが、庵主が呑んだのは大吟醸である。大吟醸といっても普通米(山田錦でないということ)の大吟醸は四合瓶で1300円である。これで十分うまいのである。その味わいは贅沢の域にはいっている。さらに山田錦45%の大吟醸も満足である。さらに山田錦35%の大吟醸もうまい。
そして極めつけは大吟醸の金賞受賞酒の4年古酒である。この酒はうますぎる。これだけの味わいになるとからだが酒を拒まないようになるのである。からだがそのうまさのとりこになってしまうのである。
庵主もいつになく、二杯、三杯と盃を重ねてしまった。いや、もっと呑んだはずである。もう一杯呑もうとして瓶を手に取ったら、一緒に呑んでいた他の呑み手もこの酒はうまかったとみえてすでに空になっていたのである。












