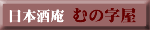
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成14年9月の日々一献
★すごい人★14/9/30のお酒
すごい人がいる。松岡正剛氏の「千夜千冊」(レイアウトが粋)にアクセスしてみてほしい。毎日一冊の書評を積み重ねて、千冊の書評に向けて今驀進中である。松岡正剛氏は本読みである。その読書の幅の広いこと。深いこと。世の中にはすごい知性の人(読み手)がいるものだと圧倒されるのである。
すでに六百数十冊の本がとりあげられているというのに庵主が読んだことのある本は一冊だけしかない。「誤植読本」である。ヤスケンこと安原顕氏などのような剛の読み手の読む本と庵主の読む本がほとんど重なっていないということで己の知性の水準を知るのである。読み手としての次元が彼我には差がありすぎる。まさに教養の違いを痛感するのである。ただ立花隆氏とは重なっていないことで庵主はまだまっとうであるということが裏付けられたと安心しているのである。(内藤陳氏と重なっていたら、これはカタカナ書きのビョーキである。)
で、セイゴウ氏の教養を少しでも分けてもらうおう思って堀田善衛の「定家明月記私抄」を早速買ってきたが、こんどはその「明月記」が読めないのである。「めいげつき」か「みょうげつき」かで戸惑うのである。声に出さなければ意味がなんとなくわかるからすんでしまうのだけど。
もっとも読書の幅の広さでは庵主もひけをとらない。競馬の必勝法から聖書にいたるまで日本語で書かれている本なら一通り読めるのであるが、セイゴウ氏との違いは中身がてんで理解できないということだけである。本を読んでいるのではなく、字を読んでいるだけなのである。だから必勝法どおりに馬券を買っているのだがどういうわけかそれで当たったためしがないし、聖書の名のもとに人は平気で人を殺したきたという歴史をみるにつけあれは本質的にはオブラートで包まれた人殺しの手引き書だと理解してしまう庵主の貧困な知性と氏のそれとはまさに月とすっぽんなのである。
そしてセイゴウ氏に対してはそんなにいっぱい本を読む時間があるというのだからよほどヒマのある人なのだろうとうらやましく思うのである。いやいや、長生きして人より持ち時間が多いという恵まれた人なのかもれしない。
そういえば酒を呑む人(庵主のことである)もまた酒を呑んでは時間を無為に過ごしているのだから人には息抜きの時間も必要なものと思われる。読書を酒呑みの無為と比べてはいけないのかもしれないが、やっぱり似ているような気がするのである。
思えば、この題名だって「すごい人」という粗雑な題の付け方はないだろう。ほんとうは「二流の愉しみ」としたいのである。ただし山本夏彦氏の書名とはちがって庵主のは「愉(かな)しみ」とルビを振るのだけれど。

★伏線★14/9/22のお酒
あらかじめ断っておくが以下の文章はフィクション(作り話)である。ただし最後の6行は真実である。
平成14年9月17日の「読売新聞」の朝刊に大略つぎのような広告が載っていた。
「お詫びとお知らせ 弊社製甲類乙類混和焼酎『ゴールドマックス』および『スーパーゴールドマックス』の一部製品にカラメルを着色料として添加していたことが判明しました。カラメルが添加された焼酎は酒税法上『しょうちゅう』類ではなく『スピリッツ』類として販売すべきものでした。消費者の皆様はじめ関係各位にご迷惑をかけたことをお詫びいたします 旭化成株式会社」。
この広告を見て庵主は事情を理解した。8月12日付の「読売新聞」夕刊に「焼酎とよべぬ! 」(14/8/12のお酒を参照)が一面トップを飾った理由がである。広告取りのための記事だったのである。それは伏線だったのだ。
新聞社の経営は読者の講読料ではなく、広告掲載料でまかなわれている。このところの不況で広告収入が激減しているため、何としてでも有料広告を獲得してくることが経営上の至上命令となっている。
新聞の経営構造は昔からこうである。企業なり、宗教団体なりの公表されては困るできごとを取材してきて、記事掲載を見合わせることを条件に広告(もちろん有代である)を出稿してもらうというものである。発行部数の多寡が広告料金に反映されるので増売も怠ることはできない。ただバーター広告を表立ってやったのでは恐喝かなんかになるので、いまはもっと手がこんでいる。あらかじめ記事で非をならしておいて、後日それに当たることがらをチクッては企業にお詫び広告を出さざるをえないように持っていくのである。これなら新聞社はなにも悪いことをしていない。企業が自主判断で広告を出すのだから。しかも広告掲載料金は定価で取れるのだから喜ばしい。
旭化成はその手に引っかかったのである。
焼酎に毒がはいっていたわけではない。砒素入りミルクの時は広告料と引き換えに記事の掲載を見合わせたと聞くその時の砒素とは違うのである。砒素は毒だからわかった時点ですぐに報道してもらわなければ困る事柄である。ところがカラメルは毒でもなんでもない。ただ焼酎に入れると酒税法上は焼酎として販売できないということなのである。焼酎にカラメルをいれるとスピリッツ類ということになるのだそうだ。そんなことは「ゴールドなんとか」を買い求める人は気にしてないのである。安い焼酎でそこそこに呑めるから買っているだけなのだから。
酒税法上は発泡酒とされる酒をみんなビールだと思って買っているのだし(その代用ビールがうまいからと思って求めている人はほとんどいないと思われる)、またアルコールで増量した清酒でもそれが日本酒だと思って疑うこともなく呑んでいるというのが実態なのである。清酒に関してはアルコールを加えた合成酒も日本酒とみなすと法律で定義を変えてしまうのだから呑めれば酒なのである。他の食品の不正表示と違って、こと酒に関しては毒が入っていなければ中身などそれほど気にしない世界なのである。生ビールの定義といい業界の都合であとからスイスイ変えてしまうのだから、酒の中身が常識と乖離していてもだれも文句をいわないのである。酒税法上の違いなどは飲み手は気にしていないのである。歌をくちずさむときにいちいち作詩はだれ、作曲はだれそれと確認してから歌う人がいないのと同じである。楽しめればいいのだ。だから旭化成は取り越し苦労をしたということになる。
焼酎の文字の上に「スピリッツ類」と書いたシールを貼っておけばいいのである。「焼酎のさわさやな呑み心地を追求したほんのり甘い淡麗辛口のスピリッツです。」とでも書いてあれば、庵主などは見た目焼酎だけど従来の焼酎とどこが違うのだろうかと好奇心を刺激されてつい買ってみたくなるほどである。
こうしてみると給料が高いことでは銀行に劣らない新聞社も読者離れと広告収入減少の中にあって銀行には負けられないとする矜持から自分の高収入を維持するために精一杯営業努力をしているようである。がんばってね。
いつもこれに似た記事ばかり読まされているものだから、それをなぞらえて書いたらなんとなくもっともらしい内容になってしまった。庵主の悪趣味である。
本当の事情は旭化成に電話(0120−010−246)すると教えてくれる。新聞社からのチクリではなく製造現場の事情からカラメルの件がわかったものらしい。

★玉泉堂二題★14/9/16のお酒
玉泉堂(ぎょくせんどう)といってもわからないかもしれないが、岐阜の「醴泉」(れいせん)の蔵元である。
庵主と「醴泉」との出会いは大吟醸の「真咲吟醸」(よめない)だった。これは香りといい味わいの充実感といい庵主好みの酒だった。「醴泉」といっても種類がある。別のところで「醴泉」を見つけて呑んでみたら本醸造だったのか、うまくもなければまずくもないという印象に残らない酒を呑まされたことがある。ラベルで酒を呑まないこと、という自戒を身につけたのである。
その「醴泉」の純米を呑む。うまい訳ではない。かといって不味いというのではさらさらない。さりげない味わいなのである。利き酒をするかのように気張って呑む酒ではない。呑んでいて気持ちのいい酒なのである。気の置けない酒というのはこういう酒をいうのだろう。
どの純米酒もいつもこういう味わいを保っていてくれるのなら、日本酒は純米酒が一番と自信をもってすすめられるのだけど、本醸造にかなわない純米酒も少なくないのである。
同じ玉泉堂の「純米 秋波」は山田錦100%で30か月熟成させた酒であるという。味がのっているというのはこういう酒をいうのだろう。2年有余の熟成を感じさせる味わいはその酸味の美しさと相まって酒を呑む楽しみを満喫させてくれるのである。いい酒を呑んでいるという幸せにひたることができるのである。
酒に心がある。そんな気がする味わいだった。

★高山行★14/9/15のお酒
新宿発の高速バスで高山に向かう。松本で高速道路を降りるとそこは長野県である。
道路沿いに酒の看板が目につく。
「大雪渓」
「岩波」
「夜明け前」
「大信州」
「真澄」と知っている長野の酒の看板がつぎつぎに目にはいってくる。
安房(あぼう)トンネルを抜けると「久寿玉」の看板で岐阜県にはいったことがわかる。
沿道の酒屋の看板には「深山菊」「蓬莱」「久寿玉」とある。岐阜県である。電柱に目をやると「白真弓」の看板が続いている。しかも一本一本の電柱にである。
3連休の中日である。高速道路の渋滞に加えて一般道路も渋滞で、午前8時に新宿を出たバスは8時間かかって高山に着いた。午後4時である。
まずはビールを一杯と思って、駅前の酒屋をのぞくと「飛騨高山麦酒」があった。飲むのはこれに決めた。
「NHKテレビ小説 さくら」という日本酒が目についた。一つは「鬼ころし」の老田酒造、もう一本は「蓬莱」である。
庵主はテレビを持っていないので「さくら」の舞台がどこであるかを知らなかった。ご当地高山がそうだったのかのと初めて知った。「テレビはそろそろ終わるから、このお酒もここにあるだけです」とお店の人。
そういえば高山には蔵元が何軒もあったのを思い出して「高山には蔵元さんはいくつありますか」ときいたら「8軒ありますよ」とのこと。
会津に行ったときも、あっちにもこっちにも蔵元があって数の多さにびっくりしたものだが、高山もうらやましい限りである。
ヴァイツェンをはじめてとして何種類かの瓶が並んでいた。「飛騨高山ビールを飲めるお店はありませんか」ときくと、「駅の前の道をまっすぐ行って4本目の道を右に回って」と飲めそうな店を教えてくれた。「きょうは休日だから店をやっているかどうかわからないけどあの店なら飲めるかもしれないなぁ」と親切に教えてくれた。「高山ビールはいま7種類あるから、全部は揃ってはいないと思いますよ」とのこと。そのうえ小売り価格が一本750円なのである。500ミリリットル入りと思われる瓶でである。
ぶらりと古い町並みのあたりを歩いていたら桟橋のそばの喫茶店「バグパイプ」にあこがれの「飛騨高山ビール」の広告幟が出ているのを発見。
ためらわず飛び込んで注文する。「ダークエール」だけですとのこと。それでいい。
サーバーから注いでもってきてくれたダークエールはまずかおりがいい。これがビールだと庵主は納得する。味もたしかにビールだと満足する。この店の飛騨高山ビールはうまい。
帰りに寄ったラーメン屋では、瓶入りを1000円で提供していた。入って来た観光客がビールを頼む。「キリンと高山高原ビールがあります」というと客は「飛騨高山ビール」を選んだ。「値段が高いですけどよろしいですか」と店の人が念を押す。
うまいビールである。しかし世の中は値段が安い発泡酒が売れているというのが実態である。小売値ではなんとその7倍近い値段なのである。観光客でもなければ飲むわけがない。庵主は量が飲めないから少々高くてもまともな(うまい、という意味)ビールを飲むことに抵抗はないが、たくさん飲む人はこの値段では財布の都合上気楽に飲めないだろうということは想像に難くない。
庵主はそのラーメン屋では「蓬莱 純米吟醸」の一合瓶を冷やで呑んだ。
「蓬莱」はにおいが昔の純米酒によくあったはなやかさのない沈むようなにおいなのだが、呑んでみると酸味がすっきりしていて悪くはない。ぺっぴんなのに化粧が下手な娘といったところだ。いい酒なのにもったいない。藍色の一合瓶は高級感を漂わせている。
ちょっと醤油がこってり気味の高山ラーメンを食べながらおいしく呑める酒だった。
高山は存外酒都なのである。

★国分寺の酒★14/9/12のお酒
版画家の岡谷敦魚(おかのや・あつお)氏から版画展をやるので国分寺まで見に来てくださいと案内のハガキをもらう。
銀座の画廊で個展を開いたときに作品を拝見して、何か感じるものがあったから記帳してきたのである。見た作品がちっとも理解できなかったときは何も書かないでくるのが常である。
和紙に版である。抽象画である。版面の色遣いは渋い。庵主にはどうやって版を作ったのかわからなかった。いいのである。味わいがある。手で触れてみたくなるような見た目に感触のよさそうな版なのである。
この味わいは襖絵にするとしっくりくるいい絵柄だと思った。以前見た中西夏之氏の作品がそうだった。抽象的な柄を見てこれは襖絵だと思ったことがある。
中西氏の作品は心かろやかに躍っていた。一方、岡谷氏の作品はこれを襖絵に仕立てると心が落ち着く深みがあるのである。
お誘いがあれば出かけていく。知らない街に酒をさがす楽しみがあるからでもある。
店は駅のそばですぐに見つかった。居酒屋「はる」である。
「開運」純米ひやづめ、
「美丈夫」五百万石舞、
「うきたむ」純米吟醸、
「千代むすび」純米3年古酒、
「羅浮仙」大吟醸
とカウンターの前に掲げられている。酒を呑ませてくれる店である。
島根の「羅浮仙」(らふさん)大吟醸を最初に呑む。大吟醸の模範的出来ばえの酒である。ちゃんと大吟醸の風がただよっているがそれ以上でもそれ以下でもないということである。一杯の値段が高いだけにそれだけではいまの庵主にはものたりない。心にひっかかる特徴がないのである。
山形の「うきたむ」純米吟醸は乳酸のにおいがある。よくいえばこってりした酒。しかし庵主はそのにおいを好まない。
たった2杯で酔いがまわってしまったが、どうにも仕上げの酒が呑みたくなったのである。
「美丈夫」(びじょうふ)を呑んでみた。五百万石舞とある。これはうまい。味にクセがない。過度な匂いもない。そして味に必要にして十分な厚みがある。立体感がある。この酒を最後の切り札にとっておいたのは正しかった。
もちろん前の二つがまずいというのではなく、ただ庵主の口に合わなかったというだけのことである。いずれもまだ呑んだことのない酒だったので好奇心から味わってみたのである。知っている酒があるとホッとする。
なれない人が、例えば「篠峯」(しのみね)だの「夢醸」(むじょう)だの「鳳凰美田」(ほうおうびでん)だの「天明」(てんめい)だの知らない酒ばかり並んでいる酒祭りを目の前にしてドキドキする気持ちがよくわかる。何を頼んだらいいのやらわからないのが普通なのである。もっとも知らないときはお店に聞けばいいのである。たとえば「ベテラン杜氏の造った酒が呑みたい」というように。「うちは今月は若手杜氏の酒を揃えてみました」と返ってくるか、奥から別の酒瓶が出てくるか、はそのお店の実力(=日本酒に対する興味の多寡)次第ということである。

★珠玉のビール★14/9/10のお酒
かなり酔いが回っていたのである。そのビールの名前を聞いたものの全然思い出すことができない。
博石館ビールの2年眠らせたビールである。ギネスビールのような真っ黒い色をしたビールだった。
それがうまかった。それを口にするまでにいろいろなビールをもう何杯も飲んでいたから十分に酔いがまわっていた。そういう状態で飲んだにももかかわらず、そのビールのうまさは庵主が知っているビールの味を越えたものだった。酔いがさめる思いがした。居住まいを正して呑みたくなるような気品がただよっていたからである。
たしかにビールだ。がしかし、これはビールの味ではない。庵主がこれまで飲んだことのあるビールの範疇を越えている。想像を越えたビールなのである。これまで経験したことのないビールの味である。
甘い飲み物を「甘露」という。たえなる飲料を「醍醐味」という。このビールはいうならば「珠玉(たま)」のような美しさなのである。
ビールというと、夏場のビールメーカーの広告のようにジョッキかグラスでぐびぐびと飲むのがおいしいかというと、すべてのビールがそういう飲み方でうまいというものではない。
じっくり味わいながら飲めるビールがいくらでもあるのだ。これまでの日本のビールは水がわりに飲んでもおいしいビールしか作って来なかっただけなのである。それがビールのすべてだと思わされていただけのことなのだ。万人向けのだれが飲んでもそれなりにうまい味を作り上げたきたのだからそれはそれですごいことである。しかし時代は変わった。もっとうまいビールが飲みたいという需要が発生したのである。いわゆる地ビール(これ、もっといい言葉にならないのかな。地酒じゃありまいしネーミングがよくない)の醸造所が認められるようになってから日本のビールは夜明けを迎えたのである。
どこで飲んでも同じ味わいのこれまでのビールを共産主義ビールというのなら、やっとビールの味の選択ができる資本主義ビールの時代になったということである。
べつに種類が一つしかなくても生きていく分にはいっこうに差し支えない。種類が増えると今時の事務用電話機のように機種ごとに微妙に使い方が異なることからかえって使いにくいということさえ起こりうる。携帯電話機にいたってはよくもまあこんなに次から次に下品なデザインを思いつくものだと感心するほどの盛況である。種類が多くなるとろくでもないものが氾濫するというのが現実である。
とはいえ、酒は飲めばなくなる一時(ひととき)の快楽品だから、いろいろ種類があったほうが浮気の庵主としてはうれしいのである。こと食い物、飲み物に関しては毎日同じ物を口にすると飽きてしまうという人間性からしても種類はたくさんあった方が精神的にもよいことなのである。
そして話は博石館の珠玉のビールに戻るが、サワーグラスに注がれたそのビールの気品のある味わいに庵主はすっかり魅了されてしまったのである。
庵主がこれまで知らなかった世界を覗いた思いがした。

★夏の終わりにはまともな酒を3杯★14/9/6のお酒
「南」純米大吟醸 金賞受賞酒
「天の戸 白雲悠々」純米大吟醸
「醸し人九平次 佐藤彰洋」大吟醸
この順番で呑んで正解だった。
「南」の渋さを含んだ大吟醸の味わいは十分にうまい。一口で酒のうまさが口に広がる。厚みのある味わいの中にほんのりと渋みが隠れている。いかにも大吟醸といったこってりした味をそれだけの印象に終わらせない渋みである。酒のうまさを堪能できる一本である。
「天の戸」もこのランクの酒になるとじつにうまい。それ以外の酒がまずいというのではなく、酒がほんとうにきれいなのである。「南」の後に呑むとさらっとした味わいがいっそうこころよい。個性のある酒を呑む楽しみがここにある。
「九平次」ははじめて杜氏の名を付した酒を出したという。酒造りもこの段階に踏み込んだら酒にいいも悪いもない。うまいとか、まずいとか、そんな下世話な次元を越えているのである。ただ酒の品格を味わうのみである。
酒が呑めない庵主でもこの3杯なら呑むことができる。おいしく呑むことができる。べつに呑めないのを無理してまで酒を呑むことはないのだが、まともな酒なら庵主のからだは酒をぜんぜん拒まないから不思議である。もちろん酒のうまさにだまされて呑みすぎると後になって覿面に気分がわるくなるのはいうまでもない。やっぱり酒が呑めない体質なのである。今夜は60ミリリットルのグラスで3杯である。これが庵主の限界のようである。一合で幸せになれるのだからありがたいことである。

★千歳の酒★14/9/4のお酒
北海道千歳市が庵主の生まれ里である。市内にはサントリーの瓶詰工場がある。キリンビールの工場もある。地ビールの「ピリカワッカ」の醸造所がある。隣の恵庭市にはサッポロビールの工場がある。清酒「千歳鶴」の蔵元がありそうだがそれは千歳の酒ではない。札幌の酒である。
千歳という街は飛行場があるだけでなんのとりえもない普通酒のような街だと思っていたが、こうしてみるとビール天国といっていい街なのだ。
で、市内で日本酒を呑もうとするとこれがなんとも頼りないのである。
ひめぜん。街中の「地酒あります」の看板で見つけた店である。ちょうど仕入れの端境期だったのか呑む酒がないのである。店頭には「開運」「十四代」「南部美人」などの空きビンが並んでいたので日頃の酒の揃えはしっかりしていると思われるが、この日は庵主がワクワクするような酒がなかった。
しかたなく「国稀」(くにまれ)の本醸造を呑むことにした。「鬼殺し」である。「国稀」は北海道増毛町の酒である。北海道の地酒ではないか。地酒を売りにしている店なら「国稀」のもっと上のランクの酒も揃えておくぐらいの意欲があってもいいと思う。「辛口」の(わるくちである)本醸造なんか呑んでもおもしろくないのである、庵主にとっては。国際空港をもっている街なら北海道の酒をぞんぶんに楽しませてほしいのである。
千とせ。この店は数十本の酒が大きな冷蔵ショーケースの中に並んでいる。管理は申し分ない。「雪雀」(ゆきすずめ)の純米吟醸を呑んでみた。評判どおりのいい酒である。炭火焼きの若鳥の焼け具合のうまさは抜群。「呼友」などのいい酒もあるのだが、また「北奏夢」(ほくそうむ)といった北海道でもなかなか呑む機会のない釧路の酒もあるのだが、しかし酒の揃えにいま一つおもしろさがないのである。
このおもしろくないというニュアンスは以前に酒名を具体的に列挙してそのところを書いたことがあるのでそれを読んでほしい。
ビアワークス千歳。ヴァイス(ヴァイツェン)の生を飲む。が、この5月に東京で開催されたビールフェスタで飲んだヴァイツェンの生きのよさが感じられない。まずくはないがいまいち生ビールの華やかさが感じられない。瓶入りのヴァイスを買ってきて飲んでみたが、生とは別物のような元気のない味わいだった。東京で飲んだヴァイツェンが全国の地ビールの中にあってもひときわうまかっただけに、その印象が強く心に焼きついていたので、そのときとの落差に愕然としてしまったのである。

★「万齢」大吟醸 三年古酒★14/9/1のお酒
「万齢」(まんれい)は佐賀県相知町出身の酒である。その「大吟醸 三年古酒」を呑む。
東京ではなかなか呑む機会のない酒である。と思っていたが、なにげなく「陶玄房」(とうげんぼう)(新宿にある居酒屋)の店頭に掲げられた黒板をみたら、酒のランクは書かれていなかったが「万齢」と記されているのが目についた。知ってる人はちゃんと集めてくるのである。東京の酒場は酒の流行をよく知っているものだと感心する。
この三年古酒の大吟醸は至福の一本である。「なにも足さない、なにも引かない」というのはウイスキーのコマーシャルである。そのキャッチフレーズはうまい。そのうまいところを借りてきていうならば、この酒は「なにも言葉はいらない、そしてなにも語ることはない」のである。
うまい、と書いたのではこの酒を口にしたときにじわっーとわきおこってくる感銘といっていい味の深さを正しく伝えることができない。
言葉でそのなんともいえない味わいを語れば語るほど、この酒を口にしたときの悦びからは遠ざかっていくのがわかる。そう、ことばはいらないのである。
香りが渋い。そして三年寝かせても紹興酒のようなクセのある味は出ていない。その味わいをあえていうならば、ありがたい味わいとしかいいようがない。
もっとも、そこいらで庵主がこの酒をラベルを見ることなく呑んだなら、今夜のように深い味わいを覚えて感銘を受けるかどうかはわからない。よくできた普通酒かな、と判断してしまうかもしれない。
さいわいなことによく管理された店でこの酒と最上の状態でめぐり会えたことはしあわせだった。いい酒をよく管理された店で呑むときの日本酒のうまさは至福と同義語といっていい。心にしみてとくるうまさを感じるのである。
うまい酒をおいしく呑ませてくれる店だけが庵主の立ち寄れる呑み屋なのである。
庵主は酒が呑めない体質だと思っている。まずい酒が出てきたときには、顔で笑って呑むという芸当ができないからである。とにかくも酒を口に入れようとしてもからだが受け付けないからである。一口も呑まずに、この酒はうまいですね、とはいえないではないか。にもかかわらず、からだが平気で受け付けてしまう酒が現にあるのだからやっぱり日本酒はすごいと思うのである。そのすごいものをいつも少しだけたしなんでいる。
庵主にも呑める日本酒があるということはありがたいことである。











