<
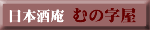
「むの字屋」の土蔵の中にいます


FONT size="5">平成14年1月の日々一献
★しこたま呑む★
酒を呑んだ。しこたま呑んだのである。久しぶりのことである。そして庵主はやっぱり酒が呑めないということを思い知ったのである。
もう呑んだ酒も思い出せないほど、いくつもの酒を呑んですっかり酔っぱらってしまった。せっかく呑んだ美酒をすっからもどしてしまったほどである。そういうときに限ってうまい肴をたべているのだから勿体ないという思いが募る。
その日は酒の量を抑制できないほど心が疲れていたのだと思う。それほど心が疲れているとは庵主自身が気がついていなかった。酔ってはじめてそれを知ったのである。このところ、ちょっといろいろあるもので。
一緒に呑んだ男は酒が呑める男で、自宅の冷蔵庫には、今は黒龍、田酒、麒麟山がはいっているという。酒の話になると話がはずむのである。
呑みすぎる条件はそろっていたのだが、その男もその日は酒にまかせたい事情があっていつになく盃を重ねていた。
一軒目が盛況でつぎの客がはいってきたので店を出た。もう一軒寄ってみようと思ったのが地獄へのまっしぐらであった。その時点ではまだ酒がうまかったのである。
さすがに二軒目では酔いが体を縛りはじめた。その店で出てきた酒もほんとうにいい酒なのである。酒の保管がいい。日本酒グラスに注がれた酒につやがある。庵主はいつもなら一杯しか呑まないしけた客なのだが、その日は酒呑みと一緒だったからついつきあってしまったのである。
ただただ勿体ない酒の呑み方をしたものだと忸怩たる思いが残る夜だった。酒に失礼な呑み方をしたと深く懺悔するのである。
どうやってうちに帰ってきたかよく覚えていない。
●14/1/31

★三杯の酒★
佐賀県塩田町出身の「東一」(あずまいち)の「雫搾り斗瓶貯蔵酒」を呑む。「うまい」。庵主がうまいと思う酒はこういうまろやかな味わいの酒である。酒を舌にのせたときに、液体なのにまるでやわらかいゼリーをふくんだような感触がある。酒がぽっちゃりちとやわらかいのである。その感触が好きである。そういう酒を一杯だけ呑みたいのである。
味はあまい。日本酒度はプラスなのだろうが、味わいは旨(あま)い甘いのである。そういう旨い酒が庵主は好きなのである。
「じゃ、もう一杯呑みますか」と言われたら、笑ってごまかすだけである。「いやいや、私は呑めないものですから」と。この手のぽっちゃりしたふっくらした甘い酒は、最初の一杯としてはうまいのだが、しかし、二杯、三杯となると、ちょっと呑みつづけるのは苦しいのである。そのうまさゆえに、うますぎるので、そのうまさに飽きてしまうのである。
福井県松岡町出身の「仁左衛門」(にざえもん)。押しも押されもせぬ酒である。この酒を呑んで不味いといったら、呑み手の教養がうたがわれるいやな酒である。だから、そういうときは「ちょっと私の好みにはいませんね」といなしておくことだ。
この酒の味わいにはわび、さびの世界を感じるものがある。味が枯れているのである。きれいに枯れているのである。二、三年寝かせた酒のような年を経た味を感じたのである。しみじみと味わったのである。やっぱりこの酒はうまいとかまずいとかいう酒ではなく、じっくりその味わいを感じて呑む酒である。
この酒をまずいと感じたら、それはまずいという言葉ではなく、もっと適切な言葉で表現しなければならない味わいなのに、それを表現する言葉を知らないばかりにまずいという言葉を当ててしまっただけなのである。
庵主にもその味を知っているのにどう表現したらいいのかわからない酒の味がある。その、その味なのだけれど、なんといっていいのかわからないのである。言葉を知らないのである。
その味わいを表現する言葉を自分自身で見つけないとならない酒なのである。なにもあわてることはない。呑んで、呑んで、呑んで、ある日、その酒がみえてくるのだから。
「磯自慢」(静岡県焼津市出身)の「水響華」は水のような味わいである。「東一」のような重厚な味わいではなく、「仁左」(にざ。にざえもんのことである)のように深い味わいをさぐるような酒ではなく、さらりとしているので、前二酒のあとに呑むと頼りない感じのがする華奢な酒なのだか、呑んでいるうちにその酒のよさがじわーっとわかってくるいい酒なのである。
この三杯の酒を一度に味わうことができるのである。東京では。東京は日本酒を呑むには恵まれすぎている街ある。ここはまた酒都なのである。
●14/1/29

★手書きラベルの「富久心」★
茨城県十王町出身の「富久心」(ふくごころ)の吟醸酒である。
ラベルが手書きなのである。コピーかとよく見たが、やっぱり手書きなのである。蔵元名と所在地はスタンプを押してある。「お酒は20才になってから」という親切書きもゴム印である。それ以外はすべて筆文字で書かれている。
手書きのラベルといえば「義侠」の「妙」(たえ)があるが、あれは四合瓶でもかなりのお値段の酒である。本数も少ないのだろうが、この酒は四合瓶で1300円の酒である。数はずっと多いだろう。しかし東京ではなかなかお目にかからない酒だからそんなに本数は多くないのかもしれない。丁寧に造られた酒で、蔵元の地元だけで売り切ってしまう美酒なのかもしれない。そうなるとこの酒はお買い得である。というより、ひょっとしてめぐり会えた人だけがその幸運に与れるうまい酒かもしれないという期待が湧いてくる。
よかった、と思っている。期待どおりの酒だったのである。
多少の香りがあるのは「郷の誉」風である。味がしっかりしている。要するにうまいのである。
庵主がうまいと思う酒には、「うまい」と感じさせる味わいがある。「うまい」と感じさせる一定の水準があって、うまい酒はその水準を越えているのである。あとはその酒の個性である。口に合う、合わないは呑み手の好みである。
「富久心」吟醸は「うまい」の水準をなんなく超越している酒である。しかもそれ以上にいらない力がはいっていない酒なのである。じつに気のおけない酒なのである。静かにそのうまさを味わうことができる酒なのである。
●14/1/27

★酒の呑み方に品が出る★
その店で「量は五勺でけっこうです」と言ったら断られてしまった。「うちは定量でおすすめしていますので」。結局、庵主には呑みきれない 1.5合で出てきたのである。
売値を揃えるためなのだろう、ある酒は1合で1200円、別の少し安い酒は 1.5合で1200円となっている。
その日庵主が呑みたかった酒は、 1.5合で1200円だった。呑みすぎると、最初うまいと思った酒もやがて感動が薄れていくものである。酔いがまわってきてそのうち味なんかどうでもよくなるのである。
幡ヶ谷にある酒亭「たまははき」では、呑めない人は五勺で注文してくださいと張り紙が貼ってある。そうなのだ、その人に合ったおいしい酒の量というのがある。たくさん呑んだ方がうまいという人はたくさん呑むがいい。しかしほんの少しの美酒に悦楽を求める庵主にとっては少量の酒で十分なのである。食い物もそうだが、酒にしても呑みきれないほどの酒を注文するのはみっともない。
銭金の問題ではなく、物を粗末にする心がいやしいのである。自分の適量を読めない品性の欠如がはずかしいのである。
せんだってのことである。昼間に酒が呑みたくなったが、コップ一杯はいらない。夜なら時間をかけて呑むこともできるが、昼間である、ちょっとだけ味わいたかったのである。半分でもいいと思ったが、制するまえにコップの酒はなみなみとつがれて袴にあふれていた。結局半分以上も残してしまうことになってしまった。
たくさん注ぐことがサービスだと思っているのである。親切だと思っているのである。酒はおいしく呑んでもらうことが本当のサービスなのである。適量を越えた酒はうまくもなんともない。かえって呑むのが苦痛ですらある。
よくあることだが、ケチな男がたまたま人に酒をおごるというときに、気前のいいところを見せようとしてか、さあどんどん飲んでくれ、勘定の心配はするなと太っ腹なところを見せることがある。それが間違いなのである。相手の酒量を越えた飲酒は酒をまずくするだけである。最初はうまいと思った酒も酔いはその感動さえも忘れさせてしまうからである。そういうときはいい酒を適量すすめるのである。どうでもいい酒をたくさん飲まされてもうまいわけがない。あとから二日酔いにでもなったら、せっかくのゴチ(ごちそうにること)が苦痛として記憶されることになる。
自分の適量を知るということが、酒呑みの修行なのである。きちんと自分の酒量をはかれるということが酒呑みの器量なのである。
酒はきれいに呑みたいと庵主はつねづね思ってはいるのだが、なかなか、つい。
●14/1/23

★警世の書★
昔のことである。三増酒(さんぞうしゅ)が全盛のときに、一冊の本が出た。雑賀進氏が書いた三増酒を糾弾する本である。純米酒こそがまともな日本酒であると主張する本だった。
庵主はその本を読んで日本酒に目覚めた。そのころはまだ酒を呑む風をもっていなかったのだが、当時の日本酒がいかにひどいものだったかを知って、まとまな酒だという純米酒ならきっとうまい酒なのだろうと信じ込んで純米酒を探し求めたのである。ところがその純米酒とやらが売っていないのである。
そのころ多くの人は三増酒が日本酒だと思い込まされていたのである。もっとも当時は生まれた時からそれが酒だと思って育ってきた人ばかりなのだから、本物の酒を知らなかったのも無理はない。人間の呑み物ではないものを酒だと信じ込まされていたのである。呑み手は長くだまされていたのである。
食事とはいえない食い物があふれている。人間の食い物ではない、それは餌である。日本酒の世界もそうだった。酒ではなく、ただのアルコール飲料が日本酒であるとして売られていたのである。うまいわけがない。それが業界ではあたりまえだったのである。酒のよしあしは特級、一級、二級だというのだから、今となっては噴飯ものであるが、そのような酒しか流通していなかったのである。そのことを教唆しつづけたのが大蔵省である。よくよく恥を知らない官庁である。最近は旧悪を恥じて財務省と改名したがその性分があらたまるわけがない。おんなじ人がやっているのだから。
むかし缶詰業界が鯨の肉をコーンビーフと称して売っていた時期があった。買い手は長くだまされていたのである。ラベルには牛肉みたいに書いてあるのに中身は鯨肉というのは不正表示ではないかと指摘されたら、それは業界の慣習であると強弁していたものである。業界が間違っているのである。
岡目八目というが、傍から見ているとよくわかるのに、その世界の中にはいると異常性に気がつかなくなるものである。新聞の記者クラブは、新聞が記事で批判する談合の最たるものなのに、新聞社という世界の中に入ってしまうとその異常性がわからなくなるのである。なんたって周りにいる人がみんな異常なのだから、それに気がつかなくなるのだ。腐った年寄りがその状態に安住しているのだから若造の批判に耳を傾けるはずがない。その年寄りは若造の未来なのである。
三増酒を批判する雑賀進氏の書に匹敵する警世の書が出た。松田忠徳氏の「温泉教授の温泉ゼミナール」(光文社新書・680円税別)である。
温泉の多くが循環風呂だとはこの本を読むまで庵主は知らなかった。しかもその水質には問題が多いというのである。
温泉業界はそのことを明らかにしないのである。
庵主もだまされていたのである。温泉は体にいい湯水だと思っていた。
おいしい酒を呑むためにも商品知識が必要であるように、いい温泉につかるためにはこの本は必読書である。あとは、お酒とおなじように数多く当たってみることである。
温泉に徳利と猪口を載せた盆を浮かべてちびちびやるという図があるが、体にいい呑み方なのかどうかは知らないが、それもまた日本人が経験から生みだしたお酒のおいしい呑み方なのだろう。いちどはやってみたいではないか。
温泉につかることは日本人の至福なのである。その温泉に、業界の都合でウソをもちこまれては困るのである。
−−−
三 増 酒
戦時中の米不足のときに、需要を満たすため少ない米からなんとか日本酒らしいものを作ろうという切実な事情から考えだされた醸造法によって作られた、なんとなく日本酒みたいなお酒のこと。薄っぺらな味わいが特徴の致酔飲料である。これも、いちおう日本酒と呼ぶことになっている。日本酒に似て非なるものである。
マーガリンをバターと称しているようなものである。バターにとっても、マーガリンにとっても不幸なことである。
戦争中の昭和17年酒造年度から日本酒にアルコールを添加することで増量することが行なわれるようなった。この時点では米だけで造る量に比べて1.5倍ぐらいの増量だったという。
戦前の満州ではすでに造られていた三増酒が日本国内で造られるようになったのは実は戦後になってのことなのである。昭和24年酒造年度以降、アルコールの添加量を増やし糖類を加えて味を調整して約3倍の量の酒が造れる醸造法が取り入れられるようになった。徴税のつごうもあってのことだが、その悪弊が今日まで尾をひいているのである。
本来の造り方によって造られる量の約3倍の量の酒が作られることから三倍醸造酒という。略して三増酒。
庵主は三蔵法師に引っかけてその酒を孫悟空と呼んでいる。へたな造りの酒より三増酒のほうがしっかりしていることもあるので、一概に三増酒はまずい酒であるということはいえないが、やっぱり本来の造りによるまともな酒の方が味わいは深い。
ただ酒は好みですからおいしいと思ったら孫悟空をお飲みください。甲類焼酎を好む人もいるぐらいですから。好き嫌いにとやかくいわれることはないのですから。
要するに日本酒は今なお戦時体制を維持しているということである。日本酒業界はお上のいうことに素直にしたがう律儀な業界なのである。日本酒はそういういい人たちが造っているのである。悪貨が良貨を駆逐するように、三増酒は一時まともな日本酒を駆逐してしまったのである。
●14/1/17







