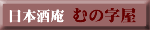
「むの字屋」の土蔵の中にいます


平成13年11月の日々一献
★お歳暮をいただく★
ありがたいことである。
庵主にお歳暮と称してお酒を贈ってくれる人がいる。その気持ちがうれしい。庵主はいただき物が苦手なのであるが、酒なら呑めばなくなってしまうので後に残らないから助かる。
とはいえ、庵主は酒の量が呑めないので、たくさん酒をいただいても
うれしいやら、心のこもったお酒なのでぞんざいに扱うわけにもいかず、どうしょうものかと思案にくれるやらで、なんともうれしい悲鳴をあげたくなるいただき物なのである。
ひょっとして贈り主の中にはこのホームページをご覧になっている方がいらっしゃるかもしれないので、さりげなく注文をつけておこう、と。
庵主にお酒をどうしても贈りたいという方は、今年呑んだお酒でいちばん印象に残っているお酒を四合瓶で一本だけ送っていただけませんか。そのお酒のおいしさを一緒に味わいましょう。庵主にお酒を贈るときは、その値段ではなく、その味の思い出を贈ってくれるとうれしいのです。
それはともくか、礼状を書くためにいちおう味を楽しませていただく。
なつかしい酒があった。「銀盤」の「米の芯」である。この酒はロングセラーである。
何年も前に、手に入る美味い酒といったらこの「米の芯」だった。当時はまだ三増酒が全盛の時代で、そのなかで「米の芯」は燦然と輝いていた美酒だった。銘酒なのである。ウィスキーの醸造器のような瓶の形も昔と変わっていない。蓋はプラスチックになっていた。包装紙を開けるまでもなく、その箱の形で銘柄がわかる唯一の酒である。
いまは、若い杜氏が造る気合のこもったうまい酒も加わって、美酒を選ぶのにかえって迷うほどになったが、いまでも「米の芯」はその格調のある味を楽しませてくれる。
「おお、そちも健吾であったか。予も健吾であったぞ」としばし再会を懐かしがったのである。お歳暮の酒もいいね。
●13/12/22

★今日は風邪の日★
朝から頭が妙にずきずきするのは、昨日呑んだまずい酒のせいかとも思ったが、なにぶん量を呑んでいないのだから、二日酔いということも考えられず、寝不足からくる風邪の症状なのだろうと見極めた。
頭がはっきりしないと体もだるい。風邪薬の代わりにと酒を呑みに出た。
「十四代」の「双虹」(そうこう)である。かおりも強くなく、といっても庵主は風邪気味で鼻の感度が落ちているので本当の味を感じているわけではないからもっと香りがきいていたのかもしれないが、舌に感じる味わいは品のいい酒に仕上がっている。凜とした味わいなのである。
で、呑みたい時に「天保正一」があった。鼻がきいていないから、ただ舌の感触だけで酒を味わっていた。あまい。柔らかい。まろやかな味わいが舌をくすぐっていく。庵主ごのみの酒である。
そして、あの辛い酒「醴泉正宗」。ところが前に呑んだときより今日の感じはやわらかいのだ。風邪のせいか、封をきってから呑み頃になっていたものか。
一つの酒もただ一杯だけという呑み方ではなく、時間をおいて呑んでみるというのもまた風雅な呑み方である。その酒の変化を楽しむのである。お酒はいろいろな呑み方ができるから面白い。
風邪気味だったので、「醴泉正宗」を燗にしてもらってもよかった。
今日は舌の感触だけで酒を呑んだが、それでもいい酒はアルコールがよくなじんでいるのがわかる。香りを楽しめなかったから片肺飛行であるが、いい酒はそれでもうまいのである。うまいというよりも味に個性がはっきり感じ取れるのである。
銀座に自らを隠れ家と称する酒亭「吟泉」がある。以前は六丁目にあったのだが、今度は八丁目に店を移していっそう隠れ家のような場所で店を開いた。一見、どこに入り口があるのかがわからない。
不思議な店なのである。ここに移ってまだ二週間もたっていないのに、やって来る客はまるで自分の家に帰って来たかのように脱いだコートをハンガーにかけて、昔からそこに通っているような感じでさりげなく空いている席に座るのである。手慣れているのである。かえって主人の方が、店が変わってからまだ体が店になじんでいないとこぼしているというのに。
知らないと絶対わからない店に、うまい酒を求める酒徒は初めての客でも旧知のように訪れてくるという。そう、そういう酒徒はいいお酒と旧知なのである。
ただ黙っていい酒を三杯ごちそうになって、早めに帰ってぐっすり寝たら今朝は風邪の症状はおだやかになっていた。
●13/12/20

★まずい酒★
いやはやまずい酒なのである。あきらかにまずいという酒に出会ったのである。
これはなかなかお目にかかれないまずい酒である。あんまりまずいのでかえって感動してしまったほどである。皮肉でいっているのではない。庵主が普段呑んでいるうまい酒とは明らかに味わいの方向が異なる酒なのである。
これほどまずい酒に出会うと逆にカルチャーショックを受けてしまう。こんなまずい酒がいまでも造られているのかと。
「うまい」酒というのは一定のうまさの水準を越えている酒である。
うまくない酒がすなわちまずい酒ではない。うまくもないが、まずくもない、そして味わいもない酒はいっぱいある。だれでも知っている有名大手蔵の酒にそういう酒が多い。庵主がうまいと思わない酒の多くは、悪い酒ではないが味わいがない酒だった。しかしこの酒は明らかにまずいのである。
ある有名な料理人がいうことには「まずいのも味のうちです」とのことである。ふつうに料理を作ったり、酒を造ったらそこそこの味になるものである。だからまずいというのは味の個性なのである。ただ後ろ向きなだけである。
今そのまずさを、いや味の個性を、じっくり堪能しているところである。なぜまずいのか。どこがまずいのか。どうしてまずいと感じるのか。
まず味が沈んでいる。うまい酒は味が明朗にして快活にして明るいのである。性格がいいのである。この酒は性格が暗い。
つぎなる特徴は口にしたときにアルコールを感じるということ。無個性なことからそれを上手に使うと酒の味を引き締めるアルコールの、生(き)のままの味が感じられるのである。それはよくない。アルコールを舌に感じる酒は味に立体感がないのである。平べったい味わいになるのだ。
さらに米くさいということ。美酒にも出てくることがあるのだが、庵主が表現に困っているあの独特のおいが露骨に感じられるのがいけない。
しかし、そのにおいがあるゆえに、この酒はひょっとしていい酒ではないかとかえって不安を覚えるものがある。庵主の舌もいいかげんなものである。
念のため、うまい酒の瓶に詰め替えて呑んでみた方がいいかもしれない。そうすると、この酒はあら不思議、渋みを含んだしかも落ち着きのある辛口のきれいな酒になるかもしれないから。
●13/12/19

★広告する「立山」★
読売新聞の朝刊(平成13年12月13日付)に真ん中の頁の見開き2頁を使った広告が載っていた。一見して何の広告だかわからないけれど全面2頁を使って広告を打てるほど儲かっている会社だということはわかる。
余白をたっぷりとった贅沢な広告である。そのわりに文字が小さい。もともと読ませるための文章ではないようだ。レイアウトが先にあって、そこに当てはめるための文章に意味があるわけがない。レイアウトの美しさを感じてほしいといった酔狂が目的の広告だと庵主は見た。
左下に、清酒銀嶺立山とあるから日本酒の広告だということがわかる。日本酒のサントリーだと思った。広告はモダンなのである。使われているモノクロ写真は1色でもいいのに4色製版である。こっているのである。
レイアウト屋さんの美意識がなんの掣肘もなく遺憾なく発揮されている雅(みやび)な広告もいいけれど、しかも上品過ぎて読売新聞には似合わないけれど、こんなにいっぱい余白があるのなら、できればもっと実用的な記事を書いてほしいと思うのだ。うまい酒とそうでない酒の違いを読みやすい大きい文字できちんと啓蒙してくれたなら全部読んじゃうのに。
広告は、ウソでもいいから、うちの酒はこういう美意識で造っているのだからこんなにうまいと書いてほしいのである。酒呑みの買う気を上手にそそってほしいのである。
とはいえ「立山」はちょっと気になる酒である。そのくせ庵主は「銀嶺月山」をよく「立山」と間違えて呑んでしまう。呑み直そうと気づいたときにはすでに酔いがまわっていて次がないものだから、なかなか「立山」にたどりつくことができないのである。
ところで、「立山」は東京で売っているのだろうか。あまり見かけることのない酒である。広告では聞くが庵主の目にははいってこないそれは幻の酒なのである。
荒木町の「とらたつま」には「立山」があったが、どんな味をしていたが全然印象に残っていない。まずい酒なら恨みをこめて(蔵元にではなく、そんな酒をうまいといってすすめてくれた酒亭に対してですよ)記憶に残っているから、全然おぼえていないということは悪い酒ではないということなのである。
ただ本当のところをいうと、「立山」、「月山」、「八海山」と庵主は山登りの趣味がないのである。美しい山は遠くから眺めているのがいい。
●13/12/16

★溝口直次入魂の酒★
達筆な筆文字「槽口直汲」を溝口直次(みぞぐち・なおじ)と読んだ人がいるという話を書いたことがある。庵主のことである。
それ以来、庵主は溝口直次という名前を架空の杜氏の名前として温存しているのである。
その名杜氏が醸した酒が手にはいった。ほとんど幻の酒といっていい酒である。たぶん本数が少ない酒だと思う。実在することは確かであるが手にはいらないのである。一般的にどこでも手に入る日本酒にはあまりうまいと思う酒はないというのが庵主の実感である。酒の造り方が違うからである。
うまい味を追求した酒と、多少保管がいいかげんでも呑むことのできる酒質を求めた量産酒との違いである。よしあしではなく、販売政策の違いが味の違いとなっているのである。
それは日本酒度−16の酒である。甘い酒が好きな庵主の気をひく酒である。「純米吟醸 仕込第参拾弐號」と書かれた酒は「13.9.」(13年9月)の瓶詰であるが、上槽年月日は1998.2.2となっている。三年間の眠りから目覚めた酒である。
日本酒度がマイナス(甘口の酒とされる目安である)の酒が必ずしもうまいわけではないが、時に庵主好みの清冽な甘い酒と出会うことがある。この酒は庵主ごのみの甘い酒である。甘いからたくさん呑めないことはいうまでもない。すぐあきるからである。でもこの酒はいい。うまい。
「これは苺に合う酒である」という。「ブルーベリーと一緒に呑んでもおいしい」ともいう。ね、どんな酒かちょっと呑んでみたいお酒でしょう。
そういうお酒を造るのである、「秋鹿」は。
ラベルには「Funakuchi Jikagumi」と書かれた酒なのでご紹介した次第。
●13/12/14

★今夜も「白雪」★
大手蔵の酒は、多くの日本酒マニアがそうであるように、庵主もめったに呑むことはない。もっともそれが向こうからやってきたときは拒むものではない。ありがたく頂戴することにしている。
そうはいうものの呑みたいという誘惑にかられる他のうまい酒がたくさんあるものだから、それらの酒を呑む順番はどうしてもあとまわしになるということである。
酒を呑むのなら、やっぱりうまい酒が呑みたいから。
過日「白雪」の純米酒上撰を呑んだことから、同じ「白雪」の純米酒、クラシックシラユキを呑んでみることにした。庵主は能書きが大好きだからつい手にとったのである。
「三十年の時間からの贈り物
選びぬかれた米と水を
鍛えぬかれた伝統の知識と技で醸しても
どうしても超えることのできないものがあります。
それは生命をはぐくみ
そしてつかさどる時間という名の神秘。
タイム・カプセルEXPO'70の中で
30年間生きつづけた麹菌があります。
その麹菌を使って仕込んだ酒、クラシックシラユキ。
生命の力、時間の神秘を五感で味わいながら
お召し上がりください。
一九七〇年大阪万博開催の時に毎日新聞社と松下電器産業に
より埋設されたタイム・カプセルEXPO'70から30年の歳月を生き
続けた当社の麹菌が発見されました。」
きりりとした味である。辛口といえる酸味を感じる。うまいか、と問われたら、庵主の好みの方向ではないと答える。
四合瓶で1000円税別の酒である。
庵主ならあと数百円を出して、火入れであっても「冬樹」を呑みたいと思う。好きな酒を呑むほうがずっと楽しいからである。
●13/12/12

★赤米酒★
赤米(あかまい。あかごめ、とも読む)で造ったお酒が送られてきた。
赤米は、穂が長くて倒伏(稲穂が倒れる)しやすいとか離粒性(籾がすぐこぼれてしまう)が高いということから、今となっては商品性がなくなってしまった米で、古代米として一部の神社などで細々と作られている米である。
文字どおり赤い色をした米である。といっても米粒の表面がほんのり紅茶色といったところだろうか。中は白い。赤いというよりはちょっと褐色がかかっているといったほうがいいかもしれない。だんだん赤くなくなってきたが、それでもやっぱり赭(あか)いので赤米という。
この米でなら赤い着色料を使わなくてもちゃんと赤飯ができる。おめでたい米である。
お米センターなどで売られているので手にはいらないことはないが、ふつうはお目にかかることがない米である。だからめずらしい酒なのである。
丹後の芦田行雄先生が植えた赤米が豊作で、その赤米で造ったお酒であるから由緒正しいお酒である。
色はワインのローゼ色。味も日本酒というよりはワイン風といった感じである。米の由来は古いが味はモダンである。
ふつうの日本酒は精米歩合70%ぐらいまで磨いて造るのだが、この酒はそこまで磨くと赤い色がでないということで、なんと精米歩合95%という驚異的な酒なのである。米粒の外側5%を糠として落としただけなのである。赤米を70%も磨くと、米の芯の方は白いから普通の酒と変わらなくなってしまうからである。
家庭で日本酒を密造するときに使うごくふつうの食用米でさえ精米歩合は92%といわれているのだから、こと精米歩合からいうとこれは日本酒ではないといっていい酒なのである。これで酒ができるのなら、70%も精米しているにもかかわらず、時々お目にかかるまずい酒は立つ瀬がないではないか。
だが、この赤米はけっこういい味なのである。あえてうまいとは書かないよ。リキュール感覚で呑めるなかなか優雅なお酒なのである。
赤米の珍しさと色のおめでたさを楽しむことができるありがたいお酒である。
京都府弥栄町出身の「弥栄鶴」(やさかづる)から「赤米酒」として販売されている。お酒には小さな袋にはいった赤米がついている。
●13/12/10

★意表をついてくる酒亭★
その酒亭がほかの店とちがって楽しいのは意外性があるからである。
庵主のような日本酒マニアになると、呑み手としては十分にすぎる日本酒の知識をもっていて、一通りのいい酒も呑んでいるから能書きだけはいくらでも語ることができて、雑誌の酒の特集などもよく目を通しているのでおりおりの酒の流行(はやり)も心得ているから、めったな酒を見せられても驚かなくなっているのである。イヤナ客。
せっかく酒亭のご主人が見つけてきてくれた「龍勢」を、「ご存じですか」と聞かれて「広島の藤井酒造でしょう。以前に番外酒を呑んだことがありますが、いい酒ですよね」と応じていいものか、ためらうときがある。
「その酒知ってるよ」とたまたま知ってることをひけらかすしてご主人の感激をそぐこともないだろうと思うからである。うまい酒を見つけた喜びのほうを共有したいと思うのである。酒をおいしく呑むということはその旨さを人と共感するということなのである。「うまいでしょう」「ん、うまいねぇ」と。
この画家の絵は絶対いいと一人で思い込んでいても、それに共感する人が他に一人もいないとしたら、こんな心細いことはない。そしてちっともおもしろくない。
酒も人と共感してうまくなるのである。
その酒亭はそういうヒネタ(老ねた、ではない)呑み手に意表をついた酒をさりげなく出してくるのである。今度は何が出てくるのかと、その瞬間のスリルとサスペンスがたまらない。
その夜も、出てきた一杯は「開春」の「限定中取り 生 純米 流霞」である。「開春」は有名な酒である。うまいに決まっている。だが、その中から選び出した酒がいいのである。絶妙なのである。
甘い酒で、庵主好みである。が、ラベルを見ると日本酒度は+6.8と書かれている。この数字ならかなり辛口の酒なのだが、先だって呑んだ「醴泉正宗」は+3でも相当の辛口と感じる味わいだったのに対して、この酒は逆に甘く感じられる。
酸度は1.8となっているから、「醴泉正宗」の1.5より高い。酸度からみてもこの酒のほうが辛口の感じになると思われるのだが、呑んでいる酒の味わいは甘いのである。
データーとはちぐはぐな味わいの妙。こういう不思議な楽しみをその居酒屋では体験することができる。だからおもしろいのである。
あ、「与太呂」の荒木町店である。
●13/12/5

★赤米酒★
赤米(あかまい。あかごめ、とも読む)で造ったお酒が送られてきた。
赤米は、穂が長くて倒伏しやすいとか離粒性(籾がすぐこぼれてしまう)が高いということから、今となっては商品性がなくなってしまった米で、古代米として一部の神社などで細々と作られている米である。
文字どおり赤い色をした米である。といっても米粒の表面がほんのり紅(あか)いのである。中は白い。赤いというよりはちょっと褐色がかかっているといったほうがいいかもしれない。だんだん赤くなくなってきたが、それでもやっぱり赭(あか)いので赤米という。
この米でなら赤い着色料を使わなくてもちゃんと赤飯ができる。おめでたい米である。
お米センターなどで売られているので手にはいらないことはないが、ふつうはお目にかかることがない米である。だから珍しい酒なのである。
丹後の芦田行雄先生が植えた赤米が豊作で、その赤米で造ったお酒であるから由緒正しいお酒である。
色はワインのローゼ色。味も日本酒というよりはワイン風といった感じである。米の由来は古いが味はモダンである。
ふつうの日本酒は精米歩合70%ぐらいまで磨いて造るのだが、この酒はそこまで磨くと赤い色がでないということで、なんと精米歩合95%という驚異的な酒なのである。米粒の外側5%を糠として落としただけなのだから。赤米を70%も磨くと、米の芯の方は白いから普通の酒と変わらなくなってしまうからである。
家庭で日本酒を密造するときに使うごくふつうの食用米でさえ精米歩合は92%といわれているのだから、こと精米歩合からいうとこれは日本酒ではないといっていい酒なのである。これで酒ができるのなら、70%も精米して造られた時々お目にかかるまずい酒は立つ瀬がないではないか。
だが、この赤米はけっこういい味なのである。あえてうまいとは書かないよ。リキュール感覚で呑めるなかなか優雅なお酒なのである。
赤米の珍しさと色のおめでたさを楽しむことができるありがたいお酒である。
京都府弥栄町出身の「弥栄鶴」から「赤米酒」として販売されている。お酒には小さな袋にはいった赤米がついている。
●13/12/3

★JSA★
絶対JAS(ジャス)と読んでしまう。航空会社ではない。「JSA」である。韓国映画である。
封切りのときに見逃してしまった。庵主はテレビを持っていないので、映画館で見落とすと二度と再びその映画(しゃしん)を見ることができない。するときまってあとから見落とした映画のことを称賛する文章にであって臍(ほぞ)をかむことが少なくない。
さすがは東京だ。ちゃんとスクリーンに映してくれる劇場(こや)があった。最終日の最終回に間に合った。
38度線を挟んで北と南の二人が写っている写真がラストシーンである。この映画を見た人にはその深い意味がわかる。知らなければ板門店で撮ったただの一枚の写真である。
事件の調査を任された女士官が解任されることになった時に個室に戻って机の上に立てかけてあった写真をたたんで帰任する場面。その室内に差し込んでくる窓からの光のきれいないこと。そのせつない光に庵主は涙するのである。この映画はおいしい映画だ、と。そして開巻の梟(ふくろう)を撮った画面の美しいこと。昔の大映映画の技をみるようななつかしさをおぼえたのである。
はじめはわからなかった北と南の兵士の顔の区別がつくようになってくる。
南の兵士は豊かな文化(物)にめぐまれて軟弱化したやさしい顔(お醤油顔)、北の兵士は飢え(物でも文化でも)をただよわせた栄養欠乏を感じさせる顔(唐辛子顔)なのである。そういう配役なのである。
北と南の兵士が北側の監視小屋の中で酌み交わしていた酒はどんな酒だったのだろうか。「真露」みたいな焼酎か、あるいはマッコリみたいな酒なのか。北朝鮮の酒は輸入されているのだろうか。新大久保あたりで探してみよう。
「一、すじ。二、ぬけ。三、役者」ということばがある。映画で一番大切なのは筋=脚本、次に抜け=画面の美しさ、そして一、二が揃っていれば役者はだれでもいいといったところである。
「JSA」は一よし、二もきれい、三もいいのである。まだ神話が残っている国の映画はおもしろい。作り手と観客の間に共通の思いがあるから手放しで楽しめるからである。
しかしこうして出来のいい商業映画を見ると、アメリカのタリバン爆撃のシナリオの下手くそなことがよくわかるのである。「勇敢フジ」とか「日癇ゲンダイ」などの連日の一面の見出しが、あらかじめアメリカ政府(アメリカ人にではなく)に都合のいいように書かれたストーリーにそって出てくるものだから底がわれてしまう。
それらは娯楽新聞だからだれも文句はいわないのだろうが、一般新聞で裏もとらずに片方の一方的発表を書き連ねたらその新聞は信用を失墜すること必至である。あ、それで最近は新聞を取る人が減っているのか。
●13/12/1












