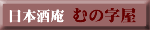
むの字屋の美術品の部屋
むの字屋が心ひかれて買い求めた美術品をおさめています。どうぞごゆっくりご鑑賞ください。
絵の大きさは同率で縮小したものではありません。[押]をクリックしてサイズをご確認ください。

 青いボタンをクリック
青いボタンをクリック
すると大きなサイズで
絵を見ることができます

|
平野 遼の「コーランを唱える人」
平野
遼(ひらの・りょう)の水彩画である。
小品であるがその静謐感に庵主は心ひかれた作品である。庵主は平野遼の絵が好きで、せめて1点は身近においておきたいと思っていた。
絵の販売業界では、どういうわけか水彩画に比べると油彩の絵はその何倍も高く売られている。それが庵主には理解できない。絵のよしあしではなく、絵の具の違いで値段が全然違うのである。看板なら製造原価の違いということで理解できるのだが。
庵主がほしいと思う油彩は高くて買うことができない。ちなみに庵主はいい酒が呑めないほどの赤貧ではないが、まとまった物を買うことができるほどの財はない。要するに世間並みの貧乏人なのである。そのような中でなんとか絵を手にいれることができたのは水彩画が油彩より販売価格が安いというしきたりのおかげである。いいしきたりである。
水彩画は安いといっても、あたりまえのことだが下手な油彩より味があることは酒の世界と同じである。絵は作品のよしあしに価値があるのだ。
なお、この絵は、作者によると「コーランを唱える人の朗々たる祈り声が教会いっぱいに響きわたりその余韻に酔った」とある。
静かな場面を描いた絵ではないのである。しかし庵主はこの絵に静謐を感じてならないのである。
|

 青いボタンをクリック
青いボタンをクリック
すると大きなサイズで
絵を見ることができます

|
岩谷徹の「月の光 大」
岩谷 徹(いわや・とおる)の版画である。
銅版画の作品でメゾチントという技法によるモノクロの版画である。メゾチントの黒は精神の深みをたたえた黒である。いちどその黒の美しさを知るといい作品がほしくなる。
メゾチントの、テクニックが上手な作家は多いがそれが精神性をたたえた作品は少ない。美しいだけでそれ以上に心が引かれないのである。
この版画は大きい画面で見てほしい。深い孤独感と永遠の生命を感じるのである。その印象は作者からこの作品を制作したときの状況を聞いて間違ったものではなかったことがわかった。
この版画のよさがわかるまでにたどった庵主の歩みは話すと長くなるのでそれはまたいずれかの機会に書くことにして、いまはこの版画のもっている趣のよさを感じていただけたなら知音を得た喜びがわいてくるのである。
「芸術品の声価を高めるということは、その作品の味わいに共感できる人をふやすことである。人がまだ気がついていない美を見いだして伝えることである」と、ある画廊主が言っていたことを思い出した。
いい酒、いい絵、心ゆたかな時間。
|

 青いボタンをクリック
青いボタンをクリック
すると大きなサイズで
絵を見ることができます

|
三田村和男の「お気に入りの飾り」
三田村
和男(みたむら・かずお)の一見リトグラフにように見えるが実は手描きの作品である。
この軽快な色遣いがここちよい。
三田村和男の色は明解な赤であり、青であり、緑である。本来感情をもたないそれらの色が絶妙に組み合わされるとリズムを生んで心をはずませる豊かな感情を醸し出すから面白いのである。
命がないはずの色彩が作家の感性によって組み合わされると生命感を発するようになるから不思議なのである。しかもにぎやかな赤が少しもうるさくないのである。うるさい絵は見ていて疲れる絵である。そういうことがないのだ。
その色彩の妙からはたたみかけてくるような朗らかさを感じて、見ているうちに心が軽やかになってくる。その色彩の力に、色の構成力に「感動する」のである。なんでも感動する小泉総理みたいに安直に感動したというのは芸がないとは思うが、庵主の美意識にしみてくるのである。
この作品を見ていて気持ちがよくなるのは、絵が心を揺さぶるということを実体験して作品がもっている感性に共感した自分の心にやわらかい感受性を覚えてふとほほえむことができるからなのである。
心の凝りを解放する力をこの作品は秘めているからなのである。
|

 青いボタンをクリック
青いボタンをクリック
すると大きなサイズで
絵を見ることができます

|
大沢昌助の「女」
大沢
昌助(おおさわ・しょうすけ)の感覚はなんと若々しいのだろう。そしてなんてモダンなのだろう。絵を描くことを楽しんでいる自由闊達な気分を感じて気持ちがいい。
庵主が初めて大沢昌助の絵に出会ったのはたしか銀座和光での展覧会だったと思う。シンプルな色と思い切りのいいすっきりした線を見て、才気の発露としかいいようのないおしゃれな絵を描く人だと思った。庵主の想像を絶したその色遣いと、庵主なら思いもつかない心地よい線の絵をみて、いつかは大沢昌助の絵がほしいと憧れたものである。
歳月が流れて、いまその思いがかなった。いいお酒が向こうのほうからやってくるように、大沢昌助の小品が向こうの方からやってきた。もちろん庵主にとっては腹をくくらなければならない金額だった。腹をくくったのである。
じつは庵主は、この作品を見て初めは何が描かれているのかわからなかった。ただきれいな色遣いが気持ちいい絵だと思っていた。なるほど色はこういうふうに使うと気持ちよく感じるものなのだと、大沢昌助の感覚に感心していたのである。
そして、突然絵が見えたのである。その瞬間にこの絵から離れなくなってしまったのである。
|
| |
|





